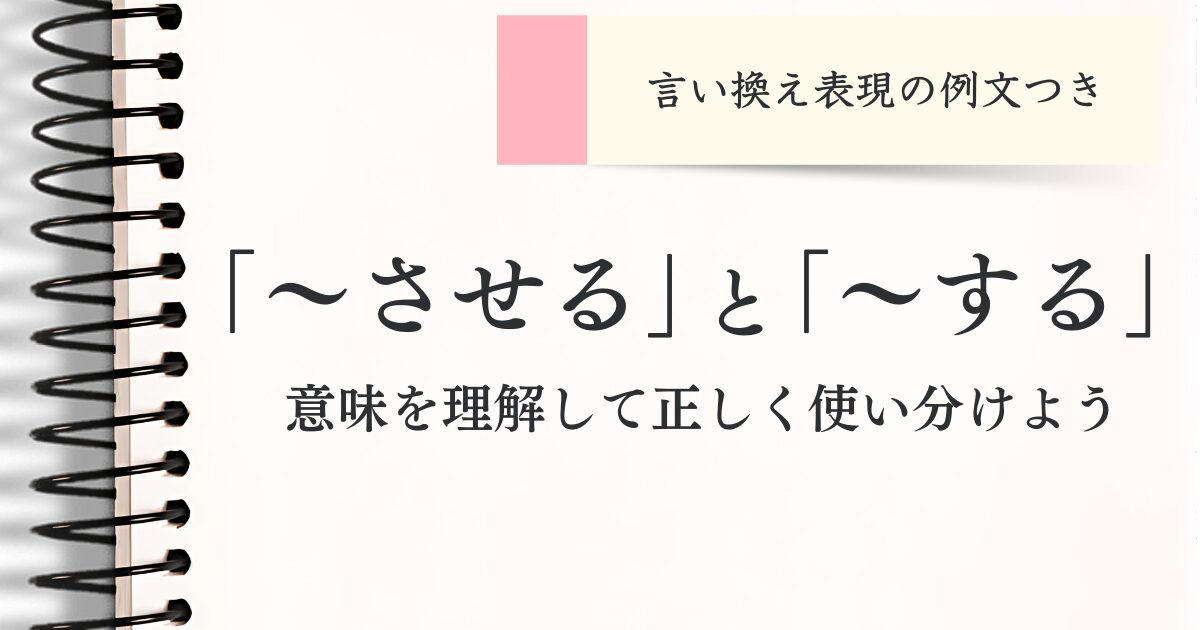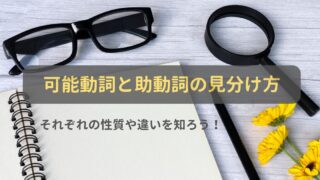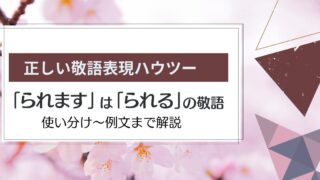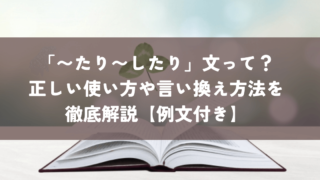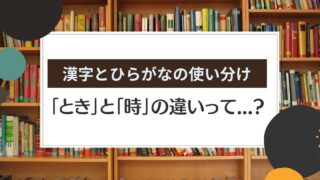「させる」と「する」は、どちらも日常会話やビジネスシーンで頻繁に使われる表現ですが、使い方を誤ると意図しない意味になってしまうことがあります。
たとえば、「勉強する」は自分が勉強することを意味しますが「勉強させる」は、他人に勉強をさせることを意味しますよね。
一見すると当たり前のことですし、普段は自然と変換しているかもしれませんが、これらの違いを正しく理解することは、円滑なコミュニケーションを図るうえで非常に重要です。
そこでこの記事では、「させる」と「する」の違いや使い分けのポイントを、例文を交えてわかりやすく解説します。正しい日本語表現を身につけたい方は、ぜひ参考にしてください。

「させる」と「する」それぞれの意味は?
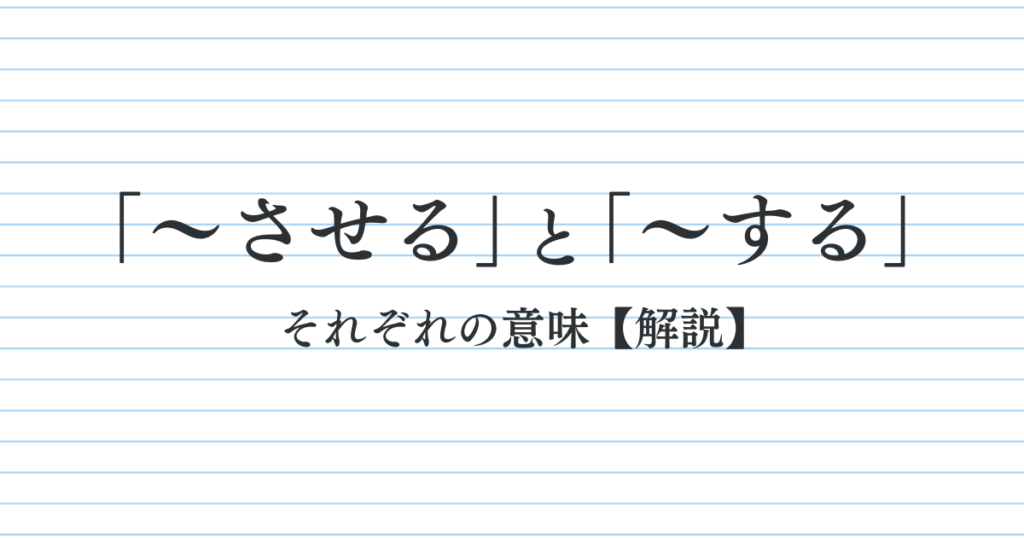
「させる」と「する」は、それぞれ意味が異なります。
両者の意味を把握することで、正しい使い方ができるでしょう。
「させる」の意味

「させる」は人に対して何かを行わせる「使役」の意味を持つ助動詞です。
- 使役…ある動作を他人に行わせる
- 助動詞…他の語をサポートし意味を補強する語
「させる」の使い方は、以下のとおりです。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 親が子どもにピーマンを食べさせる | Parents make their child eat green peppers |
| 医師が患者を入院させる | The doctor makes the patient get admitted to the hospital |
相手に強制したり指示したりするときに「させる」を使用します。
「する」の意味

「する」は、ある動作や行為などを行うといった意味を持つ動詞です。
動詞…主語の行動や状態を示す。
たとえば、以下のように使用します。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 私が車を運転する | I drive a car |
| 私が病院に入院する | I am admitted to the hospital |
自発的に行動する場合や想定外の結果になってしまったケースなど、多種多様な場面に用いられます。
「させる」と「する」の違いと使い分け
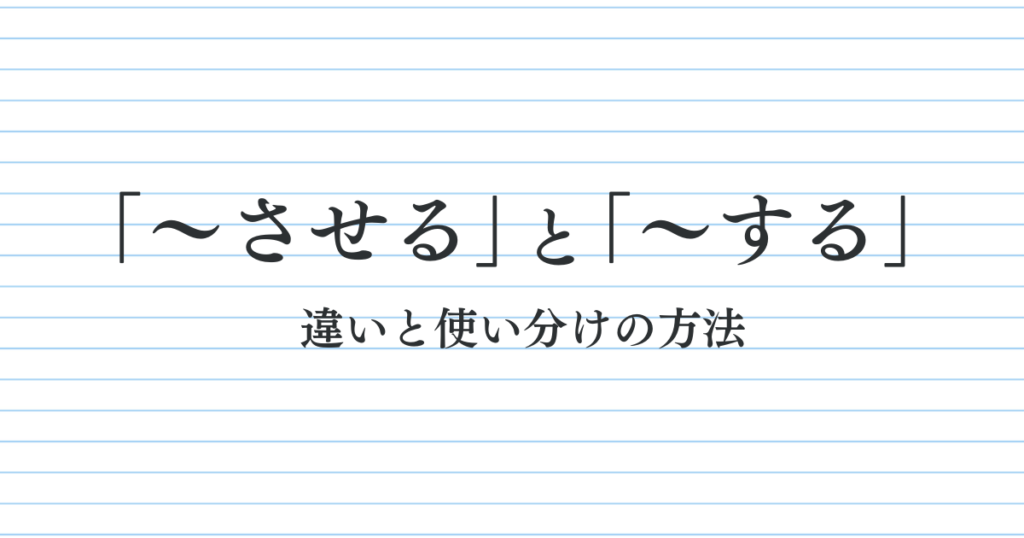
「させる」と「する」の主な違いは、以下の3つです。
| させる | する |
|---|---|
| 動作の対象を必要とする | 動作の対象を必要としない |
| 動作に直接影響を与える | 動作に直接影響を与えない |
| 「~を」に付く | 主語や対象に「~が」「~に」が付く |
違いを把握したうえで正しく使い分ければ、円滑なコミュニケーションが可能になるでしょう。
それぞれ使い分けるポイントを解説します。
「させる」

「させる」は、動作の対象を必要とする他動詞に該当します。
以下のように「~を」に付くのが一般的です。
教師が生徒に勉強をさせる。
たとえば、他動詞を「~が」に付けた例文においては、日本語として違和感しか残りません。
教師が生徒に勉強がさせる。
「~が」に「させる」を付けて違和感が残る場合は「させる」を使用します。
なお、英語で「させる」は「Make」です。
「する」

「する」は、動作の対象を必要としない自動詞です。
以下のように、主語および対象に対して「~が」や「~に」に付くのが基本です。
- 電車が駅に到着する
- 子どもが図書館で勉強する
主語や対象に対して「~を」を付けた場合、違和感の残る文章になります。
- 電車を駅に到着する
- 子どもを図書館で勉強する
主語や対象に「~が」や「~に」を付けて違和感が残る場合は「する」を使いましょう。
英語で「する」は「do」または「perform」です。
それぞれの意味は以下のとおりです。
| do | 日常的な行動に対して使われる |
| perform | スキルや準備が必要な活動をするときに使われる |
「させる」の言い換えとは?3種類をそれぞれ解説【例文付き】

「させる」を使った文章は、高圧的な印象を与える場合があります。
相手に不快感を与えないためにも、言い換えをマスターしましょう。
してもらう
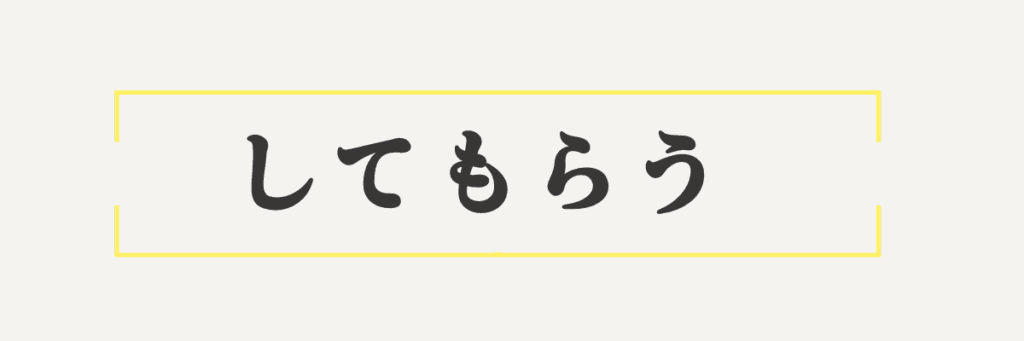
「させる」は「してもらう」に言い換えられます。
以下の例文では「してもらう」に言い換えることで、高圧的な印象を抑えました。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 子どもにリンゴを食べさせる | Make the child eat an apple |
| 子どもにリンゴを食べてもらう | Have the child eat an apple |
「させる」を「してもらう」に言い換えるだけで、強制のない文章になります。
していただく
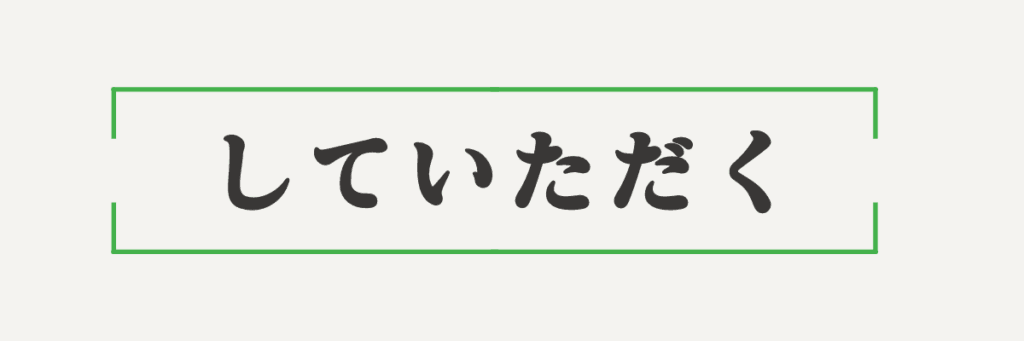
「させる」は「していただく」にも言い換えられます。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 先輩に資料を確認させる | Make the senior check the documents |
| 先輩に資料を確認していただく | Have the senior check the documents |
目上の人に対して「させる」を使うのは失礼にあたります。
とくに、ビジネスシーンにおいては、上記の例文のように「していただく」に言い換えるのが有効です。
さす
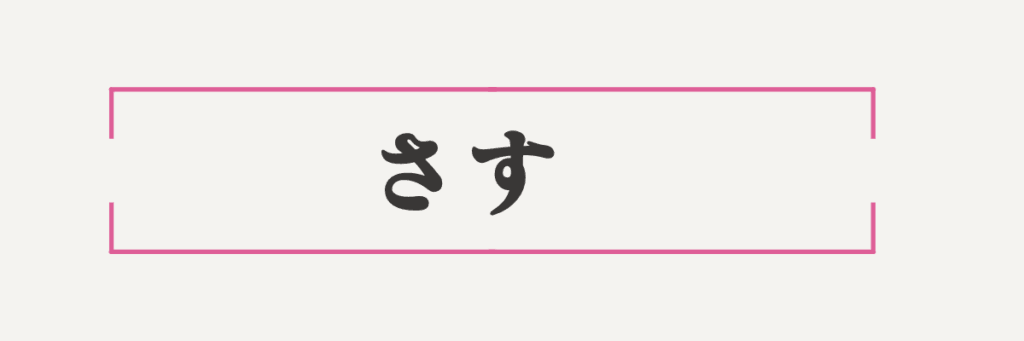
「させる」は「さす」にも言い換えられます。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 子どもに宿題をさせる | Make the child do their homework |
| 子どもに宿題をさす | Make the child do their homework |
「さす」に言い換えることで、カジュアルな印象になります。
日常会話においては「させる」を「さす」に言い換えると、親しみやすい印象を与えられるでしょう。
ただし、カジュアル過ぎる言い換えであるため、ビジネスや公的な場面では使わないほうが無難です。
「する」の言い換えとは?3種類をそれぞれ解説【例文付き】

「する」の言い換えをマスターすることで、表現の幅が広がります。
表現の幅が広がれば、コミュニケーションの質も向上できるでしょう。
「する」の言い換えを3つ紹介します。
やる
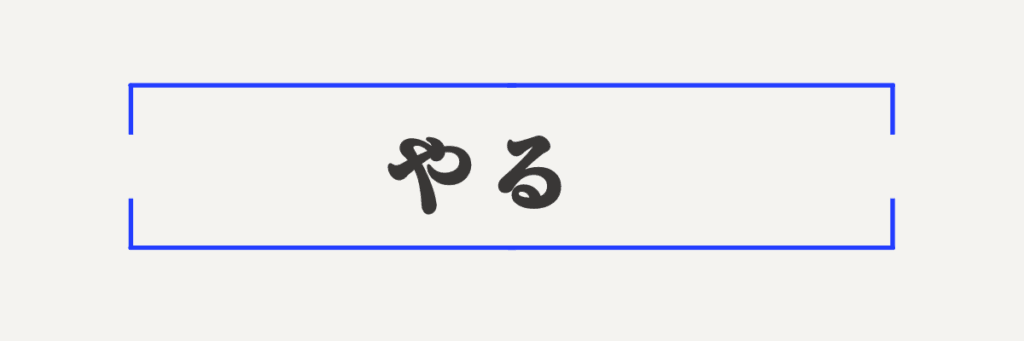
「する」は「やる」に言い換えられます。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 塾で勉強をする | Study at the cram school |
| 塾で勉強をやる | Do studying at the cram school |
「する」を「やる」に言い換えたことで、カジュアルな表現になりました。
友人や家族と話す場面においては、上記のように言い換えるのもよいでしょう。
ただし、固定の表現や慣用句などにおいては「やる」に言い換えられないケースもあります。
たとえば、以下の例文では「やる」に言い換えると意味が通じなくなります。
- 会社に貢献する
- 会社に貢献やる
上記の例文のように「する」を「やる」に言い換えると、不自然な日本語になる場合があります。
「会社に貢献する」は「会社に貢献した」と言い換えるのが自然です。
行う
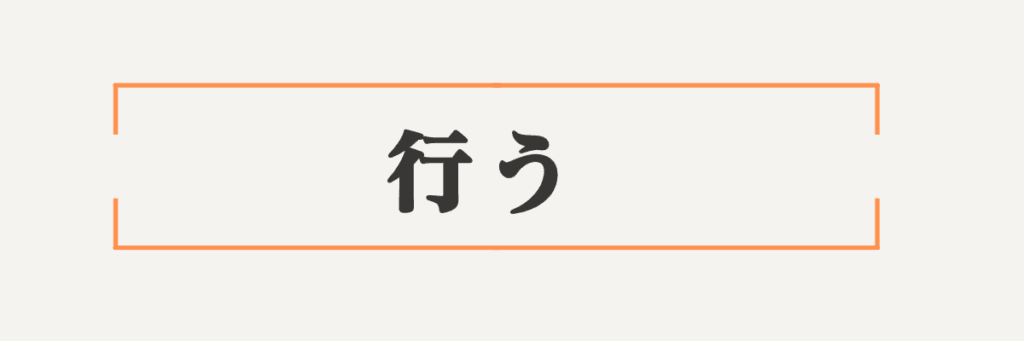
「する」は「行う」にも言い換えられます。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 上司に報告する | Report to the supervisor |
| 上司に報告を行う | Make a report to the supervisor |
「する」を「行う」に言い換えることで、丁寧な表現になります。
ビジネスシーンにおいて使える言い換えです。
ただし、言い換えると不自然な日本語になる場合もあります。
- 転職して新しい経験をする
- 転職して新しい経験を行う
上記の例文では「行う」に言い換えたことで、不自然な日本語になっています。
「経験する」は「経験を積む」と言い換えるのがベストです。
言い換えられない場合は、他の言葉に置き換えられないか検討しましょう。
不自然な日本語を使うと、相手とのコミュニケーションが取りにくくなります。
為す
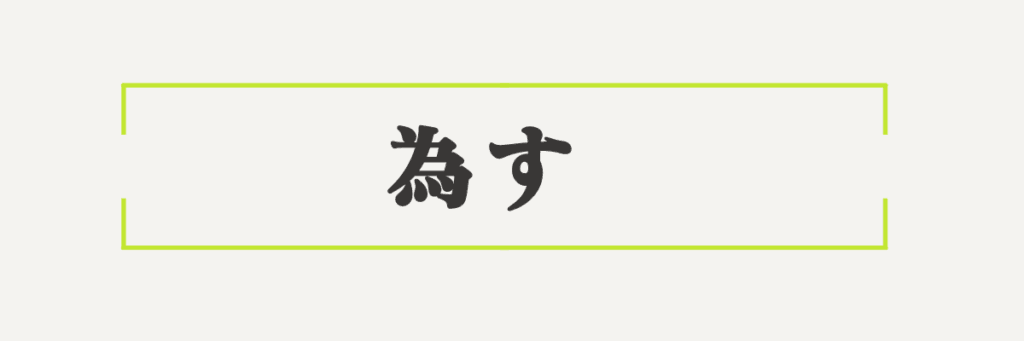
「する」は「為す」にも言い換えられます。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 目標を達成する | Achieve the goal |
| 目標を為す | Accomplish the goal |
「為す」に言い換えることで、格式のある表現になります。
ビジネスや公式の場面において有効な言い換えです。
ただし、以下のように意味が通じない言葉になる場合もあります。
- 宿題をする
- 宿題を為す
- メールをする
- メールを為す
上記の例文では、言い換えによって不自然な日本語になっています。
以下のように、言い換え自体をやめたり異なる言い換えをしたりするのがベストです。
- 宿題を為す→宿題をする
- メールを為す→メールを送信する
「する」を「為す」に言い換えると、かしこい印象を与えられます。
しかし、意味の通じない日本語になる可能性もあるため、無理に言い換えるのは避けましょう。
「させる」と「する」を使い分けるときの注意点
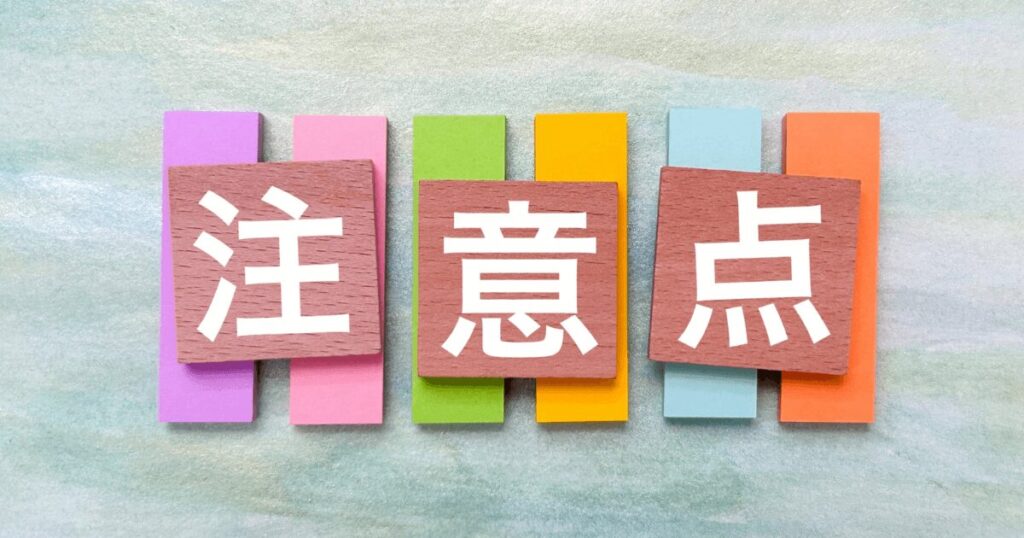
「させる」と「する」を使い分けるときは、以下の点に注意が必要です。
- 「させる」と「する」は意味が異なる
- 「させる」と「する」は対象の有無で使い分ける
- 多用することでくどい文章になるリスクがある
「させる」と「する」を正しく使い分けるためにも、注意点を把握しましょう。
意味の違いを理解する
「させる」と「する」は、文章が変わるほど異なる意味を持ちます。
| させる | 使役として誰かを動かす |
| する | 自主的な動き |
以下の例文のように、他人に対して使うのか、自分に向けて使うのかに分けられます。
| させる | パートナーに掃除をさせる |
| する | 私が掃除をする |
意味の違いを把握すれば、正しく使い分けられるでしょう。
対象があるかないか判断する
「させる」と「する」は、対象の有無で使い分けられます。
| させる | 対象がある |
| する | 対象がない |
対象がない場合に「させる」を使ったことで、不自然な日本語になっているのが以下の例文です。
私がさせる。
上記の例文では目的語が抜けており、誰に何をさせるのか不透明です。
「私が子どもに勉強をさせる」であれば、対象があるため自然な文章になります。
「させる」と「する」を正しく使い分けるために、対象があるかないかを判断しましょう。
また、他の対象に直接影響を及ぼすか否かでも「させる」と「する」を使い分けられます。
| させる | 他の対象に直接影響を及ぼす |
| する | 他の対象に直接影響を及ぼさない |
たとえば「教師が生徒に勉強をさせる」では、主語が「教師」で動作は「勉強」です。
「勉強する」のは「生徒」であるため、教師が生徒に直接影響を与えて勉強させることを表しています。
一方「電車が駅に到着する」の場合は、主語が「電車」で動作は「到着する」です。
「到着する」のは「電車」自体の動作であるため、他の物や人に直接影響を与えません。
対象があるかないか・他の対象に直接影響を及ぼすか否か、見極めたうえで「させる」と「する」を使い分けましょう。
多用しない

「させる」や「する」を多用することで、くどい文章になるリスクがあります。
以下は文中に「させる」を2回使用した例文です。
教師が生徒に宿題をさせて、翌日に提出させる。
上記の例文をシンプルに言い換えると、以下のようになります。
教師が生徒に宿題を出し、翌日に提出させる。
また「する」を2回使用した例文においても、しつこい文章になります。
今日は学校で勉強をして、家に帰ってから宿題をする。
上記の場合は、次のように言い換えましょう。
今日は学校で勉強し、家に帰ってから宿題をする。
「させる」や「する」を多用せず、他の言葉に言い換えられないか検討してください。
「させる」と「する」のパターンを覚えて正しい文章を作ろう!

ちょっとしたニュアンスの違いで、相手に与える印象も異なってしまうのが日本語です。
「させる」は、他人に強制する際に使う強い言葉です。
「する」は、自分が何か行動をする際に使う言葉になります。
目上の人には「させる」ではなく「していただく」を使うのがマストです。
ビジネスシーンでは「する」を「行う」と言い換えるのがベストです。
場面によって適切な言葉を使うことで、円滑なコミュニケーションが可能になります。
本記事を参考に「させる」と「する」のパターンを覚えて、正しい文章を作成してください。

「させる」と「する」に関するよくある質問

「させる」に関して疑問を抱いている方が大半です。
そこで「させる」に関して多く寄せられた3つの質問に回答します。
疑問を解決して、正しい日本語を使いましょう。
よくある質問①「させていただく」は間違いですか?
「させていただく」は間違いではありません。
「させてもらう」の謙譲語に該当します。
謙譲語とは、自分がへりくだることで相手を立て、敬意を表す敬語です。
ただし、以下の例文においては間違った使い方になります。
山田さんと同じ教室で勉強させていただきました。
「させていただく」を使うのは、以下の場合においてです。
- 相手側または第三者の許可を受けて行う場合
- そのことで恩師を受ける事実や気持ちがある場合
上記の例文では、山田さんに許可を取って同じ教室で勉強する必要はありません。
したがって、間違った使い方になります。
※参照:文化庁 敬語の指針
よくある質問②「さす」は方言ですか?
「さす」は和歌山県の方言です。
和歌山県では「はめる」を「さす」と表現します。
たとえば「手袋をさす」は「手袋をはめる」となります。
「させる」の言い換えとして活用する分には、カジュアルな印象を与えられるでしょう。
よくある質問③英語で「させる」はLetとMakeのどちらを使いますか?
英語で「させる」は「Make」を使用するのがベストです。
「Make」も「Let」も使役動詞ですが、意味が異なります。
- Make…強制的に何かをさせる
- Let…相手がやりたいことをさせる・許可する
「Let」は「Make」のように、強制力があるニュアンスを含みません。