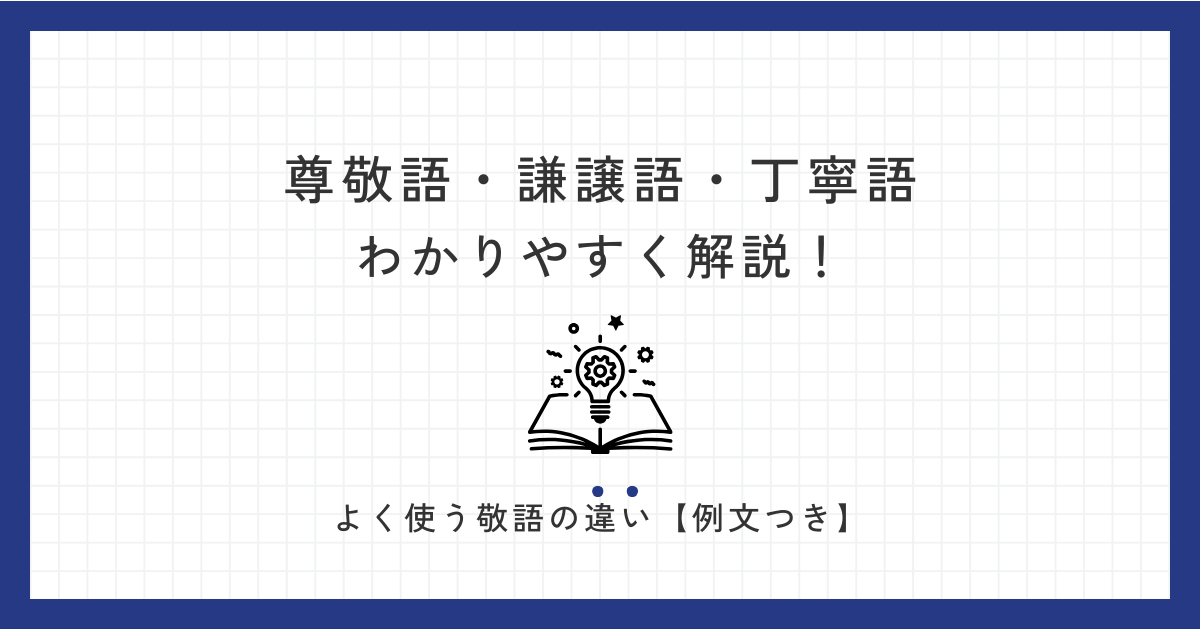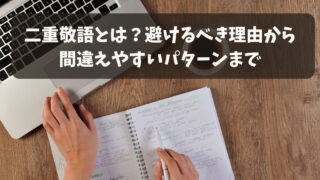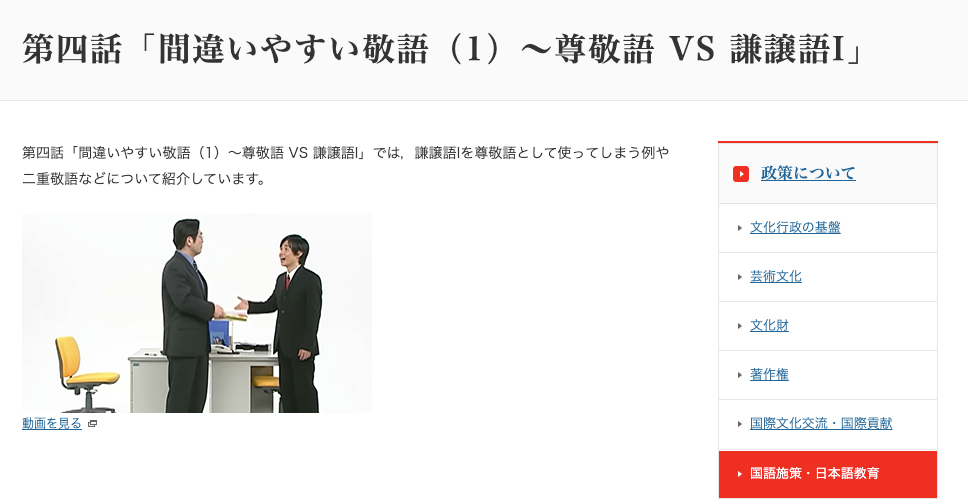敬語は、古来から息づく日本特有の言語です。
日本人の奥ゆかしさが表れる敬語はとても美しい言葉ですが、母国語であるにも関わらず、時には誤用しがちなのが難点です。
今回は、我々日本人でも難易度の高い敬語の種類と違い、つい間違えやすい言い回しなども例文をとおして学習していきます。
ここで改めて日頃の使い方を見直していきましょう!

敬語は『尊敬語・謙譲語・丁寧語』の3種類『例文つき』
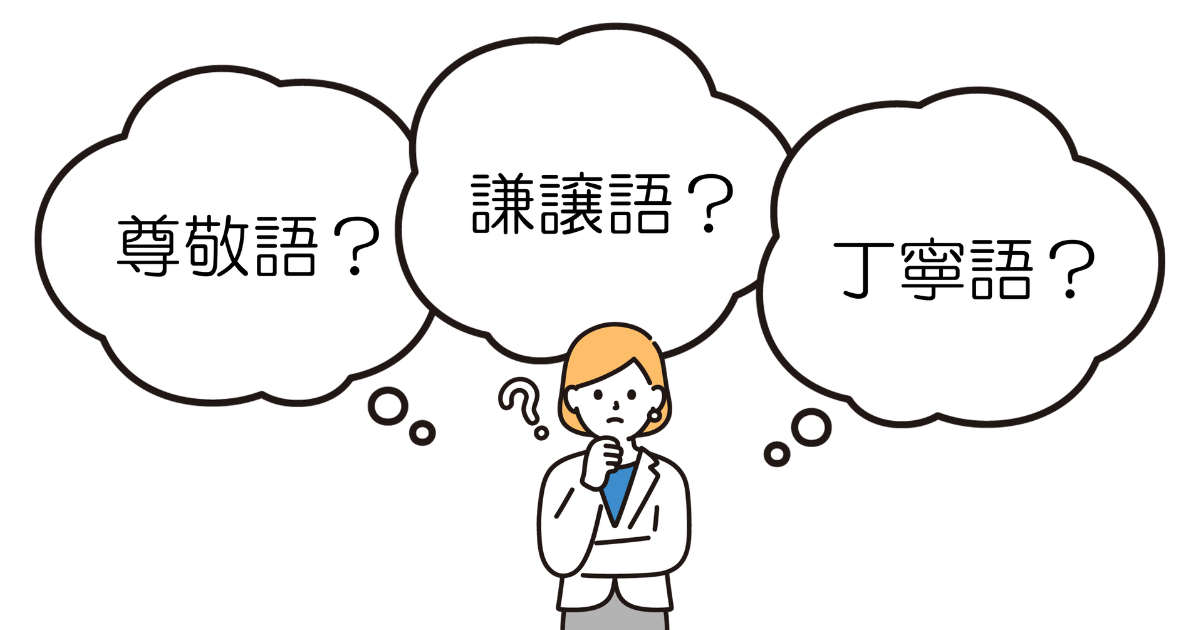
尊敬語・謙譲語・丁寧語の3つの要素から成る敬語は、それぞれで意味と使い方が異なります。
学生の時に一度は習ってはいるはずですが、説明できるまでに詳しく覚えている人はなかなかいないですよね…
まずは、それぞれの意味を復習していきましょう。
尊敬語とは「相手を立てる敬語」
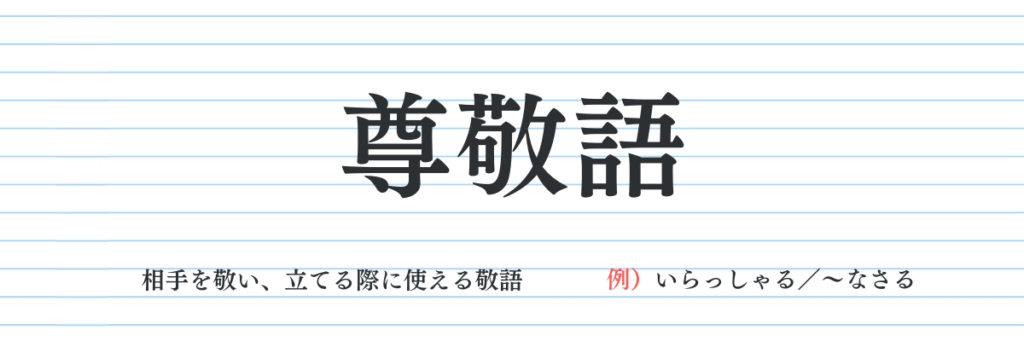
話し手が対象者を高めるときに使うのが謙譲語です。
つまり、
【尊敬語=相手を敬い、立てる際に使う敬語】…ということです。
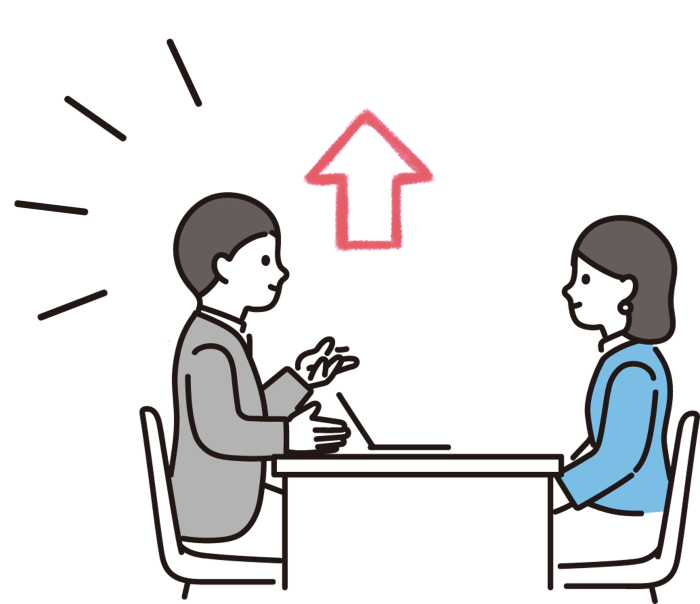
特に、目上の人や取引先の人や日頃お世話になっている人などに使われます。
では、実際の使い方を見てみましょう。以下の例文のうち、赤字の部分が尊敬語にあたります。
| 佐藤さんはこれからいらっしゃるそうです。 →佐藤さんを立てた言い方 いらっしゃる=行く |
| 明日は雨になるらしいのですが、ご存じでしたか? →聞き手を立てつつ質問 ご存じ=知る |
| 遠方からわざわざお越しになりました。 →対象者を立て、第三者に伝える文章 お起こしになる=来る |
いずれも、対象となる人物に対して丁寧な言葉で接しているのがわかりますね。
特に、取引先や役職付きの人に使うケースが多いでしょう。

謙譲語とは「自分がへりくだる敬語」
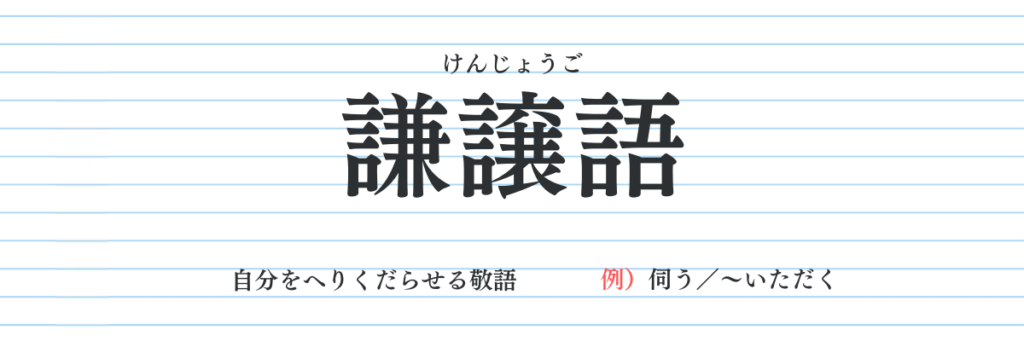
話し手自らの行為や身の回りに関するものに対して、自らを控えめに表現するときに使われるのが謙譲語です。
つまり、
【謙譲語=相手より自分をへりくだらせる敬語】…となります。
相手を敬う風習のある日本ならではの言葉遣いだと言えるように、謙譲語は自らを謙遜して相手を敬う際に使われます。

へりくだりゆずる・控えめな様子・自らを下に見て相手を立てる
| いただいた資料を拝読します。 いただく=受け取る・もらう/拝読する=読む |
| ドアまでお持ちします。 お持ちする=持つ |
| 日頃より格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。 賜る=受け取る |
なお、謙譲語はあまり使いすぎるとくどい文章になってしまうため、一度で多用せず必要な箇所のみに使うことをオススメします。
丁寧語とは「丁寧な言い回しをする敬語」
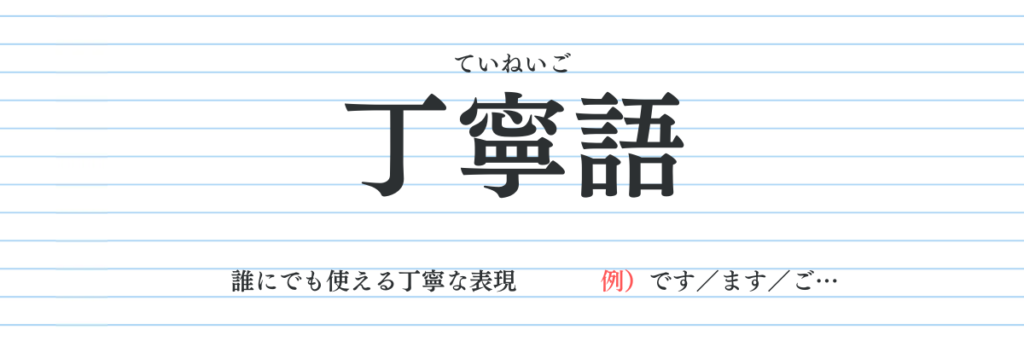
相手は問わず『です・ます』調で締めくくる言い方が丁寧語です。
つまり、
【丁寧語=誰にでも使える丁寧な言葉】
です。
日常的に使えたり親しい間柄でも使える気軽さから、子ども~大人に浸透している表現方法です。
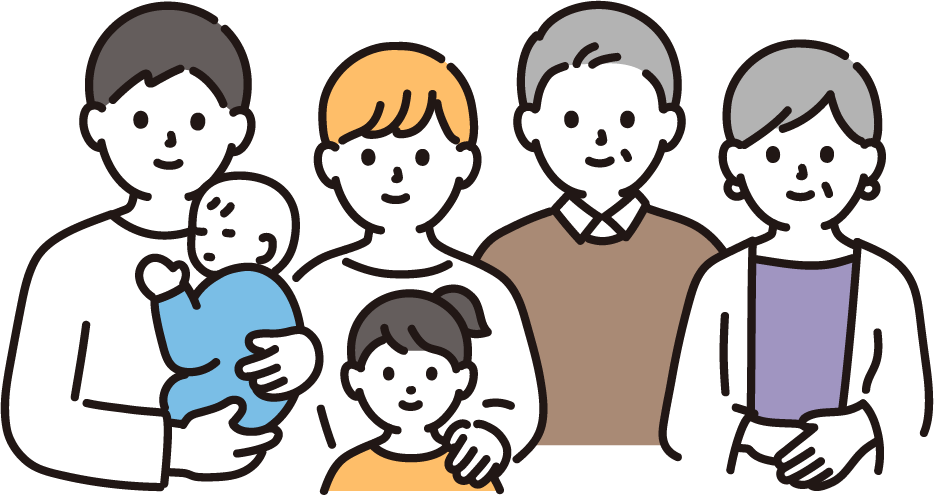
| この問題に答えられる人はいますか? います=いる |
| 夏休みは、おばあちゃんに会います。 会います=会う |
| その本をご覧になりましたか? ご覧=見る |
ちなみに、この記事自体も丁寧語で書いています!
謙譲語にある『3つの型』とその特徴

自分がへりくだる際に使う謙譲語には、細分化すると“3つの型”があります。
謙譲語は特にビジネスシーンで活躍するため、今一度その特徴とルールについて勉強していきましょう。
①特定の語句を言い換える型
1つ目は「特定の語句を言い換える型」です。
言い換える、ですのでそのとおり元の語句を他の語句で表現して謙譲語にします。
| 基本 | 謙譲語 |
|---|---|
| する | いたす |
| 言う | 申す |
| 行く | 伺う etc |
例を見てわかるように、元の語句から全く異なる単語に変化していますね。
次に、言い換える型の使い方を見てみましょう。
| 【『お目にかかる』は『会う』の謙譲語】 ✕ 社長にお目にかかってください。 〇 ぜひ社長にお目にかかりたく存じます。 |
| 【『承知する』は『わかる』の謙譲語】 ✕ この内容で承知してください。 〇 明日の会議はリスケとのこと、承知しました。 |
解説
誤った文章では、“相手を主として相手に行動を促す文章”なため謙譲語を用いてはいけません。相手が主となる文章では尊敬語を用いるのが正解です。
対して後者は“自らを主としている文章”なので正しいですね。
普段、相手が発言した敬語遣いに違和感を覚えた経験はありませんか?
謙譲語は基本となる語句を異なる語句に言い換えるため、咄嗟に出た言葉だとつい間違えてしまいがちです。
自分が使うときにも気をつけるようにしましょう。
②「お」「ご」+名詞の型
2つ目は「名詞の頭に『お』や『ご』のつく型」です。
例えば、ビジネスシーンでよく使う単語では以下のようなものがあります。
- お世話
- ご連携
- ご説明
いずれも自らの動作に「お」や「ご」がついています。
ビジネスシーンで使われる文章では、例えば以下のようなものがあります。
| 〇 いつもお世話になっております。 〇 資料をご連携いたします。 〇 後ほどご説明いたします。 |
解説
もし、上記から「お」や「ご」を取ってしまうと敬語表現ではなくなり、相手に対して中途半端に失礼な文章になります。
例えば「お」を取って「いつも世話になっております。」なんて取引先に毎回メールをしていたらどうでしょうか。
「いつも世話してくれててありがとう!」のようにフランクにも聞こえますし、本当にカタギの人間なのかと疑われるかもしれませんし、
受け手によっては「ちょっとバカにされてる?」と思われるかもしれない一言です。
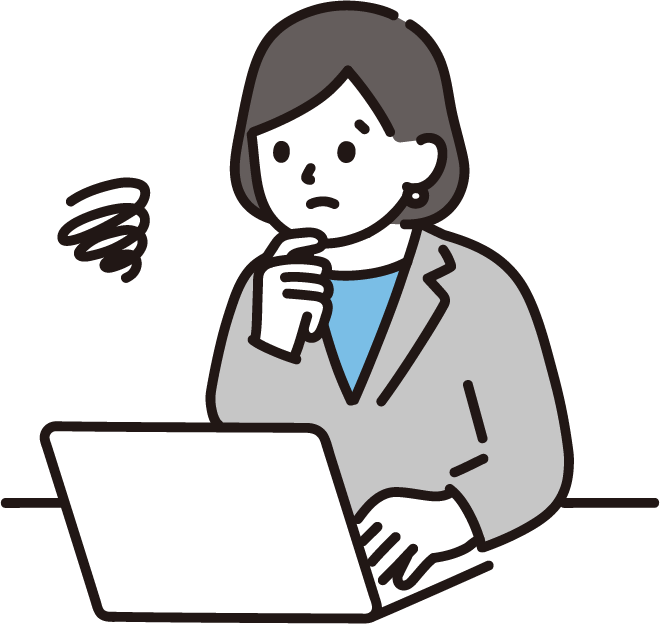
少々言い過ぎましたが…「資料を連携します」や「後ほど説明します」などはつい言いがちなため「お・ご」漏れには注意しましょう。
“自分が主となる動作に「お」や「ご」をつける”と意識していれば、取引先や顧客に対して失礼な連絡をせずに済みますね。
③「お」+「〜する」の型
3つ目は「『お』+『〜する』の型」です。
謙譲語なので、自らの動作に対して使います。
- お待ちする:待つ+お~する
- お探しする:探す+お~する
- お送りする:送る+お~する
特に、ビジネスシーンで使うパターンが多いように思います。
| 〇 明日10時にお待ちしております。 意味:私があなたを待っている |
| 〇 そろそろお暇します。 意味:私が帰る |
| 〇 お出口までお送りいたします。 意味:私があなたを出口まで送る |
解説
上記も自分が主語であり、自らの行動に対して語っていますね。
謙譲語の型のなかでは一番間違えにくい表現ではないでしょうか。
いずれにしても、謙譲語は自らが主となる文に用いると覚えてください。
謙譲語と尊敬語の違いとは?見分けるポイント
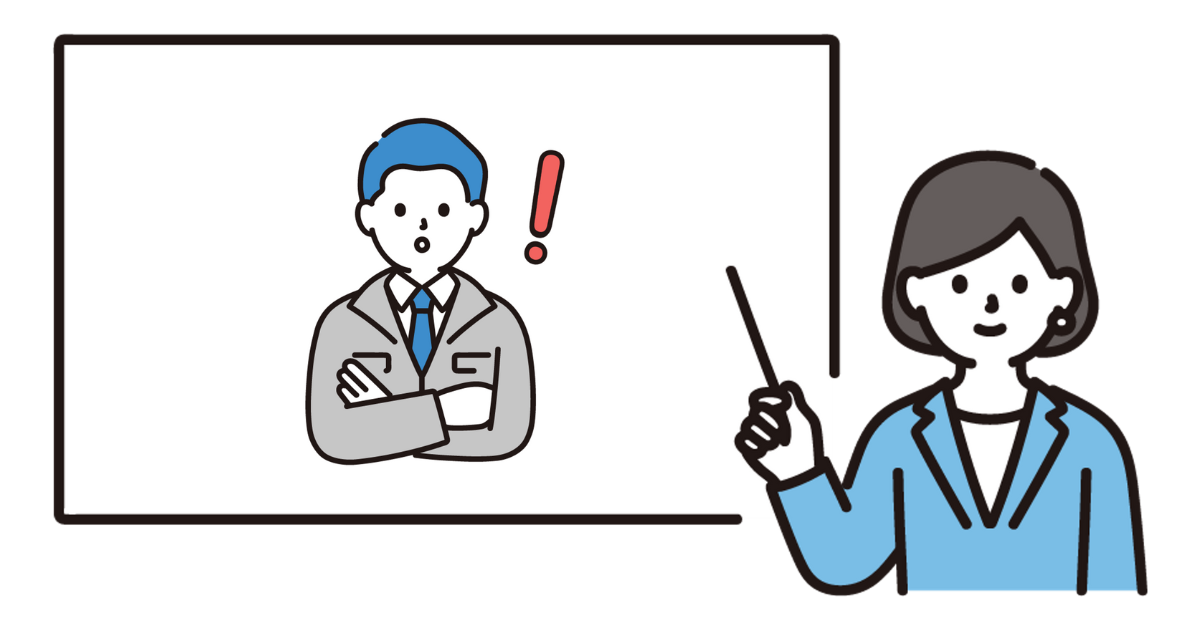
敬語の中でも特に混同しやすい謙譲語と尊敬語。
どちらも相手への敬意を示すための表現ではあるものの、使い方を間違えると真逆の印象を与えてしまうことも…。
そこで本セクションでは謙譲語と尊敬語の違いと、正しく見分けるためのポイントを分かりやすく整理していきましょう!
謙譲語の主語は自分

謙譲語は自身の行動に対して使う敬語で、主語は必ず自分になります。
そのため、使い方に迷ったときは“主語に「私」がつく文章になるかどうか”で判断できます。
では、以下の文章では「私は(が)〇〇する」の型になっているか見てみましょう。
| ✕ その件はご存じです。 →『ご存じ』は『知る』の尊敬語にあたるため適切ではない。 |
| 〇 その件は承知しています。 →『承知する』は『知る』の謙譲語なので適切。 |
▼解説
上記いずれの場合も主語に「私」をつけてみると適切な文章であるかがわかります。
前者の文章に「私」をつけると「その件であれば私はご存じです」となり、自分に対して“ご存じ”と表現するのは違和感がありますよね。
逆に、後者の「その件であれば私は承知しています」だと違和感がありません。
謙譲語を使う際は「私は(が)」が当てはまるかどうかで確認してみてください。
尊敬語の主語は相手

尊敬語は相手を立てる際に使うため主語は必ず相手になりますので、“主語に「あなた」がつけられれば正しい表現”です。
| ✕ あちらの椅子に座らせていただきお待ちください。 →「椅子に座って」と相手に動作を促しているが 「あなた」が主語となる場合、謙譲語『座らせていただく』を使うのは不適切。 |
| ✕ あちらの椅子にお掛けになられてお待ちください。 →【尊敬語『お掛けになる』+尊敬語『れる』】の形は二重敬語にあたるため不適切。 |
| 〇 あちらの椅子にお掛けになってお待ちください。 →相手に対して尊敬語『お掛けになる』を使っているため適切な表現。 |
▼解説
謙譲語と尊敬語の使い分けができない場合は、上記に主語「あなた」をつけてみると正しいかどうかがわかります。
「あちらの椅子にあなたが座らせていただきお待ちください。」だと、自分に使う敬語『座らせていただく』が含まれていておかしな文章です。
対して「あちらの椅子にあなたがお掛けになってお待ちください。」であれば、相手に使う敬語で間違いないことがわかります。
| 謙譲語 | 尊敬語 | |
| 主語 | 自分(私は) | 相手(あなた) |
特に、語句を言い換えて使う場合の謙譲語は誤用しがちなため、チャットやメールなどであれば送信前に必ず読み返すようにしましょう。
送信後に見返して気づいてしまったら…相当に恥ずかしい思いをします。
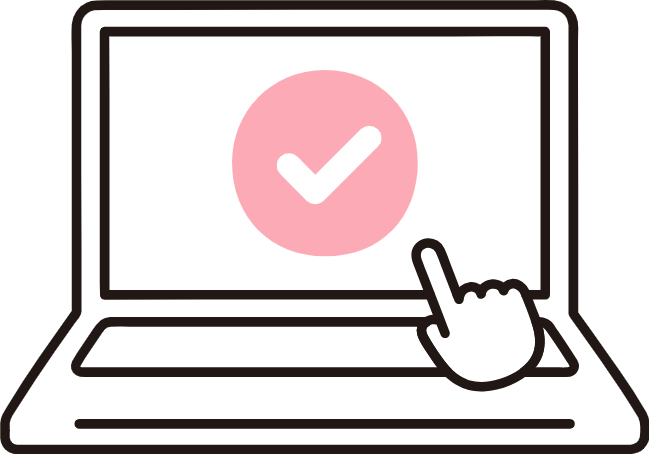
なお【二重敬語】の詳細は、以下の記事で説明していますので参考にしてください。
使われることの多い敬語の言い換え表現【一覧表】

ビジネスシーンや日常生活でよく使う【動詞の敬語一覧表15選】を用意しました。
イメージしやすよう尊敬語と謙譲語の例文もつけましたので、ぜひ今日から意識して使ってみてください。
| 基本 | 丁寧語 | 尊敬語 | 謙譲語 |
|---|---|---|---|
| 対象者問わず使える | 主語は相手 相手を立て敬う | 主語は自分 自身の態度を低くする | |
| 言う | 言います | 仰(おっしゃ)る 言われる | 申す 申し上げる |
| 【尊】お客様はそう仰いました 【謙】お願い申し上げます1 | |||
| 話す | 話します | お話しになる 話される | 申す 申し上げる |
| 【尊】社長が直接話されます 【謙】私から申し上げてもよろしいでしょうか | |||
| 行く | 行きます | いらっしゃる おいでになる 行かれる | 参る 伺う |
| 【尊】北海道へいらっしゃるのですか? 【謙】明日伺います | |||
| 来る | 来ます | みえる いらっしゃる お越しになる おいでになる | 参る |
| 【尊】ぜひまたお越しください 【謙】七五三の際はぜひお参りください | |||
| 聞く | 聞きます | お聞きになる | 伺う 拝聴する |
| 【尊】係の者にお聞きください 【謙】ご用件を伺います | |||
| 見る | 見ます | ご覧になる | 拝見する |
| 【尊】それではご覧ください 【謙】さっそく拝見いたします | |||
| 思う | 思います | 思(おぼ)し召(め)す お思いになる | 存じる 存じ上げる 拝察(はいさつ)する |
| 【尊】神様の思し召しです 【謙】多大なるご苦労があったと拝察いたします | |||
| 知る | 知っています | お知りになる ご存じである | 存じる 存じ上げる 承知する |
| 【尊】その噂、ご存じでしたか 【謙】その件は存じております | |||
| 会う | 会います | お会いになる 会われる | お目にかかる 見(まみ)える2 |
| 【尊】先生と会われたのですね 【謙】お初にお目にかかります | |||
| 考える | 考えます | ご高察される お考えになる | 検討する 拝察する |
| 【尊】ご高察されたとおり~ 【謙】一度持ち帰って検討いたします | |||
| 読む | 読みます | お読みになる | 拝読する |
| 【尊】パンフレットをお読みになってお待ちください 【謙】すぐに拝読しました | |||
| 伝える | 伝えます | お伝えになる | 申し伝える |
| 【尊】社長にお伝えください 【謙】担当に申し伝えておきます | |||
| 与える | あげます | お与えになる くださる3 | 差し上げる |
| 【尊】私にお与えになりました 【謙】差し上げますで、ぜひお試しください | |||
| わかる | わかります | ご理解いただく おわかりになる | かしこまる 承知する |
| 【尊】ご理解いただけますようお願い申し上げます 【謙】承知しました | |||
| 待つ | 待ちます | お待ちくださる お待ちになる | お待ちする |
| 【尊】今しばらくお待ちください 【謙】ご返信をお待ちしております | |||
1 本来『言う』の謙譲語『申し上げる』は【自分より上の立場の人に申す】の意味で使われる。しかし、現在は【対象となる言葉自体を敬う】表現として用いられる。ー例)謹んでお悔やみ申し上げます
2 『会う』の謙譲語『見(まみ)える』は本来【お目にかかる】の意味であるが、実際には【相手と対面する】の意で使われる。ー例)敵陣にて相(あい)見(まみ)える
3 『~くださる』は、相手を立てる一般的な尊敬語の働きとは別に『与える』の謙譲語として【相手から恩恵が与えられる】の意を持つ。ー例)今日は現役の官庁職員が指導してくださる
日頃の答え合わせはできましたか?
ちなみに『伺う』は『行く』と『聞く』の謙譲語でしたね。
『行く』と『来る』の謙譲語『参る』や『知る』と『わかる』の謙譲語『承知する』でも同様に、1つの言葉が複数の謙譲語を補っています。
読みが同じな名詞で、例えば『あめ』が『雨』や『飴』のように別の名詞になるというケースはよくありますが、
1つの動詞が全く異なる動作の意味も持つというのは面白い使い方です。

意味は異なるのに同じ語句を使う手法は、日本語の難しさのひとつでもあります。
まとめ:敬語を使い分けてスマートな大人表現を身につけよう!

今回は、よく使う敬語の種類とその違いや使い方について学びました。
日頃から意識して使い分ければスマートな大人だと認識されるでしょう。
ですが、つい丁寧に丁寧にと思いすぎるあまり二重敬語や尊敬語と謙譲語がちぐはぐになってしまったりと間違えやすいのも事実なので注意してください。
また、最近では匿名だからとネット上で他を攻撃する人が増えていて、日々流れてくるニュースを見るたびに心が痛みます…。
“たったの一言”で相手が喜んだり楽しんだり不快に思ったりするのは、その言葉自体が意味を持ち発信者の感情を携えて相手に届いているからです。
敬語は古き良き時代より受け継がれてきた言葉たちであり、“相手を敬う”という先人の心持ちがこもった言語です。
こんな時代だからこそ、敬語をひとつの手段として相手を敬う気持ちを忘れずにいてください。
そして、他でもない“私たちが”敬語を正しく常習して、人と人との関わり方を後世に伝えていきましょう。


敬語に関するよくある質問

敬語の基礎は覚えられても、実際は悩んでしまうシーンもあるかと思います。
最後に敬語に関するよくある質問を4つご紹介しますので、実践の予習としてチェックしてみてください。
よくある質問①敬語を言い間違えて恥ずかしい思いをするときがあります。間違えないようにするにはどうしたらいいですか?
よく間違えてしまう場合は、まずは一目でわかりやすい【敬語の一覧表】で勉強すると良いでしょう。
メールやチャットなど書き言葉で残っているものがあれば、何が正しく使えていて何が間違っていたのかを見返すのもおすすめです。
敬語は3種類の使い分けが必要ですが、とっさに出た言葉が間違ってしまうことはしばしば起こります。
- 尊敬語:主語は相手(聞き手や話の対象者)、相手を敬い立てる言葉遣い
- 謙譲語:主語は自分で、自らをへりくだらせる言葉遣い
- 丁寧語:主語は問わない丁寧な言葉遣い
そのため、一度使い分けの基礎から復習してみるのも良いかもしれません!
※個人的には、文化庁が公表している「敬語おもしろ相談室」は丁寧な見せ方でありつつもシュールな内容で敬語を学べるのでオススメです笑
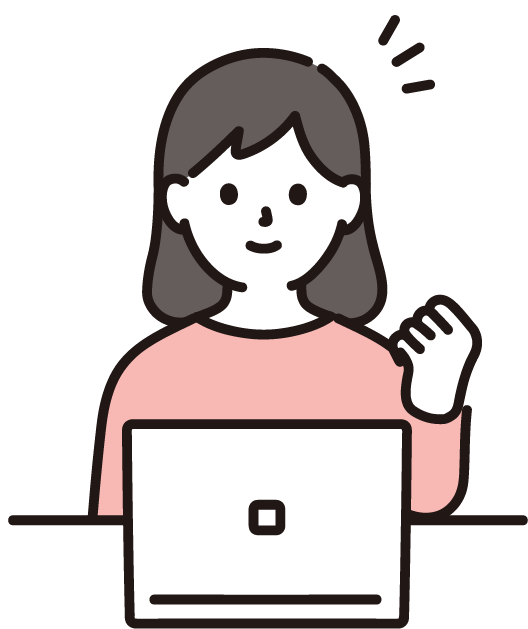
よくある質問②「~していただきます」の言い方は、相手に失礼でしょうか
「~していただきます」は、相手に何かを頼んだり指示出しをするときに使われる表現です。
そのため、相手から「きつい言い方をするな」「上からものを言う人だな」と思われる傾向があります。
対策としては、相手に決定権をゆだねる言い方に換えてニュアンスを和らげると良いでしょう。
例えば、もし同僚や目上の人や目上の人を含めた複数人に向けて
「この仕事をしていただきます」「明日の会議に参加していただきます」
などと発言した場合『私からあなたに指示出ししている』とマイナスなイメージを植つける可能性があります。
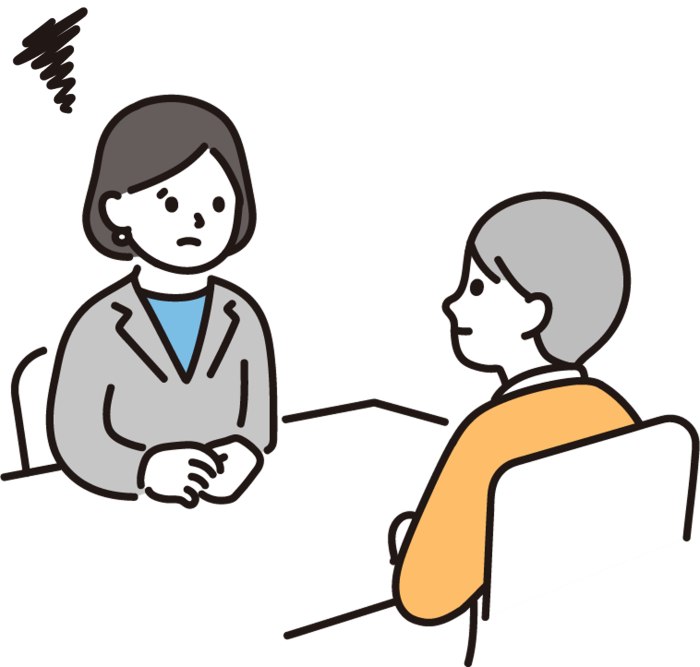
対する相手によっては
「この仕事をお願いできませんか」「明日の会議には参加でお願いいたします」
のような表現に変えてみてください。

ニュアンスを『私からあなたへ』よりも『あなたから私へ』にするだけで、相手が受け取る印象が大幅に変わります。
よくある質問③自社の上司のことを外部に伝えるときの言い回しが合っているのかいつも不安です
自分の上司か部下かに限らず、外部に社内(身内)の人のことを話すときは【謙譲語】を用います。
聞き手が顧客や取引先などであれば、“主語が社内の人”になるときは尊敬語は使わないのが鉄則です。
| ✕ 部長は席を外していらっしゃいますので、後ほど折り返すよう申し伝えます。 →間違えている点は『主語:部長』に対して『いる』の尊敬語『いらっしゃる』を使っている点 |
| 〇 部長は席を外しておりますので、後ほど折り返すよう申し伝えます。 →『主語:部長』に対して『いる』の謙譲語『おる』と 『伝える』の謙譲語『申し伝える』を使っているので正しい |

敬語の難易度を上げている原因の1つに、“身内のことを外部の人に伝える言い方が難しい”ことが挙げられます。
特に、ビジネスシーンでは誤った言い回しで相手を落胆させたくはないですよね。
よくある質問④「マニュアル敬語」の資料どおりに接客するのが苦痛です。マニュアルばかりにこだわる必要があるのでしょうか?
マニュアル敬語とは、新入社員や臨時の人員に向けて作成された【敬語の使い方をつづったマニュアル】のことですね。
会社の方針であれば、まずはマニュアルどおりの接客がよいと考えます。
(正直、筆者もマニュアルどおりの対応には違和感を覚えますが…笑)
というのも、マニュアル敬語があれば、接客に慣れない入社したばかりの人でも均一性のある接客が可能となり、敬語の基礎も学ぶことができるからです。
ただ、接客業は生身の人間同士が会話をするのですから、あまりにマニュアルどおりすぎても敬語の在り方“相手を敬う気持ち”が表れません。
マニュアル敬語は、言わば機械的に用意された言葉集ですので「自己表現ができないAIロボットのようだ!」との論争が度々起こっているのも事実です。
初めは気が滅入るかもしれませんが、ある程度慣れてくれば
マニュアルを意識せずとも自然な敬語、つまり“気持ちのこもった敬語”で接客ができるようになるでしょう。