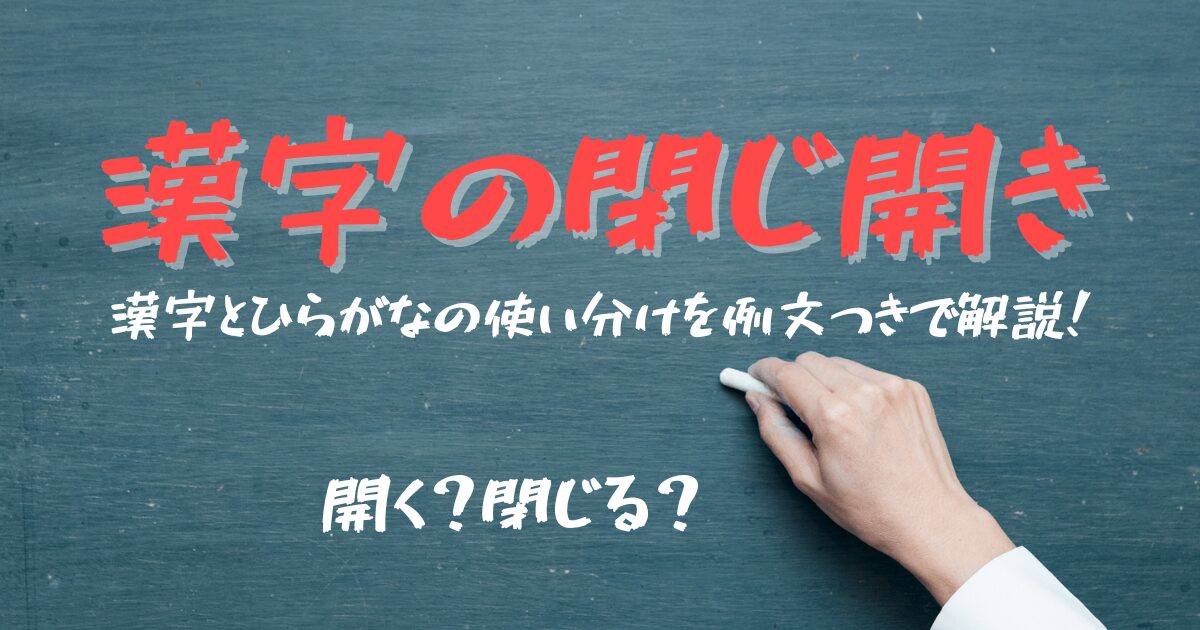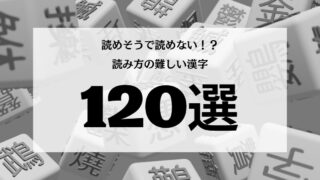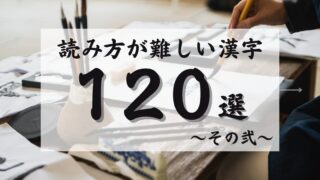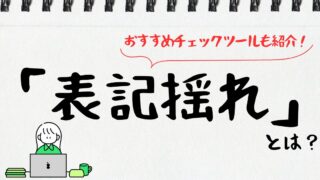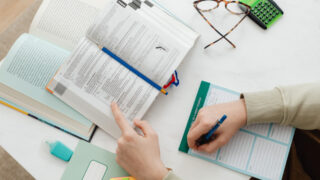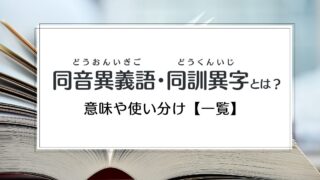漢字の閉じ開きという言葉をご存じでしょうか。
漢字をひらがなにしたり、ひらがなを漢字にしたりすることを指すのですが、読みやすい文章作成においてとても大切なものなのです。
少し思い浮かべてみてほしいのですが、漢字ばかり、あるいはひらがなばかりの文章は読みづらいですよね。
一般的に読みやすい文章の比率は【ひらがな7:漢字3】であると言われています。
この比率で文章を書くために、漢字の閉じ開きが非常に重要になってくるのです。
そこで当記事では、漢字の閉じ開きについて解説していきます。
最後までお読みいただくと、
- 漢字とひらがなの使い分け方
- 漢字の閉じ開きにおける注意点
といったことを知ることができますので、ぜひ最後までご覧ください。

漢字の“閉じ開き”って?

先述のとおり、漢字をひらがなにしたり、ひらがなを漢字にしたりすることを総称して漢字の“閉じ開き”と言います。
これはライターや編集者など、文章に関わる仕事をするうえでの専門用語です。
実は、漢字とひらがなのどちらを使用するかについて、絶対に守らなければならない決まりというものはありません。
ですが、文章を読みやすくしてくれるある程度のルールというものは存在しています。
文章に関わる仕事をする方にとっては必要な知識となりますので、必ず覚えておきましょう。
それでは、それぞれを詳しく見ていきます。
漢字を閉じるとは、ひらがな表記の言葉を漢字で表現することです。
反対に、漢字を開くとは、漢字表記の言葉をひらがなで表現することを指します。
- 私は、大学で経済を学んでいます。(閉じる)
- わたしは、大学で経済を学んでいます。(開く)
漢字を開くことによって、文章が柔らかい印象になりますね。
このように、漢字を閉じたり開いたりすることによって文章の雰囲気が変わり、ひいてはそれが読みやすさにも影響してくるのです。
開く?閉じる?品詞による判断

漢字の閉じ開きが文章を読みやすくするために重要であることは、お分かりいただけたのではないでしょうか。
ここからは、実際にどの漢字を開いてどの漢字を閉じれば良いのか、その判断方法について解説していきます。
以下にそれぞれの品詞について、閉じるべきか開くべきかの判断と例文を示しています。
副詞
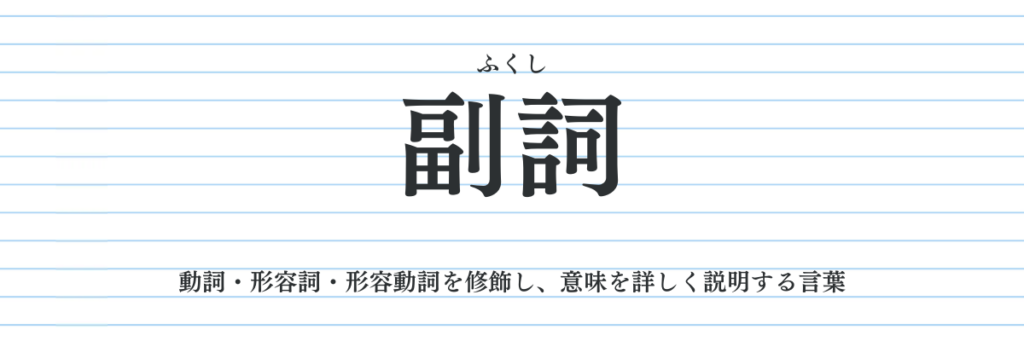
副詞は、動詞・形容詞・形容動詞を修飾し、意味を詳しく説明する言葉です。
副詞は主に、開いて(ひらがなで)書きます。
| 副詞 | 閉じた場合 | 開いた場合 |
| 殆ど(ほとんど) | ・勉強する時間が殆どない ・殆ど使わない言葉 | ・勉強する時間がほとんどない ・ほとんど使わない言葉 |
| 既に(すでに) | ・既に今月の目標を達成した ・彼は既に日本に帰った | ・すでに今月の目標を達成した ・彼はすでに日本に帰った |
副詞の中でも「例えば」や「特に」などは、閉じて(漢字で)表記する場合が多いです。
文章全体のバランスを見て、使い分けてくださいね。
接続詞
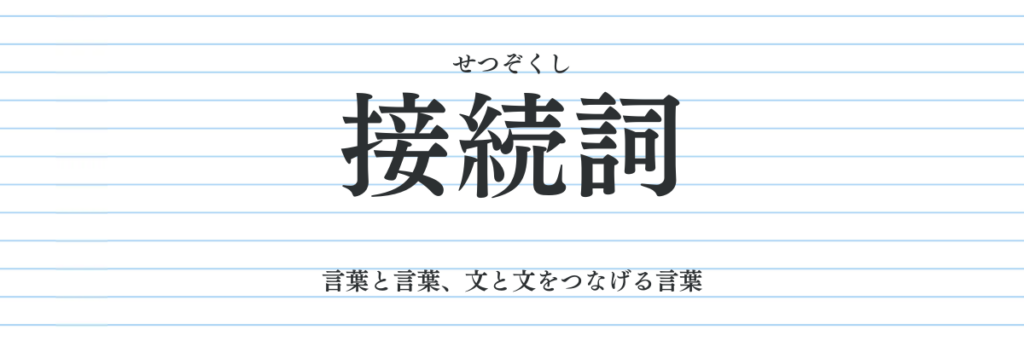
接続詞は、言葉と言葉、文と文をつなげる言葉です。
接続詞に関する詳しい解説は、こちらの記事をご確認ください。
接続詞は主に、開いて(ひらがなで)書きます。
| 副詞 | 閉じた場合 | 開いた場合 |
| 従って(したがって) | ・従って、AとBは同じである ・従って、一旦保留にします | ・したがって、AとBは同じである ・したがって、一旦保留にします |
| 又は(または) | ・交通手段は、電車又はバス ・支払いは、現金又はクレジットカードのみ | ・交通手段は、電車またはバス ・支払いは、現金またはクレジットカードのみ |
形容詞
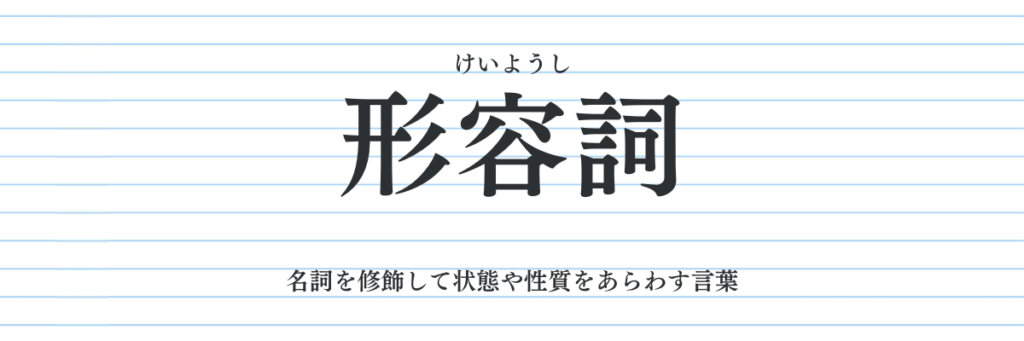
形容詞は、名詞を修飾して状態や性質をあらわす言葉です。
形容詞は主に、開いて(ひらがなで)書きます。
| 副詞 | 閉じた場合 | 開いた場合 |
| 面白い(おもしろい) | ・この映画はとても面白い ・面白い作品に出会った | ・この映画はとてもおもしろい ・おもしろい作品に出会った |
| 可愛い(かわいい) | ・可愛い猫を飼っている ・可愛い雑貨に目がない | ・かわいい猫を飼っている ・かわいい雑貨に目がない |
動詞と補助動詞
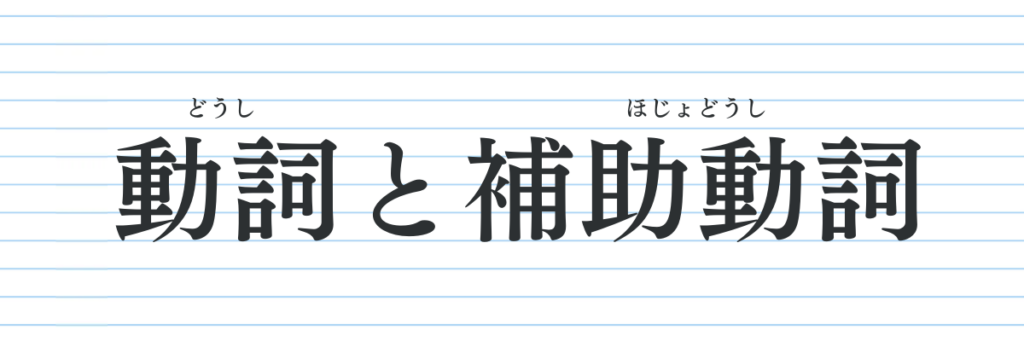
動詞は、動作・状態・作用・存在などをあらわす言葉です。
動詞は主に、閉じて(漢字で)書きます。
補助動詞は、動詞本来の意味を失い、前の言葉に意味を添える言葉です。
補助動詞は主に、開いて(ひらがなで)書きます。
| 動詞 | 補助動詞 |
| 行く(例:会社に行く) | いく(例:目標を超えていく) |
| 見る(例:説明書を見る) | みる(例:行動してみる) |
| 言う(例:お礼を言う) | いう(例:Aという場所) |
| 上げる(例:椅子を持ち上げる) | あげる(例:課題を見てあげる) |
| 下さい(例:資料を下さい) | ください(例:ご自愛ください) |
| 頂く(例:お土産を頂く) | いただく(例:資料を見ていただく) |
| 貰う(例:景品を貰う) | もらう(例:試してもらう) |
形式名詞と実質名詞
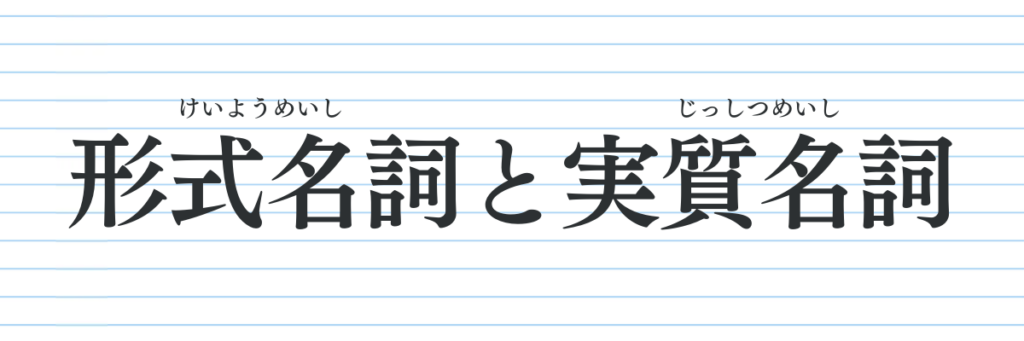
形式名詞は、具体的な意味を持たず形式的に使われる名詞のことです。
形式名詞は主に、開いて(ひらがなで)書きます。
実質名詞は、具体的な意味や内容を持つ名詞のことです。
実質名詞は主に、閉じて(漢字で)書きます。
| 形式名詞 | 実質名詞 |
| こと(例:書くことを仕事にする) | 事(例:事の始まり) |
| もの(例:比べものにならない) | 物(例:贈り物を選ぶ) |
| とおり(例:言われたとおりにやる) | 通り(例:あの通りにある店) |
| ところ(例:望むところだ) | 所(例:静かな所) |
| とき(例:困ったときの連絡先) | 時(例:時の流れは早い) |
漢字を開いたほうが良い3つのパターン
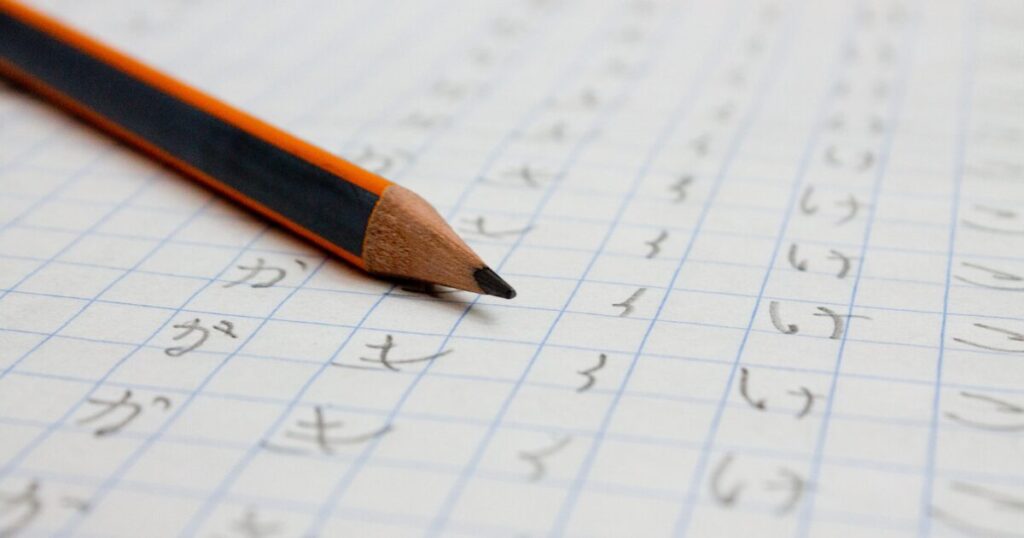
ここまで、品詞による漢字の閉じ開きの判断について説明してきました。
ここからは、2つ目の判断方法として漢字を開いた方が良い3つのパターンをご紹介します。
誤読や語解釈を防ぐ役割も果たしますので、ぜひ積極的に意識していってほしい考え方です。
【パターン1】難しい漢字
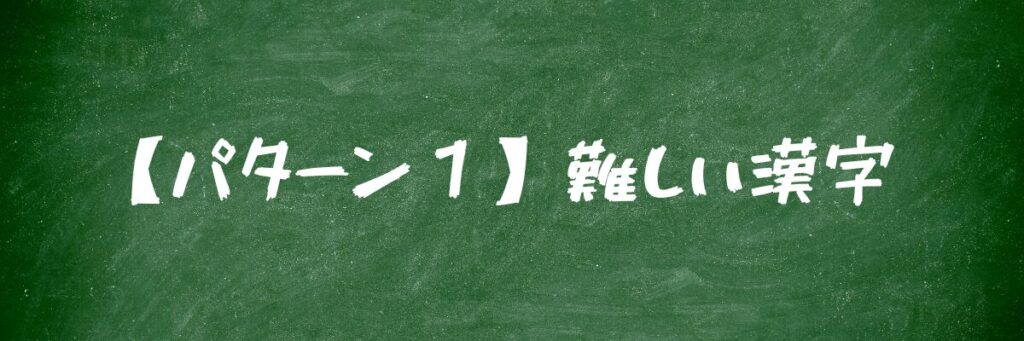
難しい漢字・馴染みが薄い漢字は開いて書きましょう。
読めない漢字は読者にストレスを与えてしまい、結果としてそれ以上読み進めてもらえない可能性があるからです。
- 纏う⇒まとう
- 捌く⇒さばく
- 稀に⇒まれに
- 所謂⇒いわゆる
- 畏まりました⇒かしこまりました
【パターン2】一部の当て字
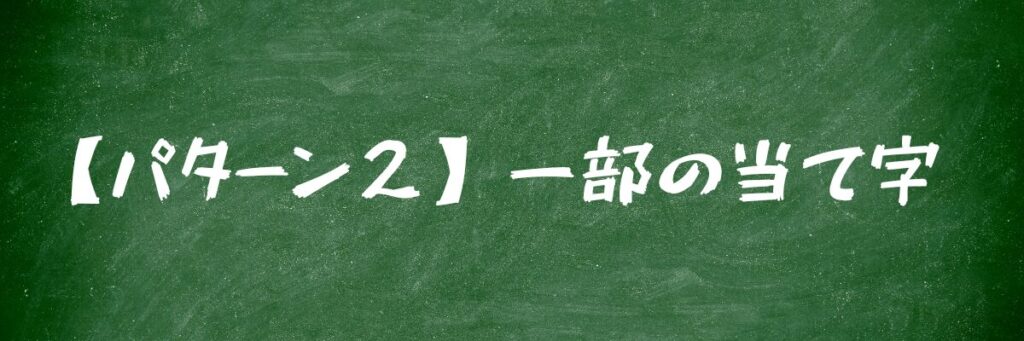
当て字とは、漢字本来の意味とは関係なく、音や訓を借りてあてはめた漢字のことを言います。
一部の当て字は開いて書くことが望ましいです。
- 上手い⇒うまい
- 流行り⇒はやり
- 流石⇒さすが
- 容易い⇒たやすい
- 相応しい⇒ふさわしい
- 目出度い⇒めでたい
- 躊躇う⇒ためらう
【パターン3】読み方が複数ある漢字
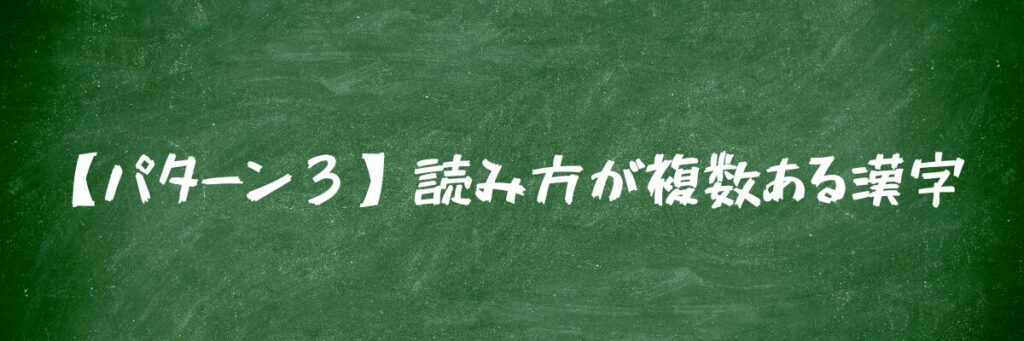
読み方が複数ある漢字も誤読を防ぐために開いて書きましょう。
読者が読み方に迷ってしまい、足止めされてしまうことを防ぐためです。
- 潜る⇒くぐる、もぐる
- 擦る⇒こする、する
- 歪む⇒ひずむ、ゆがむ
- 空く⇒すく、あく
- 居る⇒いる、おる
- 被る⇒かぶる、こうむる
- 未だ⇒まだ、いまだ
漢字とひらがなを使い分ける際の注意点
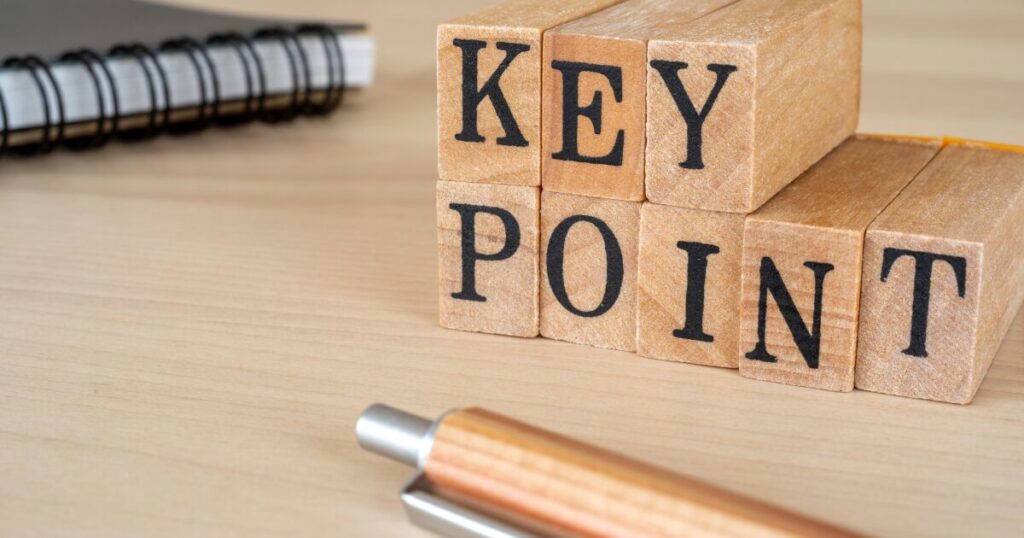
以上が、漢字の閉じ開きに関する一般的なルールとなります。
これらを意識して文章を作成すると、漢字とひらがなのバランスがとれた読みやすい文章に仕上げることができるでしょう。
しかし、ときには使用してはいけない場面や気を付けて使用しなければならない場面がでてきます。
ここからは、漢字の閉じ開きを使い分ける際の注意点についてお伝えしていきます。
表記揺れに気をつける

ルールに従って漢字を閉じ開きしていても「さっきはどのように書いただろう」と混乱してしまうこともあるかもしれません。
そのような場合でも、表記揺れは厳禁です。
表記揺れとは、文章の中で同じ言葉を異なる表記で記入すること。
例)午前9時、午前九時
表記揺れは読者にストレスを与え、離脱させる原因となってしまいます。
表記揺れには十分注意しましょう。
もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
クライアントの指示に従う

ここまでの説明どおり、漢字の閉じ開きにはある程度ルールが存在します。
しかし、ライターなどがクライアントから仕事を受注して文章を書く場合には、そのルールで書いてはいけない場合があるのです。
それは、クライアントからの指示がある場合です。
クライアント側がマニュアルやレギュレーションを用意していて、漢字の閉じ開きの指示があるのならば、
その決まりに沿って文章を執筆することがなによりも重要となってきます。
ですので、クライアントから指示がある場合には、必ずその指示に従いましょう。
「引用」した箇所は表記が混在していても修正しない
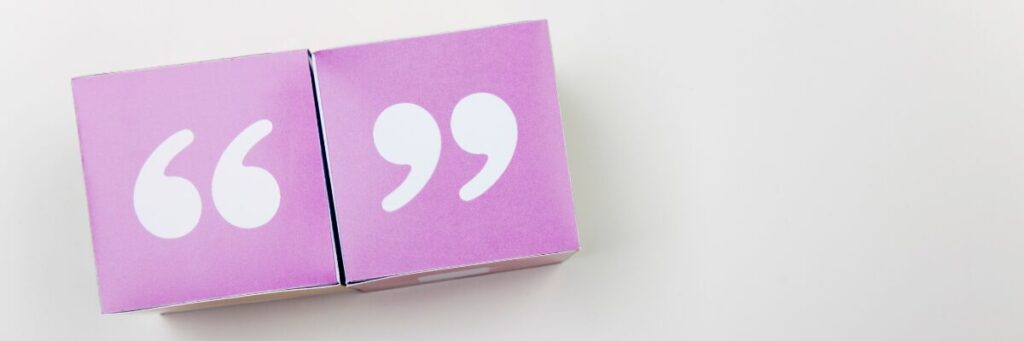
先ほど、表記揺れには十分注意しましょうと説明をしました。
しかし、引用する場合にはその限りではありません。
引用とは、他者が制作した著作物の一部分を自分の文章の中にそのまま用いることを指します。
引用をする際には、守らなければならないルールがいくつか存在します。
そのひとつが『引用した文章を書き換えない』というもの。
したがって、たとえ引用元の著作物に表記揺れがあったとしても、それを書き換えてはいけません。
引用についての詳しい解説は以下の記事をご確認ください。
まとめ:漢字とひらがなを適切に使い分けて読みやすい文章を作ろう
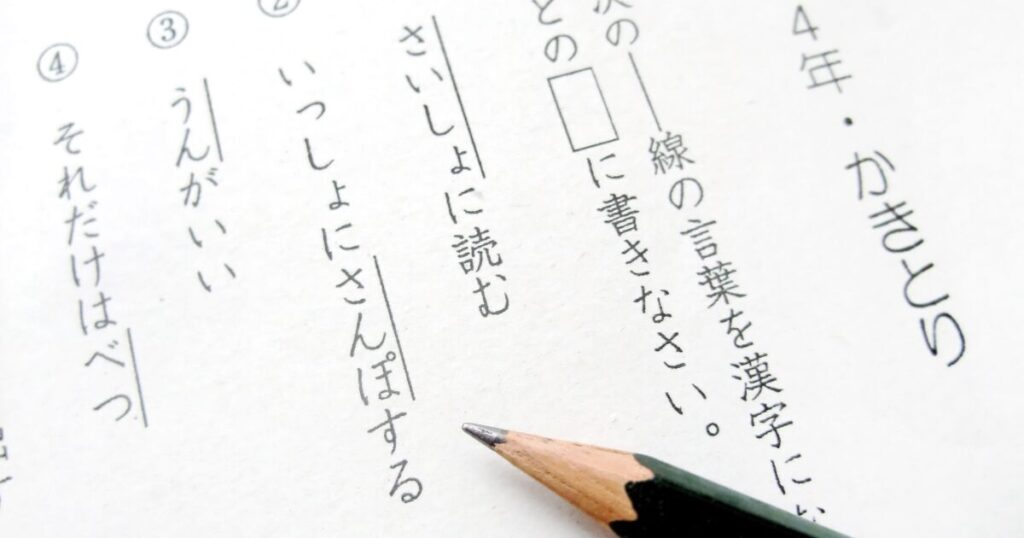
いかがでしたでしょうか?
漢字の閉じ開き、と一言で言っても様々なルールがあり、少し混乱してしまうかもしれませんね。
ですが、漢字の閉じ開きをきちんと意識して文章作成をすることで、バランスのとれた文章になったり誤読や誤解釈を防げたります。
また、読者のストレスを減らし離脱する確率を下げられる効果も期待でき、そのメリットは無視できないものがあります。
ぜひ、上記のルールを参考に読者が読み進めてしまう文章を目指してくださいね。

「漢字 閉じ開き」に関するよくある質問

いざルールに従って漢字の閉じ開きをやってみると、意外と難しく感じることがあるかと思います。
そこで、漢字の閉じ開きを行う際に役立ちそうな情報を、よくある質問としてまとめました。
上記のルールと併せて活用し、読みやすい文章の作成にお役立てください。
よくある質問①ビジネスメールでは漢字を開きますか?
ビジネスメールでは、送る相手によって対応を変えるのがオススメです。
例えば、目上の方や年配の方に送るメールであれば、かっちりとした印象を持たせたいので漢字は閉じたほうが良いでしょう。
一方、よく連絡を取るような関係の方に漢字が多めのかしこまったメールを送ると、他人行儀な印象を与えてしまいます。
ですので、そのような場合には漢字を開いて柔らかい印象の文章にするほうが望ましいでしょう。
このように、送る相手によってメールの印象を変えることが、円滑なコミュニケーションに繋がります。
よくある質問②漢字の閉じ開きに迷ったときに参考にできる書籍はありますか?
言葉の表記方法について迷ったときには『記者ハンドブック』を確認するのが良いでしょう。
記者ハンドブックとは、言葉の表記方法についてまとめられた書籍です。
漢字とひらがなの使い分け方や送り仮名の付け方など、言葉の表記に関するあらゆる情報が記載されています。
タイトルに「記者」とついていますが、ライターなど文章を書くすべての人に役立つ内容となっています。
文章作成の強い味方になってくれることでしょう。
よくある質問③漢字の閉じ開きが正しくできているかチェックする方法はありますか?
漢字の閉じ開きをチェックする方法として『文章校正ツール』が使えます。
文章構成ツールとは、入力ミスや表記揺れなどを指摘してくれるツールのこと。
有名なものとしては「文賢(ぶんけん)」が挙げられます。
正確にチェックしたいということであれば、このようなツールの使用を検討してみても良いかもしれません。
よくある質問④漢字を使用したほうが良いのはどんなときですか?
同音異義語の場合は、あえて漢字を使うほうが意図が伝わりやすい場合があります。
例えば、以下のようなものがあります。
- よむ⇒読む、詠む
- うたう⇒歌う、謳う
- あてる⇒当てる、充てる
- きく⇒聞く、聴く
- ならう⇒習う、倣う
しかし、こちらも状況によって使い分けることが前提ですので、文章の雰囲気などにあわせて適宜調節してくださいね。
よくある質問⑤ルールに沿わない漢字の閉じ開きをすることはありますか?
文章にどんな雰囲気を持たせたいかによって、漢字を閉じたり開いたりするのもひとつの方法です。
例えば、
- 医療系や金融系の記事など、少し堅い文章で誠実さをアピールしたい場面では、漢字は閉じたままにする
- エンタメ系やライフスタイル系の記事など、ラフな印象のほうが良い場面では、ルールに沿って漢字を開いてみる
といった使い分け方ができます。
あるいは、想定される読者ターゲットに合わせて漢字を閉じ開きする、というのも有効でしょう。
漢字の閉じ開きのルールは、あくまで一般的にそのようにされていることが多い、というだけで絶対ではありません。
どんな人にどんな文章を届けたいか、文章作成ではそのような心構えも大切です。
よくある質問⑥漢字の閉じ開きのメリット・デメリットは何ですか?
漢字の閉じ開きの考えられるメリット・デメリットとしては、以下のようなものがあります。
【開いた場合】
| メリット | デメリット |
| 読みやすくなる親近感を与えられる | 場合によっては読みにくくなる幼い印象を与える可能性がある |
【閉じた場合】
| メリット | デメリット |
| 読みやすくなるビジネスの場にふさわしい文章になる | 堅い印象を与えやすいページ全体が詰まって見えてしまう |
漢字の閉じ開きについての説明は以上となります。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。