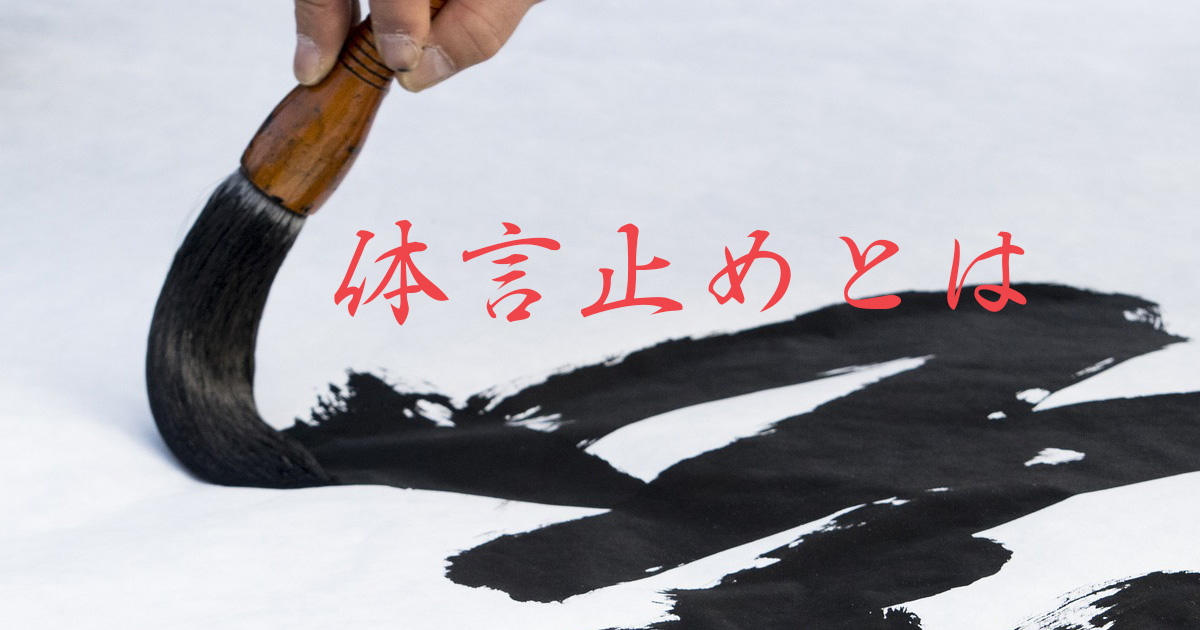『体言止め』とは、”文の最後に名詞を置くだけ”の極めてシンプルな手法です。
この体言止めを使うことにより、
・読む人をひきつける
・簡潔にまとめる
・文章に力強さを与える
など色々な効果をもたらします。
それは当然、小説、雑誌、書籍のタイトル、キャッチコピー、広告文やブログ…
いかなるシーンにおいても活用でき、もはやライティングに欠かせない手法といえるでしょう!
ただし、使うシーンを誤るとトラブルを招く恐れがあるので要注意!
そこで今回は『体言止め』とはなにか?を詳しくお伝えするとともに、効果を活かした使い方や注意点を詳しく解説します!
特に読む人をひきつける文章を書きたいライターには必須級のスキルです。
本記事の要点をしっかり押さえて魅力的な文章を作成しましょう!

体言止めとは?
体言止めは、簡単に言うと”文の最後に体言を置く”ライティング手法です。
なおこの体現とは、名詞を意味します。
名詞と聞くと”人や物の名称”をイメージすると思いますが、それだけではありません。
まずは『体言止め』のポイントである『名詞』の特徴をつかみましょう。
名詞の特徴と見分け方
『人物や物の名称』のイメージが強い名詞ですが、実は名称の他にも種類があります。
| 名詞の種類 | |
|---|---|
| 普通名詞 | 一般的な物、事、人物をあらわす語 (例:鉛筆、テーブル、バスケットボール、職員、気象予報士) |
| 固有名詞 | 唯一無二の物につけられた特有の名称 (例:人名、地名、国名、会社名、商品名、ブランド名) |
| 代名詞 | 主に人や物、事をあらわす語 (例:彼、私たち、君、これ、ここ、そこ、こちら) |
| 数詞 | 数、時間、量、順番等をあらわす語 (例:4つ、8番、7枚、9メートル、第2位) |
上記の他、動詞に似た名詞もあります。
名詞の特徴は、主語になれて、単独で意味が通じる語であること。また、語尾は変化しません。
例えば『走る』『走らない』は語尾が変わるため名詞ではありません。
また『迷い』や『動き』は動詞に見えるかもしれませんが、「~が」または「~は」をつけて主語になれる語は名詞として扱います。
迷いがない (迷いー名詞)
どちらの服を着ていくか迷う (迷うー動詞)
動きが鋭い (動きー名詞)
素早く動く (動くー動詞)
名詞かどうか迷った際は、特徴に当てはめて見分けましょう。
体言止めは特有のスタイルを持つ
それでは、体言止めについて詳しく解説します。
体言止めは”名詞を最後に置く”手法です。
文を書く際は『です』『ます』『~だ』等で終える場合が多いですよね。
しかし体言止めの場合は、これらの語を置きません。
「あまりピンとこない……」という方も、次の例文を見ればわかると思うのでご安心下さい!
私のイチオシはいちごのショートケーキです。
⬇
私のイチオシはいちごのショートケーキ。
これが今年最も売れたテレビだ。
⬇
これが今年最も売れたテレビ。
ピアノコンクールの結果は第2位でした。
⬇
ピアノコンクールの結果は第2位。
上記の文は文末を言い換えて名詞で終えているため、『です』『ます』等の語尾は使っていません。
実はこの特有のスタイルこそ、色々な効果をもたらすカギなのです。
効果や使い方を知る前に、体言止めの要点を改めてチェックしておきましょう。
≪体言止め≫
- 文末に名詞を置く
- 『です』『ます』『~だ』等の語尾を置かない
体言止めがもたらす効果とは?
冒頭でもお伝えした通り、体言止めは読む人の興味をそそる、要件を簡潔に伝える、文章に力強さを与えるなど、色々な効果をもたらします。
本セクションでは、ライターとして身につけておきたい使い方や、その上で得られる効果について5つほどご紹介します。
語尾のバリエーションを増やせる
文章を書いた時「『です』『ます』で終わる文ばかりになってしまった」という経験はありませんか?
同じ語尾の連続は、読む人に違和感を与え退屈させてしまいますが、体言止めを使うことで、語尾のバリエーションが増えるため文章全体が読みやすくなります。
≪例:同じ語尾の連続の場合≫
昨日は久々の休日でした。
ショッピングモールに行き、買い物の後に映画を鑑賞しました。
帰りにカフェで休憩してリフレッシュできました。
同じ語尾の連続は単調で退屈になり、子供っぽい印象も与えます。
語尾の連続を避けるため、一部を修正します。
≪例:体言止めを用いた場合≫
昨日は久々の休日でした。
ショッピングモールに行き、買い物の後は映画鑑賞。
帰りにカフェで休憩してリフレッシュできました。
このように体言止めを使うことで、語尾の表現が広げられます。
「気づいたら同じ語尾ばかり書いていた……」ということは、多くのライターがぶつかる問題点。
文章を作成したら、バランスよく語尾が散っているか確認するクセをつけておくといいですね。
文章に説得力を持たせられる
何かを強く訴えたい場合にも、体言止めが有効です。
特定のワードを強調したり、説得力を持たせることができるのです。
例文で印象を比べてみましょう。
お肌のトラブルは食生活で改善できる⁉
⬇
お肌のトラブルは食生活で改善⁉
料理が好きになったきっかけはこの本です。
⬇
料理が好きになったきっかけはこの本!
強調したいワードを文末に置くと、そのワードが読む人の印象に残りやすくなります。
その結果、説得力を増したり、強く訴えたりできるのです。
この表現方法は広告やチラシ、ネット通販の商品販売ページや商品パッケージ等、多くのシーンで取り入れられています。
私は商品のキャッチコピーを作る時に、この表現方法をよく使っています。
購入者に最もアピールしたいワードを文末に置いて強く訴えるイメージです。
さらに、書籍やブログ等のタイトルや見出しの作成にこの表現方法を使えば、読む人の興味をそそることにも役立ちます。
無駄な文字をカットして簡潔にまとめられる
SNS等に投稿する時に「文字数に制限があって困った」という経験はありませんか?
体言止めを使うと余計な文字数をカットでき、簡潔にまとめられます。
簡潔にまとめられた文は、内容も伝わりやすくなるので一石二鳥ですね!
さっそく例を見てみましょう。
クマの出没にご注意下さい(12文字)
⬇
クマの出没に注意(8文字)
”ご注意下さい”を”注意”に置きかえて4文字カットできました。
また、体言止めは”文末に置いたワードが強調される”とご説明しましたが、文末の”注意”を強く訴えた文になりました。
余分な文字をカットするポイントは、文の一部を名詞で置き換えること。
文字数で悩んだら、体言止めで変換できないか試してみて下さい。
余韻を残して想像や興味をかきたてる
体言止めは、風景や情景等を伝える際も有効です。
文章に余韻を残し、読む人の想像を膨らませたり、興味をかきたてたりできるのです。
「どうして体言止めで余韻が残せるか?」というと、体言止めは『です』『~だ』といった語尾がなく、言い切りを避けた文だから。
つまり”言い切らない”ことで曖昧さや余韻を残せるのです。
例文で確認しましょう。
目の前に広がるのは、真っ白な砂浜とエメラルドの海。
和歌や詩、小説等でよく使われるスタイルです。
『エメラルドの海』を文末に置いて余韻を残し、読む人が海岸の情景を想像しやすくしています。
体言止めを使用せずに書くと……
目の前に広がるのは、真っ白な砂浜とエメラルドの海です。
先ほどと比べて味気なく感じますね。
読む人に心情や風景を想像させたい時や、興味をそそりたい場合は、体言止めを取り入れましょう。
文章に抑揚やリズムを付けられる
【語尾のバリエーションを増やせる】のセクションでご説明した通り、同じ語尾が続く文章は、読む人を退屈させます。
体言止めを適度に入れるとリズムや抑揚が付き、読む人が飽きずに読めるのです。
こちらも具体例で比べてみましょう。
≪例:体言止めを用いない場合≫
夏休みに、ダイビングツアーに行きました。
場所は大物生物に出会うチャンスがある、メキシコのラパスです。
インストラクターと一緒に海に潜り、大物の出没スポットを目指しました。
目の前を通り過ぎるカラフルな熱帯魚やウミガメに目を奪われていると、
インストラクターが興奮した様子で遠くを指差しました。
差された方を見ると、何やら大きな生き物が泳いでくるのが見えました。
「何だろう?」
とワクワクしながら生き物の姿を見つめていると……
巨大生物の正体は、なんと全長8mはあるジンベエザメでした。
語尾に『ました』が多く、事実だけを淡々と述べた印象を受けるのではないでしょうか。
ここに体言止めを取り入れて修正すると……
≪例:体言止めを用いた場合≫
夏休みに、ダイビングツアーに行きました。
場所は大物生物に出会うチャンスがあるメキシコのラパス。
インストラクターと一緒に海に潜り、大物の出没しやすいスポットに向かいました。
目の前を通り過ぎるのは、カラフルな熱帯魚やウミガメ。
その光景に目を奪われていると、インストラクターが興奮した様子で遠くを指差しました。
差された方を見ると、何やら大きな生き物が近づいてくるのが見えました。
「何だろう?」
とワクワクしながら生き物の姿を見つめていると……
巨大生物の正体は、なんと全長8mはあるジンベエザメ。
単調な文章に変化がつき、リズムが出て読みやすくなりました。
また『ウミガメ』『全長8mはあるジンベエザメ』で止めたことで、
情景をイメージする余韻も残しています。
体言止めを活用するうえでの注意点【3選】
体言止めは、使うシーンに気をつけないと効果が裏目に出る場合があります。
例えば『です』『ます』を省いた文だと失礼になる場合があったり、曖昧な表現では誤解を招くこともあるのです。
最悪の場合は信用問題や人間関係に影響するかもしれません……
「トラブルは避けたい……」という方のために、注意点を3つご紹介します。
体言止めの多用はNG
体言止めは、箇条書きのような場合は多く使っても問題ありません。
しかし、一般的な文章で使い過ぎると読みづらくなります。
例文で確認しましょう。
≪例:体言止めを多く用いた場合≫
健康維持に必要なものは十分な睡眠。
栄養バランスや適度な運動も不可欠。
規則正しい生活で元気な毎日。
体言止めが続くと、ぶつ切りに感じる方もいるでしょう。
体言止めを使い過ぎると文章の流れが悪くなり、読む人に違和感を与えるのです。
「読みにくい」と感じた時点で、続きを読んでもらえないかもしれません。
そこで体言止めを減らして修正すると……
≪例:体言止めを適度に用いる場合≫
健康維持に必要なものは十分な睡眠。
栄養バランスや適度な運動も不可欠です。
規則正しい生活で元気な毎日を送りましょう。
違和感がなくなったと思います。
体言止めを使用する際は、スパイスを効かせる感覚で適度に使いましょう。
読む人を不快にする可能性がある
例として、他社宛にメールを送る場合を取り上げます。
≪例:体言止めを用いる場合≫
【合同会議 日程変更のお知らせ】
会場都合により7月2日に変更。
資料提出期限は変更なし。
時間厳守。
他社に送るには、失礼で不親切な感じがします。
体言止めを使わず、丁寧な文章に書き換えます。
≪例:体言止めを用いない場合≫
【合同会議 日程変更のお知らせ】
会場都合により7月2日に変更させていただきます。
資料提出期限の変更はありません。
時間厳守にご協力下さい。
先ほどより柔らかい印象になりましたね。
使いどころを見極めて読む人に不快感を与えないようにしましょう。
正確な情報を伝える際は適さない
体言止めは、読む人に誤解を与える可能性があるため、正確な情報を伝える際には使用を避けるのがベストです。
原料価格の高騰。これは最大の懸念点だ。
文中の”原料価格の高騰”は『現在・未来』いつの話だと思いますか?
その答えは……「どちらも正解!」になり得ます。
理由は「今、光熱費が高騰していることへの心配」とも受け取れますし「将来、光熱費が高騰することへの心配」とも解釈できるからです。
複数の解釈ができると、誤解を招く可能性があるので要注意!
補足を加えるか、体言止めの使用を避けて正しく伝えましょう。
2つの修正例をあげます。
≪修正例1:体言止めと補足を併用≫
(現在進行形)
現在も続いている光熱費の高騰。これは最大の心配事だ。
(将来)
今後起こり得る光熱費の高騰。これは最大の心配事だ。
≪修正例2:体言止めを用いない場合≫
(現在進行形)
光熱費が高騰している。これは最大の心配事だ。
(将来)
光熱費が高騰するかもしれない。これは最大の心配事だ。
実は、ビジネスや丁寧さ、正確さが必要となるシーンでは、体言止めの使用は避けた方が無難とされているのです。
体言止めは使うシーンを考えてトラブルを防ぎましょう。

まとめ: 体言止めの特性を把握して有効に使う
今回は体言止めの色々な効果や活用方法、注意点等をお伝えしました。
体言止めはライター業務に限らず、日常生活でも役立つ便利な手法です。
「この記事を読むまで体言止めと知らずに使っていた……」という方もいるかもしれませんね。
体言止めの活用は”適したシーンで少しだけ取り入れる”のがポイント。
使いどころを誤ったり、使いすぎたりすると効果が裏目に出てしまいます。
要点を押さえて、読む人に伝わりやすく興味をひく文章を目指しましょう。
読者に寄り添った、わかりやすい文章を心がけています。