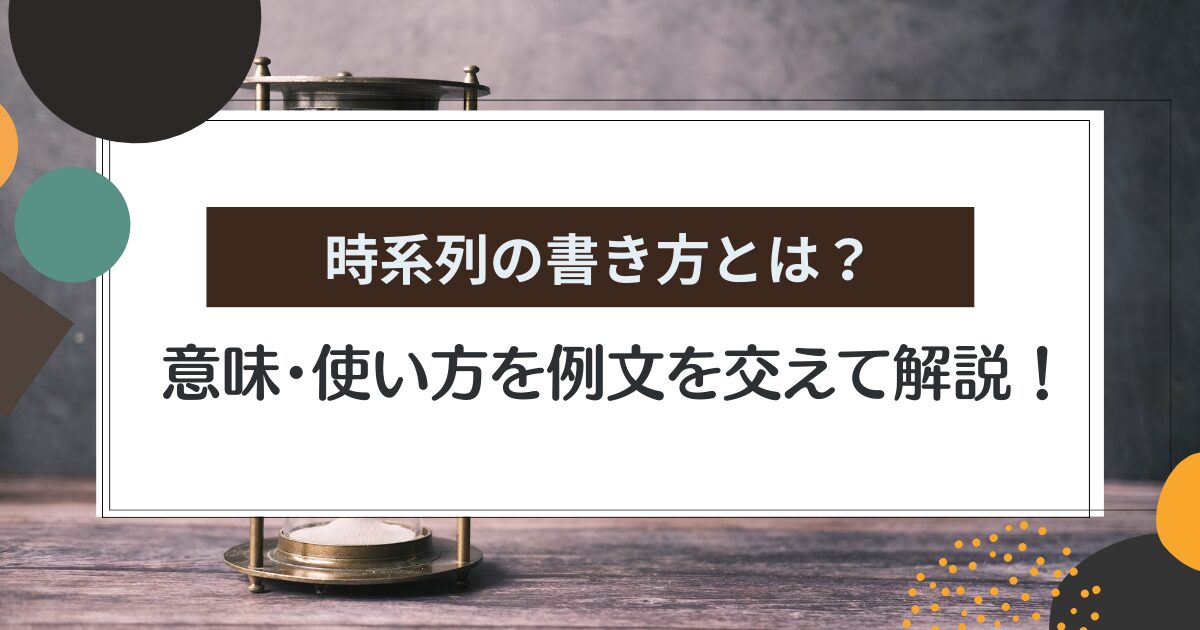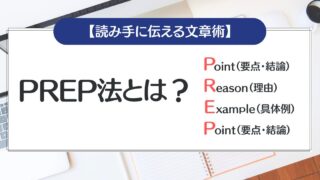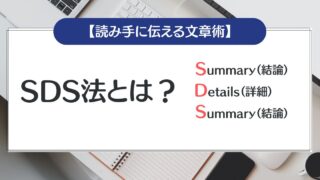なにが伝えたいのか分からないって言われる…」「書いた文章に自信がない…」
伝えたい内容が意図したとおりに理解してもらえないと、大変もどかしいですよね。
その悩みは、伝える順序を見直すことで、改善されるかもしれません。
過去から現在に向け、起きた出来事の順を追って伝えることを時系列法と呼びます。
時系列に沿って書くと文章に流れを持たせることができ、内容の整理がしやすくなります。
この記事では、時系列法の基本と使い方を例文付きで解説します。

『時系列』とは?

『時系列』とは、発生した時間の順序に従って、物事の出来事や情報を並べることです。
「いつ、なにが起こったか」という、時間の流れに沿って構成していきます。
起きた順序を意識することは、物事の因果関係を理解したり、将来の動向を予測する上で非常に重要です。
時系列法を活用したテクニックをマスターし、ライティングだけではなく報告書やシナリオなど、伝わる文章を作成していきましょう。
『時系列』で文章を書くと伝わりやすくなる?

「時系列に沿った文章は、なぜ読者にとって理解しやすいのか?」
その理由は、脳の認知プロセスと関係しています。
人間の脳は、物事を時間の流れに沿って整理し、情報を関連付ける傾向にあります。
参考:出来事の順序を記憶する仕組みの発見 | 理化学研究所
そのため、分かりやすく伝えるために時系列を意識することは、情報整理や論理的な構成の基本です。
時間の流れに沿った記述は、読みやすさと印象に残る文章作成につながります。
時系列法が有効なケース
以下の表を見ていただくと分かるとおり、シナリオや会議の議事録、報告書などの文書を時系列で構成することは、読み手にとって流れが自然で理解しやすいという大きなメリットがあります。
特にビジネス文書やプレゼン資料においては、情報が発生順に整理されることで、物事の因果関係や背景が明確になるため、説得力のある伝達が可能になります。
| 会議・打ち合わせの議事録 | 議題ごとよりも実際の会話や決定の流れを追いやすい |
| 業務報告書・進捗レポート | 作業の過程や課題発生~解決までの流れを説明しやすい |
| トラブル報告書・事故報告書 | 問題の発生点からの記録を整理しやすい |
| シナリオ・ストーリーテリング | 読者に自然なストーリー展開を提供できる |
■例1 議事録は『発言順』が最も伝わる

会議の議事録は、発言者や議題ごとに整理します。
発言順=時系列でまとめると、会議の流れや意見の変遷、意思決定の過程が明確です。
- 10:00~ 部長より挨拶
- 10:05~ 営業部より3月の売上報告
- 10:20~ マーケティング部より改善案の提案
- 10:45~ 経営陣より意思決定⁽改善案採用⁾
実際に起こった順番で記録すると、誰が・いつ・なにを言ったか・どう結論に至ったかが直感的に伝わります。
■例2 業務報告書は『日付順』で成果と課題を明確にする

業務報告やプロジェクトの進捗報告では、日ごと・週ごとに区切って記録することで、読者が流れと変化に注目しやすくなります。
- 4月1日 要件定義ミーティングを実施:課題リスト作成
- 4月3日 設計フェーズ完成:クライアントに提出
- 4月5日 レビュー完了:修正内容を確定
いつ・なにを行ったかが明確であれば、上司や関係者も状況をすぐに把握できます。
加えて、後日トラブルが発生した際の時系列トレースにも役立ちます。
■例3 報告書は『原因の発生⇒対応⇒結果』という時間軸に沿った構成が有効

トラブル報告書の読み手は「なぜそうなったのか?」を追いやすくなり、内容の納得度が上がります。
- 9:00 システム異常検知
- 9:30 エンジニアによる一次対応開始
- 10:30 原因判明、サーバーリソース逼迫
- 11:00 復旧完了
- 14:00 再発防止策を会社通達
時系列に沿った構成は、信頼性・透明性を高めるための基本的な手法として非常に有効です。
■例4 ストーリーシナリオは『過去⇒現在⇒未来』の流れに沿った展開が基本
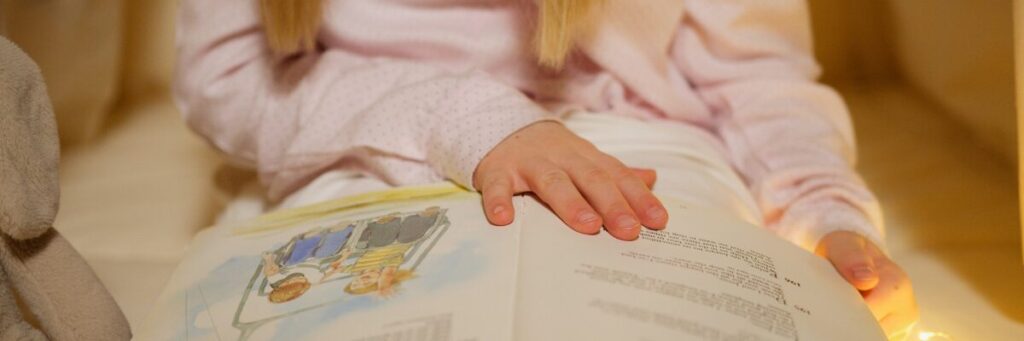
昔話や童話といった子供向けの絵本は多くの場合、時系列に沿った展開になっています。
過去に起きた出来事から順につなげられているシンプルな構成のため、幼い子供でも話の流れが理解しやすいからです。
しかし、読者を引き込む作品にするため、あえて基本を崩すことがあります。
間に回想シーンを入れたり、起きた出来事の順番を意図的に入れ替えるなど、先が読めない展開にすると最後まで読者を飽きさせません。
テクニックを駆使した応用を使いこなすには、土台が大事です。
そのため、基本通りの時間軸に沿った展開で物語を書き、誰にでも伝わりやすいストーリー作りから始めましょう。
時系列の基本的な書き方・構成
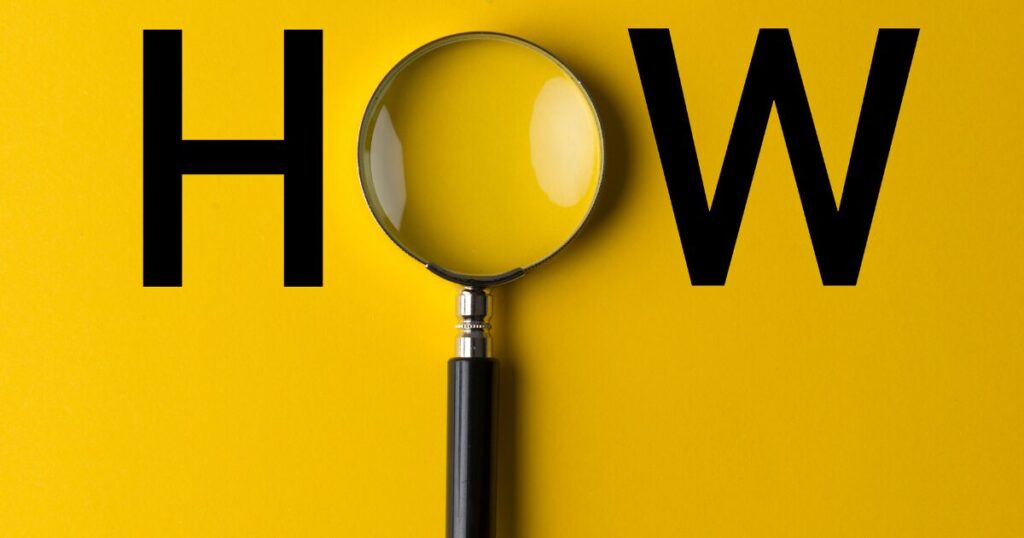
時系列で文章を構成する際、最も重要なのは、読者が流れをスムーズに追えることです。
4つのステップを意識するだけで、誰にでも伝わる、分かりやすい文章を作ることができます。
スタート地点を設定する
まず、どこから話を始めるかを明確にしましょう。
プロジェクトが始まった経緯や問題が発生した日時など、原因や発端が該当します。
スタート地点は、物語や記述の入口です。
登場人物・背景・前提条件といった初期情報を提示して、読者の理解を導く助けとなります。
例▼
| 小説 | 主人公の行動の始まりや事件の発端 |
| 歴史 | 重要な出来事の直前の社会状況 |
| 科学 | 研究を始めた動機や背景 |
文書の種類に応じて適切なスタート地点を設定することが、文章全体の一貫性と説得力に直結します。
出来事の順序を定める
次に、出来事を発生順に並べていきましょう。
日時やフェーズごとに整理することで、文章にリズムと構造が生まれます。
時系列法では、順序づけが最も重要なステップです。
物語の場合、登場人物の行動や感情の変化を時間軸に沿って描くことで、臨場感や説得力が高まります。
話の一貫性・連続性を保つ
時系列が整っていても、話のつながりがぎこちないと、読者にとって理解しづらくなります。
前後の因果関係や文脈は、接続語や補足説明で丁寧につなぎましょう。
時系列法では、話の一貫性と連続性を保つことが非常に重要です。
物語形式では、登場人物の行動や感情の変化が時間の流れと論理的に結びついていることで、リアリティと深みが生まれます。
たとえば、主人公が困難に直面し、それをどう乗り越えて変化したか。段階的に描くと、読者の共感を得やすくなります。
報告書や学術文献でも、情報が文脈に沿って連続していることで因果関係や経緯が明確になり、説得力が高まります。
- ストーリーラインを明確にする
- 論理的な順序で展開する
- 脱線や飛躍を避ける
- 接続語でつながりを補強する
これらを意識することで、読者にとって自然で分かりやすい文章になります。
ゴール地点を明確化する
最後に、どこに辿り着きたいのか・なにが結論かを示しましょう。
ゴール地点を明確化することで文章全体が締まり、読者に納得感を与えます。
時系列法では、結果や教訓、今後の展望がこの位置にくることが一般的です。
| 物語 | ・問題や対立の解決 ・主人公の成長や旅の完結 ・感情的なカタルシス⁽解放感⁾の提供 |
| 報告書・歴史文書 | ・出来事や研究結果の要約 ・調査の結論や今後の提言 |
■ゴール設定時の注意点
- テーマや目的が一致しているか
- 自然な流れで結末に向かっているか
- 読者に明確な理解や感情的満足を与えているか
ゴール地点はあくまで“読み手の印象に残すための締め”であると考えておきましょう。

時系列を活用した書き方【例文つき】
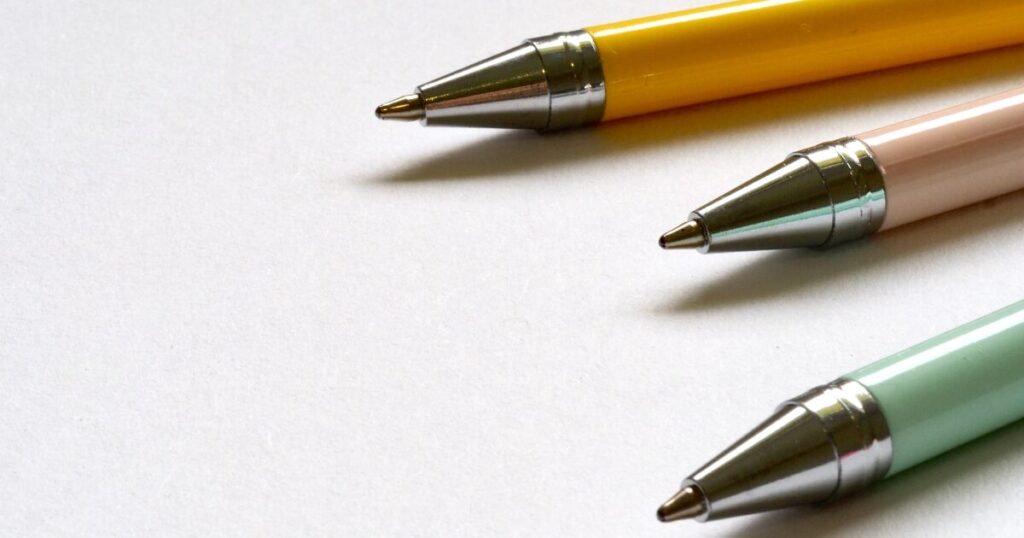
時系列法の中で最も基本的なのが、まず ⇒ 次に ⇒ 最後にという順で説明するパターンです。
時間の流れに沿って直線的に情報を並べるため、誤解を生じさせない明快な文章になります。
まず⇒次に⇒最後に(終わりに)
時系列を活用した構成の中でも、最も基本的で分かりやすいのがまず⇒次に⇒最後に⁽終わりにという順序で物事を整理して説明するパターンです。
情報を時間の流れに沿って直線的に並べていく方法は、読み手に誤解を与えず、シンプルかつ明快な文章を作ることができます。
- 手順を説明するマニュアルやレシピ
- 初心者向けのHowTo記事
- 時系列に沿った報告やレポート
3ステップ構成のイメージ
| 段階 | 内容例 |
|---|---|
| まずは | 鍋に水500㎖を沸かす |
| 次に | 麺を入れてほぐしながら3分茹でる |
| 最後に | スープの素を加えて完成 |
流れが一目で分かる構成は、読者の理解を助けます。
ただし、単調になりやすいため、以下の工夫が効果的です。
- 各段階に理由や背景・補足情報を加える
- 文末表現を工夫して変化をつける(です・ますの文末表現だけでなく体言止めなども使う)
- 「なぜそれをするのか」という意図を明確にする
1つ目は⇒2つ目は⇒3つ目は…
時系列を明確に伝えるもう1つの基本的な方法が、出来事や作業の流れに数字をつけて順番に示すパターンです。
1つ目は⇒2つ目は⇒3つ目はというように、段階ごとに数値ラベルをつけることで、読者が順を追って理解しやすくなります。
- 手順が多いプロセスの解説
- 無駄を省いて、事実だけを伝えたい場面
- プレゼン資料や業務マニュアルなど、視覚的に整理したいとき
▼例:ブログ記事作成のステップ
| 1 | テーマ選定 |
| 2 | キーワード選定 |
| 3 | 競合調査 |
| 4 | 構成案の作成 |
| 5 | 記事作成 |
番号をふることで、作業の流れが明確になり、読者が行動に移しやすくなります。
■番号構成のメリット
- 項目が多くても整理しやすく、実践向き
- 箇条書き・スライド・ビジネス文書との相性が良い
- 見た目が分かりやすく、情報がすぐ頭に入る
ただし、項目を細かく分けすぎると、逆に読みづらくなることがあります。
要点を押さえて、簡潔な表現を心がけましょう。
以前(過去)⇒現在⇒今後(未来)
物事の変化や進化を伝える際に有効なのが、以前は⇒現在は⇒今後はという時間の推移を示すパターンです。
まず過去の状況を提示し、次に現在の状況を説明、最後に未来の見通しへと話を展開します。
- 社会の変化や技術革新の流れを説明したいとき
- 商品やサービスの進化を紹介するマーケティング文章
- 過去と現在の対比に基づく未来展望型の記事や報告書
▼例:医療の進歩に関する説明
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 以前(過去) | ガン=不治の病とされ、治る見込みがなかった |
| 現在 | 治療法が確立したガンもあるほか、早期発見の技術も進化 |
| 今後(未来) | ガンも通院で処方された薬を服用すれば 治るようになると期待されている |
このように『過去⇒現在⇒未来』の流れで説明することで、読者の関心を自然と未来に向かわせ「これからはどうなるの?」という興味を引き出す効果があります。
最初に、過去という誰もが共有しやすい話題から入ることで、共感が得やすくなります。
現在との比較で進歩を実感させ、未来への期待につなげていきましょう。
時系列で文章を書く3つのメリット
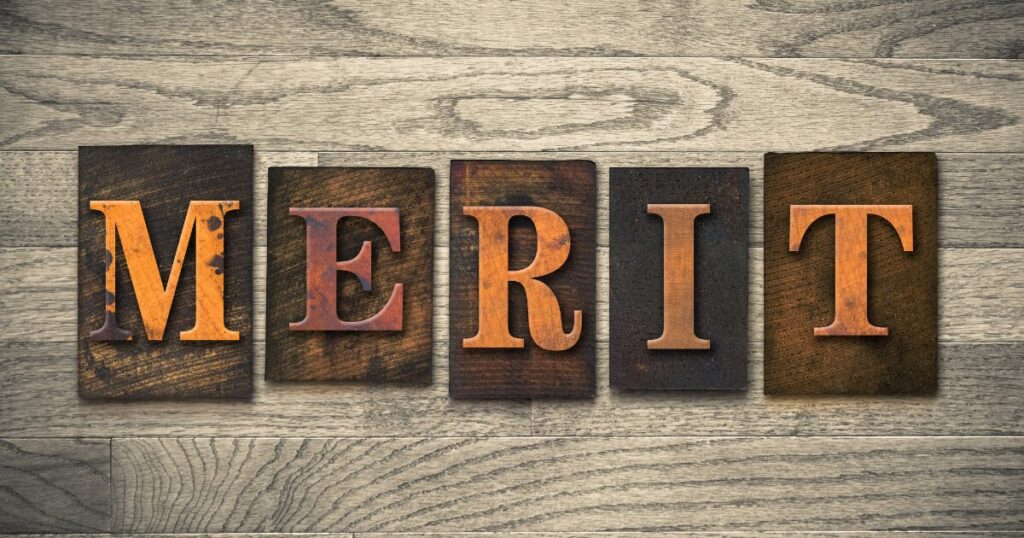
時系列を意識して文章を構成すると、読みやすく伝わりやすいコンテンツが作れます。
特にストーリー性が重要な記事や報告書・解説系コンテンツでは、その効果が顕著です。
時系列法がもたらす主なメリットを3つ紹介します。
読者が情報を自然に理解できる
最初になにが起きたのか・その後の展開・最終的にどうなったのか?…といった時間軸に沿った展開は、人間の脳が理解しやすい自然な思考パターンです。
文章を時系列で構成すれば、読者は迷うことなく情報を追え、理解度が飛躍的に向上します。
一貫性と信頼性を高められる
出来事を順番に並べていくことで、文章に一貫性が生まれます。
情報の整合性が保たれるため、この文章は信頼できると感じやすくなり、説得力もアップします。特にビジネスレポートや研究報告書などでは、論理的な構成が高く評価されます
ストーリー性が生まれ、読者を惹きつけやすい
時系列法は物語的な要素を持つため、読者にとって続きを読みたくなる魅力的な構成になります。
商品紹介や実体験のレビュー・教育系の記事などでも、時間の流れに沿って話を展開することで、読者の関心を引きやすくなります。
そのため時系列法は分かりやすく・伝わりやすく・読みやすい文章を書くための基本でもあり、強力なテクニックでもあるのです。
時系列で書く際のコツ・ポイント【5選】

時系列に沿って文章を書くのは、一見シンプルに見えます。
しかし、読者に伝わる・響く文章にするには、いくつかの視点から工夫が必要です。
さまざまな角度から、より魅力的な文章に仕上げるためのコツを5つご紹介します。
構成を決める前に『全体の流れ』を設計する
時系列で書くときは、何から始まり・どこで終わるかを明確にしてから文章を組み立てましょう。
特に長文では、前半・中盤・後半と、ストーリーの山場を意識することで読者の集中力が保てます。
【 ポイント 】 紙やマインドマップでザックリと時系列をメモする
書き手の『視点』を意識する
時系列で書くときは、誰の立場から見た流れかを統一しましょう。
ある出来事を第三者視点で書くか、当事者視点で書くかで、文章のトーンや読者の共感度が大きく変わります。
【 ポイント 】 読み手に感情を届けたいなら、あえて一人称で書くのも効果的
感情の変化も時間軸に沿って書く
物語や体験談では、出来事だけでなく感情の移り変わりも時系列に沿って描きましょう。
最初は不安だった⇒少しずつ希望が見えた⇒最後には達成感といった具合に、共感が生まれます。
【 ポイント 】 行動だけでなく、そのときどう感じたかも加えると臨場感がUP
読者が置いてけぼりにならないように配慮する
専門用語が多かったり、展開が早すぎると読者は流れを見失いがちです。
特にビジネス文書や説明系コンテンツでは、補足説明・具体例・注釈などで読者の理解をサポートしましょう。
【 ポイント 】 時間の区切りや重要なポイントは、見出しや太字で明示すると親切
メディアや目的に合わせて使い分ける
ブログ記事・プレゼン・報告書・SNS投稿など、時系列法の使い方はメディアによって変わります。
SNSでは短くテンポよく。報告書では事実を明確に並べるというように、読み手のニーズにあった表現を心がけましょう。
【 ポイント 】 用途によって『まずは⇒次に⇒最後に』『1つ目は~』などの表現を使い分けると◎
時系列で書く際に押さえておくべき注意点
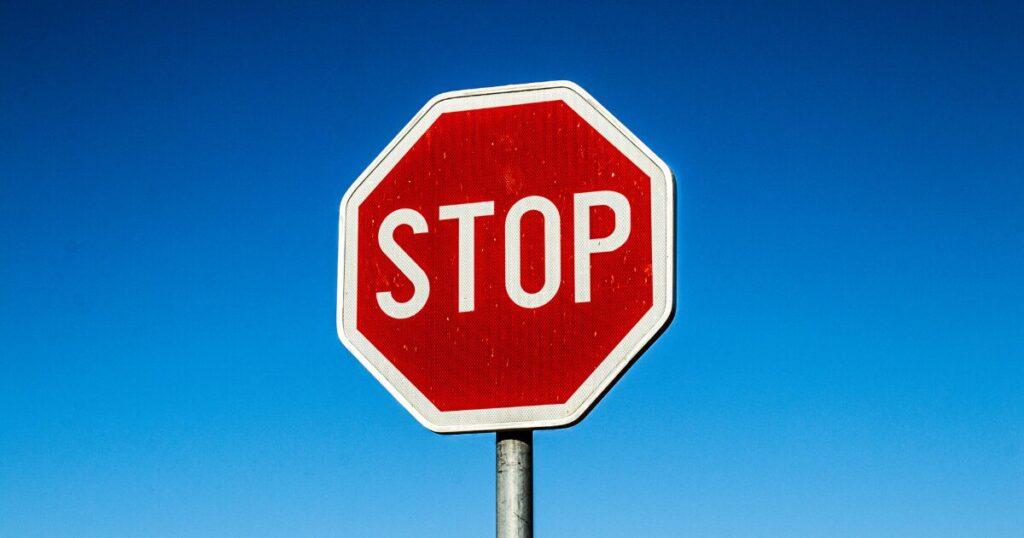
時系列で文章を構成する方法は、物事の流れを自然に伝える点です。
非常に効果的ですが、かえって読者を混乱させる原因にもなる、いくつかの注意点があります。
ここでは、時系列を活用する際に気をつけたいポイントを3つご紹介します。
『時間の前後関係』を明確にする

時系列に沿って書いているつもりでも、いつ起きたのかが曖昧だと、流れを正しく理解できません。
日付やその後・数日後・同じ日などの表現をうまく使って、時間の前後関係をはっきりと示すようにしましょう。
関係のない情報を挟まない

出来事の流れに関係のない補足情報や感想を挟むと、時系列の流れが途切れてしまいます。
補足を入れる場合は段落を分ける、または注釈的に扱うことで、本筋を分かりやすく保つ工夫が必要です。
単調な展開にならないよう自身の文章を客観視する
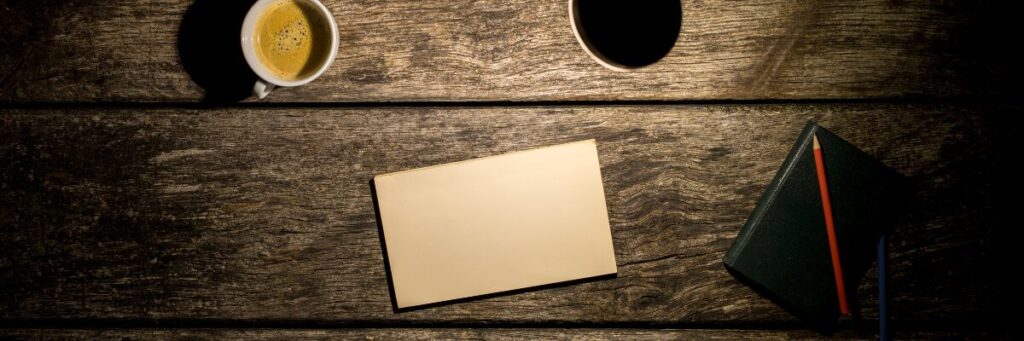
時系列は便利な一方で、単調な流れになりやすい構成でもあります。
読みやすくするためには、要所で要点のまとめや感情の描写、視点の変化などを挟み、文章にリズムを持たせると効果的です。
時系列ではない方法で伝わりやすい文章を書くには…?

文章を構成する上で時系列法は非常に有効ですが、伝える情報によっては様々なアプローチがあります。
そこで、本セクションでは時系列とは別の伝わりやすい文章構成のテクニックを3つご紹介します。
PREP法を活用する
PREP法は結論⇒理由⇒具体例⇒結論で構成する論理的な文章の型です。
説得力のある主張を短時間で伝えたいときなど、非常に効果的です。
SDS法を活用する
SDS法は要約⇒詳細⇒まとめの流れで構成する方法です。
情報をシンプルに伝えたいときや、いまお読みになっている記事(SEO記事)を始め、報告書、スピーチ、プレゼン資料などで活用できます。
読み手の情報ニーズに合わせて伝える
文章を書くうえで最も重要なのは「読み手が求めている情報はなにか?」を基準に構成を決めることです。
例えば、ライター初心者の方へ向けた記事なら、基本から応用へとレベルを上げる流れが一般的ですよね。(いきなり「クラウドソーシングではポートフォリオが重要!」なんて書かれていても理解は難しいはずです…)
そもそも文章の構成は単に情報の順番を考えるというわけではなく、読者の理解度を優先すべきです。
そのため、結論を始めに置き、次に詳細を説明するような「PREP法」や「SDS法」が文章構成の型として存在するのですが、これは「情報ニーズに合わせて伝える」という構成以前の考え方の話し。
まずは自分の書く文章は誰のためにあるのか?一度俯瞰してみることが“伝わりやすい文章”を書くうえでの最重要科目といえるでしょう!
時系列の書き方【まとめ】

文章の伝わりやすさは、時間軸に沿った流れに大きく左右されます。
時系列法とは、出来事や情報を起こった順に並べて伝える方法で、人間の脳が理解しやすい構造になっています。
会議の議事録・業務報告書・トラブル報告・物語構成など、さまざまな文書で有効活用でき、スタート地点⇒順序づけ⇒一貫性⇒ゴールまでを意識して書くことが大切です。
文章の流れを掴み、伝えたい内容がきちんと書けるよう、時間軸をうまく捉えて時系列法を実践していきましょう。

時系列の書き方を調べている方からよくある質問

よくある質問① 時系列で文章を書くときのコツはなんですか?
基本的なコツは時間の流れに沿って順番に書くことです。
冒頭でいつの出来事かを明確にし、起こった順にエピソードや出来事をつなげていくと、読み手にとって分かりやすい文章になります。
よくある質問② 時系列で書くと文章が単調になります。どうすればいいですか?
単調さを防ぐには、感情の変化や場面の転換を入れるのが効果的です。
また、適度に会話文や具体的な描写を交えると、臨場感が増して読者を飽きさせません。
よくある質問③ 現在と過去が混ざる内容でも時系列で書けますか?
はい、書けます!
主軸となる時間軸(過去・現在など)を決めておき、時間が前後する場面では時制の転換が分かる表現を加えて混乱を防ぐことで、現在と過去がごちゃまぜにならずに時系列で書けるようになっています。