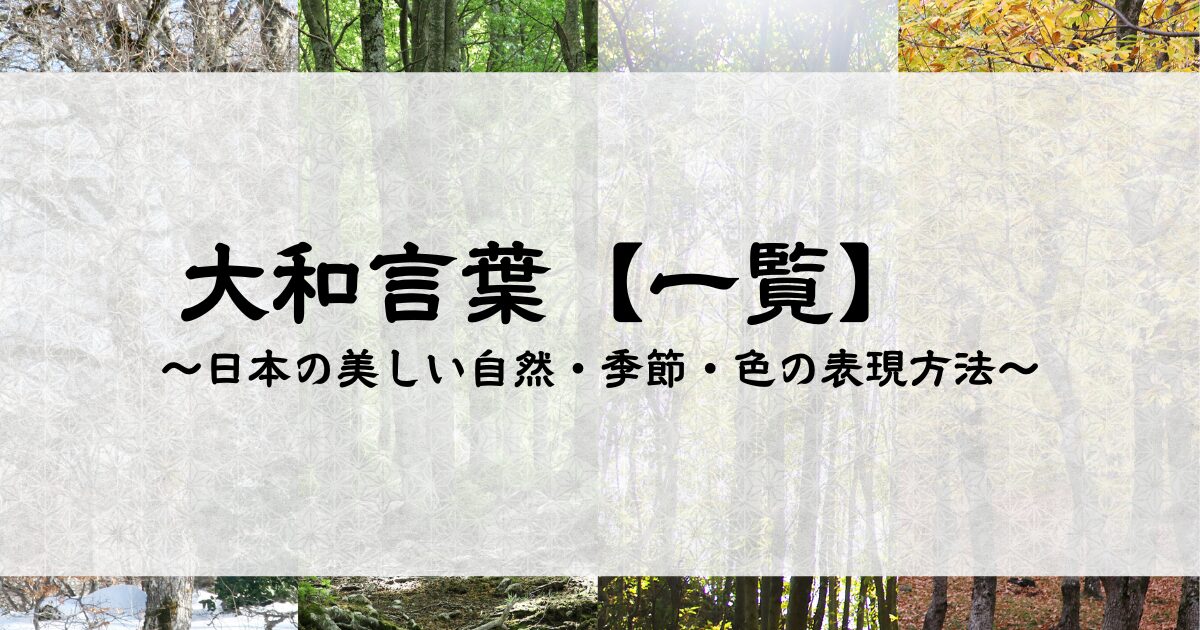私達が普段から口にする「ありがとう」という言葉。
相手に感謝を伝える言葉であることはみなさんご存じかと思いますが、耳で聞いても口に出しても、なんとも柔らかく穏やかな雰囲気があると思いませんか?
日本には、古来より伝わる「大和言葉」というものがあります。
この「ありがとう」という言葉も「大和言葉」の1つです。
「大和言葉」を上手に丁寧に使うことによって、日本らしい情緒ある表現が可能になります。
本記事では、美しい「大和言葉」の特徴や、現代での使用例まで、たっぷりの一覧も交えながら詳しくお伝えします!

大和言葉(やまとことば)とは?
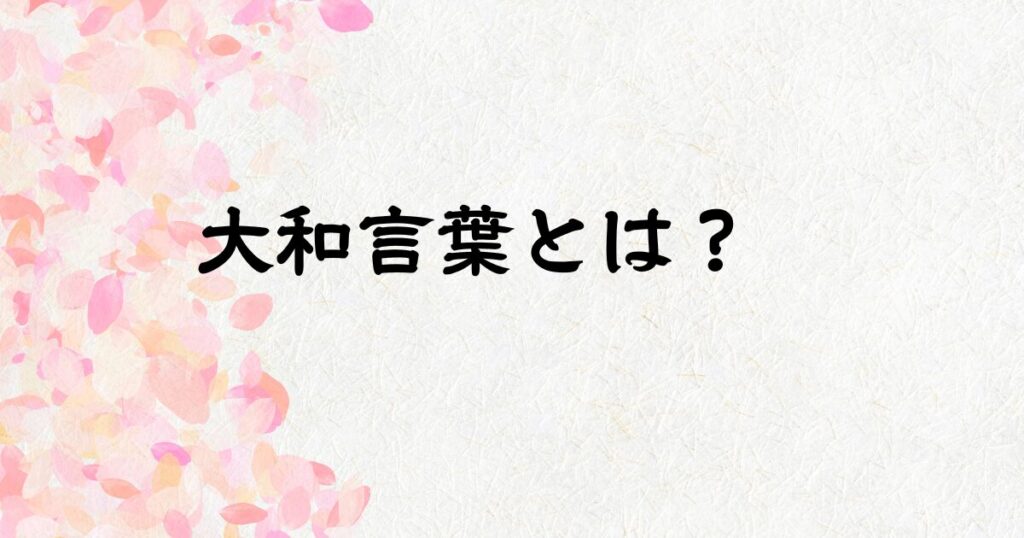
島国である日本には、独自に進化を遂げたものが多数あります。
中でも「日本語」は、自然とも深い繋がりがあり世界的に見ても優しく、美しい響きを持った言葉と言えるでしょう。
現在使われている日本語は、その成り立ちによって主に3種類に分けられます。
- 大和言葉(和語)
漢語などを含む大陸文化が到達する前から、日本で使われてきた固有の言葉。平安時代に使われていた特に優雅な言葉を指すこともあるが、以下の漢語、外来語以外のものをいう。
- 漢語
中国から入ってきた言葉。一説によると紀元3世紀頃に伝わったと言われる。一般的に漢字を組み合わせてできており、読む時は音読みが使われる。
- 外来語
中国以外の外国から由来し、その後日本に定着した言葉。主にカタカナで表記される。
「大和言葉」は、まだ文字のない奈良時代よりも前から、私たち日本人の祖先が美しい自然の中で話し言葉として生み出した言葉です。
大和言葉と聞くと昔、古典の授業で習ったような「いとをかし」「さもありなむ」のような言葉を想像されるかもしれませんが、実は現在も日常的に使われている温もりのある言葉なのです。
大和言葉はひらがなで表記されることも多く、漢字を使った場合でも訓読みになります。
音読みの漢語やカタカナ表記の外来語は、どうしても言葉の響きが固くなりますが、大和言葉は響きが柔らかく美しいことが特徴です。
また、漢語は漢字自体に意味があり組み合わせることで新たな言葉を作ることができますが、大和言葉はもともとが話し言葉であり、ひらがな1文字にも意味が含まれると言われています。
私達が日常、あまり意識することなく使っている日本語。
大和言葉は漢語や外来語に押され使われる機会が徐々に減っていたのですが、近年その良さが見直され始めています。
日本生まれの言葉のため、日本人の感性に合っているとも言えます。
言葉を使う状況に応じて上手に大和言葉を取り入れることで、品のある美しい日本語を使うことができるのです。
では実際に大和言葉にはどのようなものがあるか、パターンごとに見てみましょう。
大和言葉一覧【時間編】

古来から日本人は自然と密着しながら生活を送ってきました。
自然の流れに沿うように生活してきた中で、一年の中では季節の移り変わり、日々の中では日の出や日の入りや月の満ち欠けなどにより時間の経過を感じてきました。
日本人は繊細かつ独特な感覚で時間を捉え、以下の一覧のように美しく表現した大和言葉をたくさん生み出しています。
| 言葉(よみ) | 意味 |
| 暁(あかつき) | 夜明けの薄暗い頃 |
| 曙(あけぼの) | 夜明け ※一説では春を指すことが多い |
| 朝ぼらけ(あさぼらけ) | 夜明け ※一説では秋冬を指すことが多い |
| 朝まだき(あさまだき) | 夜が明けきらない早朝 |
| 小夜(さよ) | 夜 |
| 東雲(しののめ) | 早朝のわずかに明るくなる頃 |
| 黄昏(たそがれ) | 日が暮れる薄暗い頃 |
| ひねもす | 一日中 |
| 昼下がり(ひるさがり) | 正午を少し過ぎたころ |
| 宵の口(よいのくち) | 日が沈んですぐ |
| 夜更け(よふけ) | 深夜 |
| 夜もすがら(よるもすがら) | 一晩中 |
大和言葉一覧【自然編】

季節の移ろいとともに生活を送ってきた日本人は、自然に関する大和言葉をたくさん生み出しました。
例えば、みなさんご存じの『竹取物語』では、竹から生まれたかぐや姫は美しく育ち十五夜で月に帰ってしまいます。
また、『七夕物語』では天の川を挟んで輝いているわし座のアルタイルとこと座のベガを、彦星と織姫に見立てたお話になっています。
このように、大和言葉の中には月や星を用いた言葉や、それらを美しく表現する言葉が多数存在しているのです。
今よりもはるかに暗かったであろう夜の闇を静かに照らす月や星は、日本の文化、文学において情景を表現する際に重要な役割を果たしています。
このセクションでは月や星以外にも花や風など、自然を元にした大和言葉についてご紹介します。
非常にたくさんの言葉を一覧でお知らせしますが、いずれの言葉も耳にしただけで光景が思い浮かんでくるような美しい表現です。
是非想像しながらご覧ください。
月

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 天満月(あまみつづき) | 夜空いっぱいに光輝く月 |
| 有明の月(ありあけのつき) | 夜明けになっても残っている月 |
| 十六夜(いざよい) | 満月の翌日 |
| 朧月(おぼろづき) | 靄に包まれて柔らかく霞んで見える春の夜の月 |
| 月の剣(つきのつるぎ) | 三日月 |
| 月映え(つきばえ) | 月の光に照らされて美しく映えて見える |
| 月読(つきよみ・つくよみ) | 月の神 |
| 望月(もちづき) | 満月 |
| 昼下がり(ひるさがり) | 正午を少し過ぎたころ |
| 弓張り月(ゆみはりつき) | 半月(上弦の月・下弦の月) |
| 宵月(よいづき) | 秋の宵の時間帯に出る月 |
花

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 徒花(あだはな) | 咲いて散った後に実をつけない花、見かけだけ良くて内容が伴わないこと |
| 狂い咲き(くるいざき) | 季節外れの時期に花が咲く |
| 咲き誇る(さきほこる) | たくさんの花が美しく咲く様子 |
| 高嶺の花(たかねのはな) | 手に入れることができない憧れの存在 |
| 花明かり(はなあかり) | 暗闇の中で光って見える花の様子 |
| 花盛り(はなさかり) | 花が盛んに咲く様子やその季節 |
| 花の都(はなのみやこ) | 華やかで美しい都 |
| 花冷え(はなびえ) | 桜が咲く時期に寒さが戻ること |
| 忘れ花(わすればな) | 遅れて咲く花 |
| 弓張り月(ゆみはりつき) | 半月(上弦の月・下弦の月) |
| 爛漫(らんまん) | 花が咲き乱れている様子 |
風

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 青田風(あおたかぜ) | 初夏に吹く風 |
| 秋風が立つ(あきかぜがたつ) | 愛情が薄れること |
| 朝明の風(あさけのかぜ) | 朝の風 |
| 追風(おいて) | 後ろから吹く風 |
| 風薫る(かぜかおる) | 新緑の季節に吹く爽やかな風 |
| 凩(こがらし) | 木の葉を散らす晩秋から初冬にかけて吹く強い風 |
| 東風(こち) | 春に吹く東からの風 |
| そよ風(そよかぜ) | やさしく吹く風 |
| 野分(のわき) | 秋から冬にかけて吹く強い風 |
| 春疾風(はるはやて) | 春に吹く激しい突風 |
| 山背(やませ) | 山を越えて吹く風 |
| 夕風(ゆうかぜ) | 夕方に吹く風 |
星

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 天の川(あまのがわ) | 夜空に帯状に見える星の集まり |
| 暁星(ぎょうせい) | 夜明けの空に残っている星 |
| 綺羅星(きらぼし) | 光り輝く無数の星 |
| 箒星(ほうきぼし) | 彗星 |
| 星月夜(ほしづきよ) | 星の光が月のように明るい夜 |
| 星の林(ほしのはやし) | 星が多いこと |
| 星の宿り(ほしのやどり) | 星座 |
| 明星(みょうじょう) | 金星 |
| 夕星(ゆうつづ) | 夕方西の空に見える金星 |
大和言葉一覧【天気編】

私達が一年を通して様々な天気に出会えるのは、日本に四季があるからこそです。
例えば、英語で「rain」と表現される「雨」も、四季によって強弱や期間が異なり雨を見る側の感じ方も違ってきます。
日本における天気の繊細な側面について、天気とは別の言葉と組み合わせることで情緒溢れる大和言葉として成立させているのです。
天気を元にした美しい大和言葉はニュースや新聞などで目にする機会も多く、現在の私達にとっても馴染み深いものが多いのではないでしょうか。
言葉を聞くだけで太陽や雨の降り方まで容易に想像できることが、天気を表す大和言葉の魅力の1つです。
晴れ

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 日和(ひより) | 晴天 |
| 小春日和(こはるびより) | 初冬の穏やかで暖かい晴天 |
| 菊日和(きくびより) | 菊が咲く秋の晴天 |
| 霜日和(しもびより) | 霜が降りたあとの晴天 |
| 五月晴れ(さつきばれ) | 五月のすがすがしい晴天 |
| 麗らか(うららか) | 空が晴れて、おだやかな天候 |
雨

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 小糠雨(こぬかあめ) | 霧のような雨 |
| 木の葉時雨(このはしぐれ) | 木の葉がさらさら鳴ったり止んだりする様子 |
| 五月雨(さみだれ) | 梅雨、長雨 |
| 時雨(しぐれ) | 晩秋から冬の始めにかけてよく見られるにわか雨 |
| 日照雨(そばえ) | 日が照っているのに雨が降ること、きつねの嫁入り |
| 花の雨(はなのあめ) | 桜が咲く時期に降る雨 |
| 春雨(はるさめ) | 春の雨、ぐずついた天気 |
| ひとしぼり | 一時的に雨が強く降ること |
| 群雨(むらさめ) | にわか雨 |
| 遣らずの雨(やらずのあめ) | 帰るのをためらわせる雨 |
| 夕立(ゆうだち) | 夏の午後から夕方にかけてよく見られる激しいにわか雨 |
雪

| 言葉(よみ) | 意味 |
| 淡雪(あわゆき) | 軽くて薄い雪 |
| 粉雪(こなゆき) | 粉のように細かく舞う雪 |
| 細雪(ささめゆき) | 細かくしとしと降る雪 |
| 垂り雪(しずりゆき) | 積もって垂れ下がる雪 |
| 玉雪(たまゆき) | 粒が丸い形で降ってくる雪 |
| 名残りの雪(なごりのゆき) | 春に溶け残っている雪、春先に降る雪 |
| ぼたん雪(ぼたんゆき) | 大きくてふんわりとした雪 |
| 霙(みぞれ) | 雨まじりで降る雪 |
| 雪明り(ゆきあかり) | 雪が光を反射して明るいこと |
| 雪の花(ゆきのはな) | 花びらのように舞い散る雪 |
| 雪夜(ゆきよ) | 雪の降る夜 |
大和言葉一覧【色編】

大和言葉には、四原色と呼ばれる基本の色があります。
- 赤 : エネルギーに満ちた、熟した色
- 青 : 未成熟な状態を表す色(赤の反対)
- 白 : 光り輝く様子を表す色
- 黒 : 光も何もない「はじめ」を意味する神聖な色
四原色とは、赤、青、白、黒であり、後ろに「い」を付けて成り立ちます。
「青」は「青葉」など新芽の緑色を表すことがあるように、他の三色以外のあいまいな色の表現にも使われていたため、古来の日本人はこの四原色で色を表現することができていたと言われています。
その後、四原色以外に色を表す大和言葉が数多く生まれました。
ここ数年、巷で人気の「日本の伝統色」を彩色できる色鉛筆をご存じですか?
四季折々の自然が見せる微妙な色合いを表現できるとして、非常に話題になっています。
これら「日本の伝統色」の色の名前も大和言葉です。
色を表す大和言葉は、自然の中にある動植物などを上手く捉えて名付けられています。
西洋の色の名前にはない日本特有の趣のある珍しい色も多く、繊細な雰囲気が伝わります。
あなたはいくつご存じでしょうか?
| 言葉(よみ) | 意味 |
| うぐいす色 | うぐいすの羽のような緑に黒茶の混ざった色 |
| 乙女色(おとめいろ) | 乙女椿(おとめつばき)のような黄色味を含んだ淡い赤色 |
| 金糸雀色(かなりあいろ) | カナリヤの羽のような明るい黄色 |
| 紺碧(こんぺき) | 真夏の空のような深く濃い青色 |
| 漆黒(しっこく) | うるしを塗ったような艶のある黒色 |
| 白練(しろねり) | 絹の純白のような混じりけのない白色 |
| 翠色(すいしょく) | 樹木の緑色 |
| 躑躅色(つつじいろ) | ツツジの花ような鮮やかな赤紫色 |
| 藤紫(ふじむらさき) | 藤の花のような薄く明るい青紫色 |
| 紅色(べにいろ) | 鮮やかな赤。くれない色 |
| 濡羽色(ぬればいろ) | カラスの羽が濡れているように見えるのと同じような黒色 |
| 紫式部(むらさきしきぶ) | 紫式部の実のような赤みのある渋い紫色 |
| 山吹色(やまぶきいろ) | 山吹の花のような赤みを帯びた黄色 |
| 瑠璃色(るりいろ) | 紫色を帯びた濃い青色 |
大和言葉一覧【一文字編】
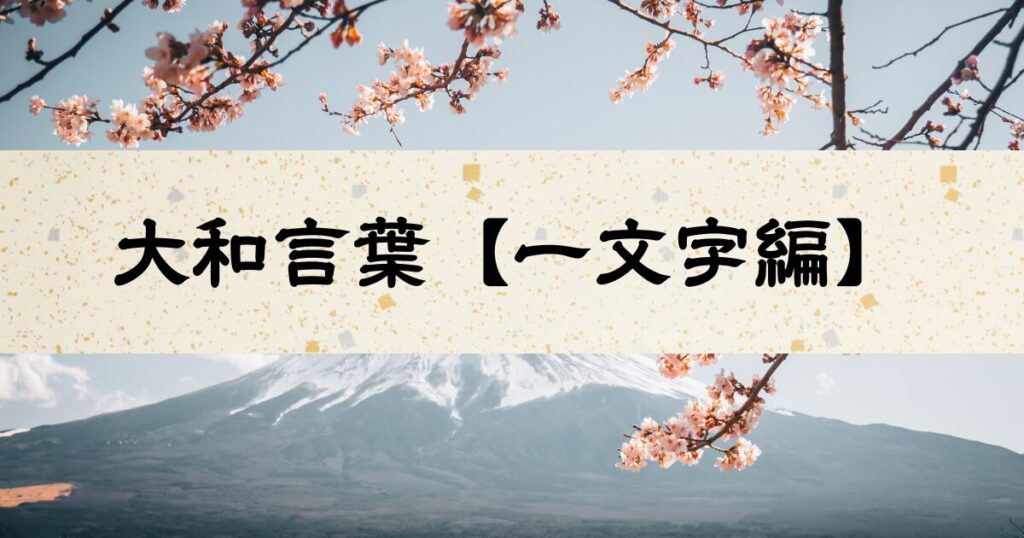
大和言葉には漢字一文字で表されるものもあります。
難しい漢字もありますが、比較的現在も日常会話でよく使われており、音を聞けばご存じの言葉も多いのではないでしょうか。
読みはすべて訓読みになっています。
| 言葉(よみ) | 意味 |
| 粋(いき) | 洒落ていること |
| 今(いま) | まもなく |
| 項(うなじ) | カ首の後ろ |
| 乙(おつ) | ひねりが利いていること |
| 頑(かたくな) | 頑固 |
| 霧(きり) | 地表近くに集まる、小さな水の粒の集まり |
| 踝(くるぶし) | 足首付近の飛び出した骨 |
| 寿(ことぶき) | 祝うこと、めでたいこと |
| 藤朔(さく) | 新月 |
| 峠(とうげ) | 山を登りつめて、これから下りになるところ |
| 凪(なぎ) | 風がやみ波が穏やかになること |
| 薑(はじかみ) | 生姜 |
大和言葉一覧【二文字編】
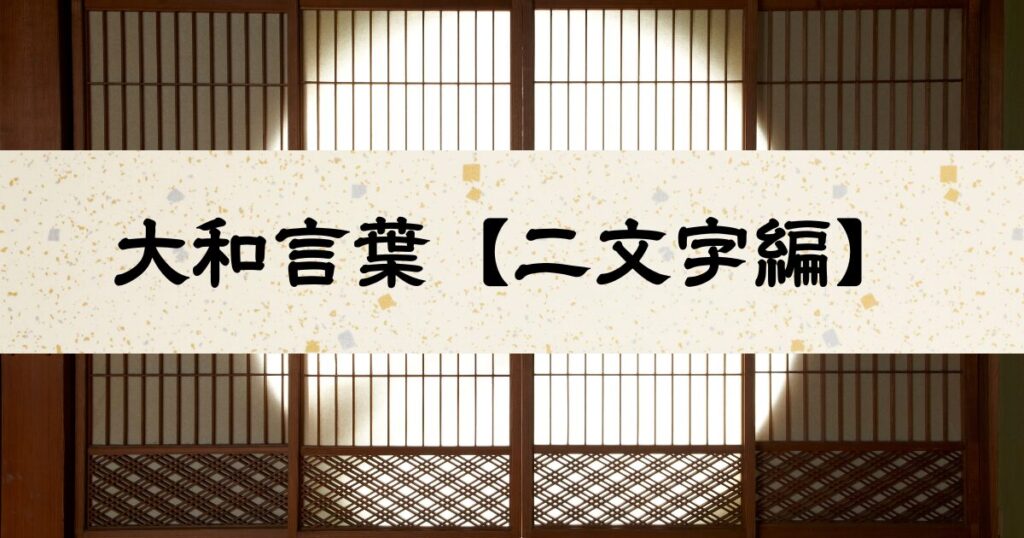
訓読みの漢字を二つ繋げてできた大和言葉は個々の漢字の意味が合わさり、より複雑な内容を表現しています。
耳にすることは多いですが、他ではあまり使わないような特殊な漢字の読み方になっているものもあります。
| 言葉(よみ) | 意味 |
| 塩梅(あんばい) | 加減 |
| 泡沫(うたかた) | 泡 |
| 空蝉(うつせみ) | 蝉の抜け殻 |
| 心恋(うらこい) | 恋しく思うこと |
| 逢瀬(おうせ) | 男女ふたりが会うこと |
| 我酒(がざけ) | やけ酒 |
| 枯野(かれの) | 草が枯れた冬の野原 |
| 久遠(くおん) | 永遠 |
| 後世(ごせ) | あの世 |
| 氷柱(つらら) | つらら |
| 常若(とこわか) | いつも若いこと |
| 鳴神(なるかみ) | 雷 |
大和言葉一覧【三文字編】
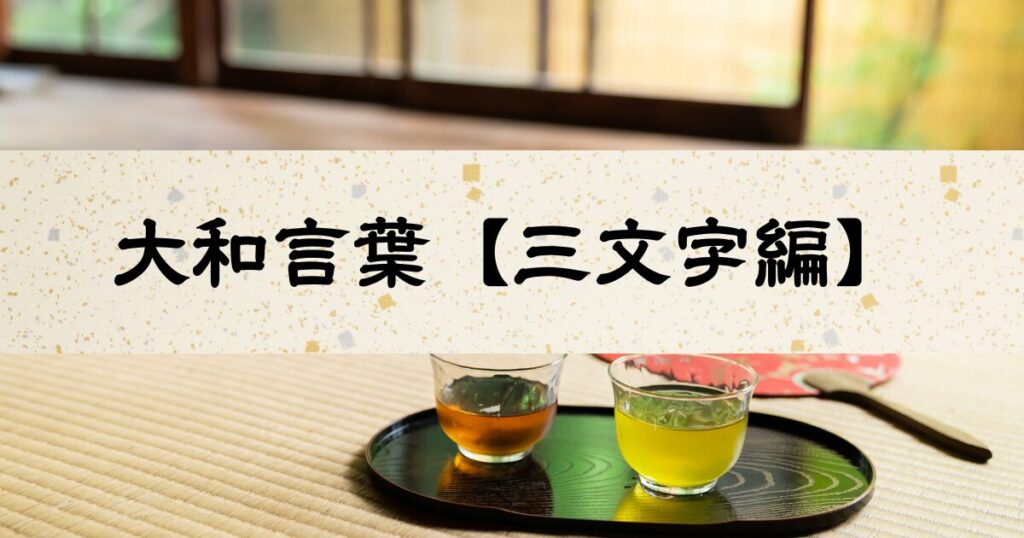
三文字の大和言葉には、短い文章がまとまったような印象があります。
一文字一文字に意味があるためたった三文字で構成されているにも関わらず、この言葉を聞くだけで状況がすぐに想像できる言葉になっています。
| 言葉(よみ) | 意味 |
| 相思い(あいおもい) | お互いに思い合っていること |
| 赤富士(あかふじ) | 富士山が夏の早朝、朝日で赤く染まって見える景色 |
| 秋田実(あきたのみ) | 稲穂 |
| 息の緒(いきのお) | 命 |
| 打ち水(うちみず) | 地面に水をまき、温度を下げること |
| 有頂天(うちょうてん) | 最高に嬉しいこと |
| 大晦日(おおみそか) | 年の瀬、十二月三十一日 |
| 奥の手(おくのて) | 簡単には他人に教えない手段 |
| 生一本(きいっぽん) | ひたむき |
| 清らか(きよらか) | 汚れがなく美しい様子 |
| 猪口才(ちょこざい) | 生意気 |
| 冬支度(ふゆじたく) | 冬を迎える準備 |
| 身の丈(みのたけ) | その人の能力 |
大和言葉一覧【日常会話編】|例文付き

これまでに出てきた大和言葉の一覧をご覧になり、大和言葉の魅力を体感いただけているのではないでしょうか。
柔らかで美しい響きを持つ大和言葉を日常会話に取り入れるだけで、穏やかで上品な会話が可能です。
また、日常会話として使われる大和言葉には、相手を敬う気持ちが込められています。
こちらのセクションでは、取り入れることで会話のグレードが向上する大和言葉を、知的で美しい例文を交えてご紹介します。
| 言葉(よみ) | 意味/例文 |
| 痛み入る(いたみいる) | もったいなく、ありがたい /お褒めの言葉を頂きまして誠に痛み入ります。 |
| 慈しむ(いつくしむ) | 大切に思う /両親は私を、慈しみ育ててくれました。 |
| おいとまする | 帰る /本日はこのあたりでおいとまします。 |
| お裾分け(おすそわけ) | 使い切れないものを分ける /お土産をたくさんいただいたので、お裾分けをします。 |
| お手柔らかに(おてやわらかに) | 手加減する /どうぞお手柔らかにお願いします。 |
| お目にかかる(おめにかかる) | 相手と会う /お目にかかれて光栄です。 |
| お心置きなく(おこころおきなく) | ご遠慮なく /お気付きの点がございましたら、お心置きなくお知らせください。 |
| このうえなく | これ以上ないくらいに /桜はこのうえなく美しく咲き誇っていました。 |
| 心待ちにする(こころまちにする) | 期待して待っている /あなたからのお便りを心待ちにしております。 |
| 胸を撫でおろす(むねをなでおろす) | 安心する /ご無事と聞いて、胸を撫でおろしました。 |
| ゆるり | ゆっくり、力が抜けている /どうぞごゆるりとお過ごしください。 |
大和言葉一覧【ビジネス編】|例文付き

ビジネスにおいては、仕事相手とのコミュニケーションを円滑に進めるために、限られた時間の中で自身の印象を良くすることが重要です。
また、ビジネスの場では日常会話に比べて簡潔なやりとりが求められることも多いため、短い言葉の中に多くの意味を持つ漢語やカタカナの外来語を用いることが増える傾向にあります。
漢語や外来語を使うとどうしてもやや堅い印象になったり、よそよそしさを感じたりします。
そういう場で堅苦しい表現をうまく和らげてくれる大和言葉を巧みに用いることにより、あなたの丁寧な人柄を感じてもらうことができるのです。
大和言葉の美しい響きは、それを使う人の人柄に品を感じさせます。
以下にビジネス向けの大和言葉を、例文とともにご紹介します。
さっそく使ってみましょう。
| 言葉(よみ) | 意味/例文 |
| 恐れ入る(おそれいる) | すみません、申し訳ない /恐れ入りますが、明日までにご確認いただきたく存じます。 |
| お知恵をお借りする(おちえをおかりする) | 教えてもらう /こちらの件に関しまして、是非お知恵をお借りしたく存じます。 |
| お手すき(おてすき) | が空いている /お手すきの際にお電話いただけますでしょうか。 |
| お引き立て(おひきたて) | 相手からひいきにしてもらうことを願う /今後ともお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。 |
| お含み置き(おふくみおき) | 理解して欲しい、知っておいて欲しい /明日より5日まで休業させていただきますこと、お含みおきくださいませ。 |
| 折り入って(おりいって) | 特に /本日は、折り入ってご相談がございます。 |
| ひとかたならぬ | 非常に、大変 /ひとかたならぬご厚情を賜り、御礼申し上げます。 |
| やむなく | 仕方なく /申し訳ございませんが、やむなく欠席致します。 |
| ゆくゆくは | 将来的には /ゆくゆくは、このプロジェクトを全国に広げていきたいと思います。 |
| よしなに | ちょうど良い具合に /どうぞ、よしなにお取り計らいのほど、お願い致します。 |
| 力添え(ちからぞえ) | 助けること /是非お力添えを賜りたく存じます。 |
まとめ:大和言葉は相手に柔らかい印象を与えることができる

多くの事例を元に大和言葉の持つ魅力についてお伝えしました。
ひらがなや訓読みで表現される大和言葉は耳にした時の印象もなめらかで、また口にするのも柔らかく温かみのある言葉であることがおわかりいただけたかと思います。
大和言葉とは、他国の文化が伝わるよりも前から私達の祖先が生み出した日本固有の言葉であり、古の日本人がそうであったように自然を感じ自然と寄り添う優しく穏やかな言葉です。
日本は昔から大和言葉以外にも他国の言葉を取り入れながら、独自の表現を作り出してきました。
情報化社会と言われる昨今、漢語や外来語といった端的な表現が増えて大和言葉が登場する機会は減っていると言われています。
端的な表現も必要ではありますが、現代だからこそ美しく味わい深い大和言葉を上手に扱い、心のこもったやりとりを心掛けてもよいのではないでしょうか?
大和言葉が生まれてきた情緒豊かな背景を感じながら、是非様々な場面で品のある柔らかい言葉を楽しくお使いください。

よくある質問
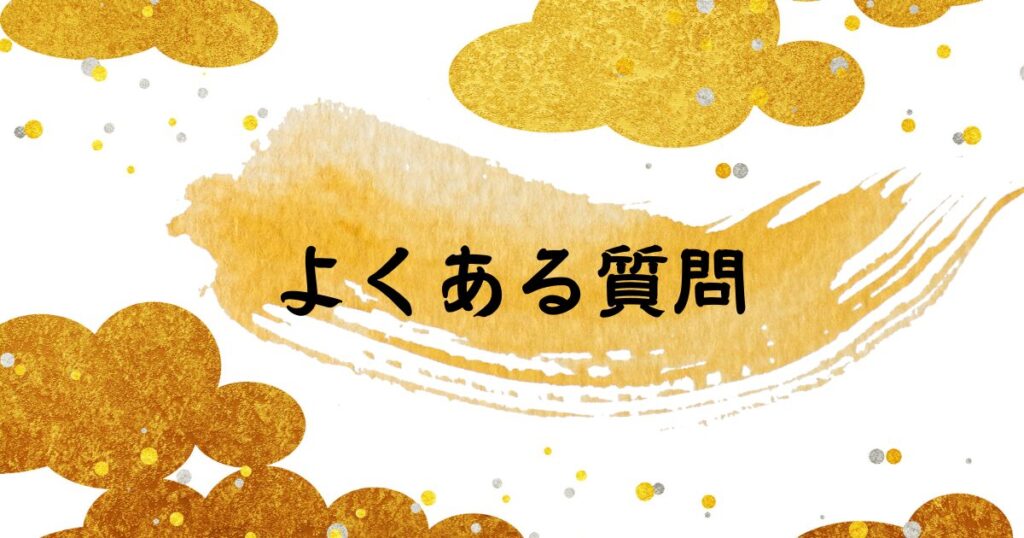
よくある質問①大和言葉を使うメリットとはなんですか?
大和言葉の美しい響きにより、上品さや柔らかい印象を演出することができます。
大和言葉自体に相手を敬う気持ちが含まれているとも言われています。
目上の方への文章に使えば、より一層敬意を伝える効果があります。
さらに、この柔らかい印象から、言いにくいことでもオブラートで包んだように伝えたい時にも有効です。
また、現代は漢語や外来語を用いることが多くなっています。
文章中に同じような意味の表現をしたい場合、漢語や外来語から大和言葉に言い換えることにより、同じ表現ばかりが重なるのを避けることもできます。
よくある質問②大和言葉の効果的な使い方はありますか?
現在はSNSなどの台頭により、端的な表現が増えています。
短文で使いやすいのは漢語ですし、スマートに感じるのは外来語が多いため、柔らかい言い回しの大和言葉の文章中での使用は減っています。
その状況を逆手に取りワンポイントとして大和言葉を取り入れることで、より効果的に品のある印象を与えることができます。
よくある質問③大和言葉を使う上で注意した方がよい点はありますか?
大和言葉には美しい響きがあり確かに上品な印象を与えることができますが、会話や文章中に何度も出てくると回りくどく感じられたり気取っていると誤解されたりする可能性もあります。
文章の中には大和言葉だけでなく口語文や漢語、外来語などもうまく織り交ぜながら伝わりやすい表現を心掛けましょう。
また、大和言葉は直接的な言い回しではなく間接的な表現です。
結局、何を言いたいのかわかりにくくなる恐れもありますので、時と場合に応じて上手く使うようにしてください。
特に「お断り」などの場合は、伝え方次第で曖昧な表現になりますので注意しましょう。
普段からnote、X、Instagramで自身の発信も行っています。
テーマに沿った深いリサーチを元に、丁寧にお伝え致します。