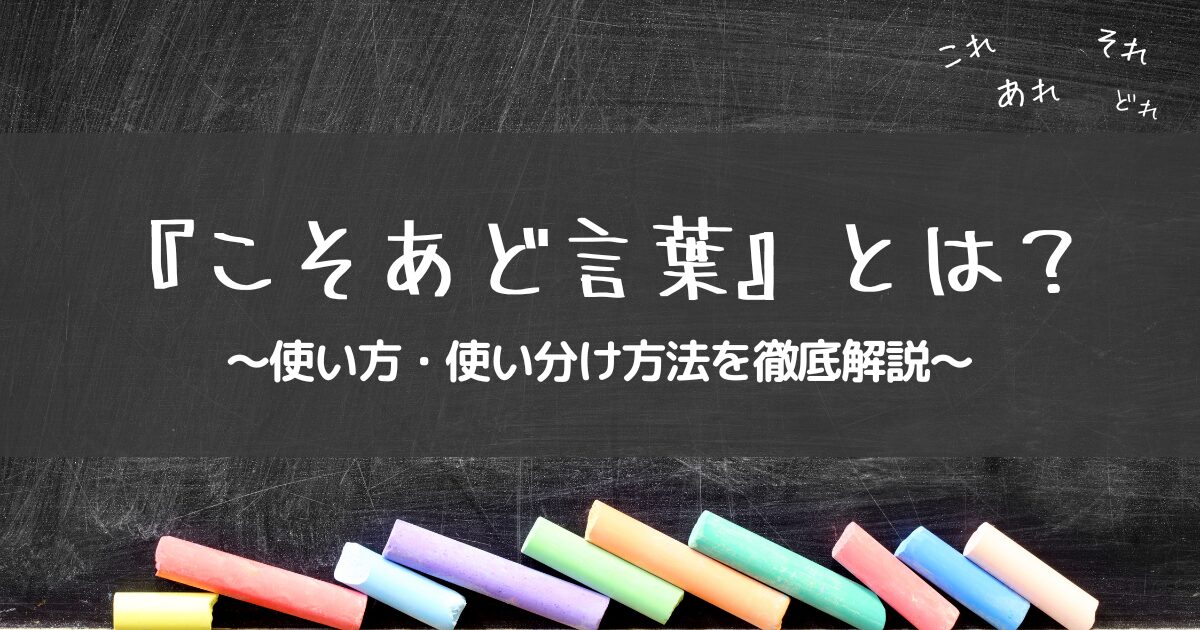「こそあど言葉」はどうすれば上手に使えるの?
「こそあど言葉」は長い文章を短くシンプルにし、わかりやすく整理してくれる便利な言葉です。
しかし、使い方を間違えてしまうと意味が伝わりにくい文章になったり、話の食い違いの原因となるかもしれません。
本記事では「こそあど言葉」の意味や指示語としての使い方を詳しく解説していきます。
最後まで読むことで正しい日本語の使い方が理解でき、簡潔でわかりやすい文章の作成のヒントを得られるでしょう!
特に文章を扱う仕事に就いている方には必見の内容となっています。

意外と知らない!? こそあど言葉の意味
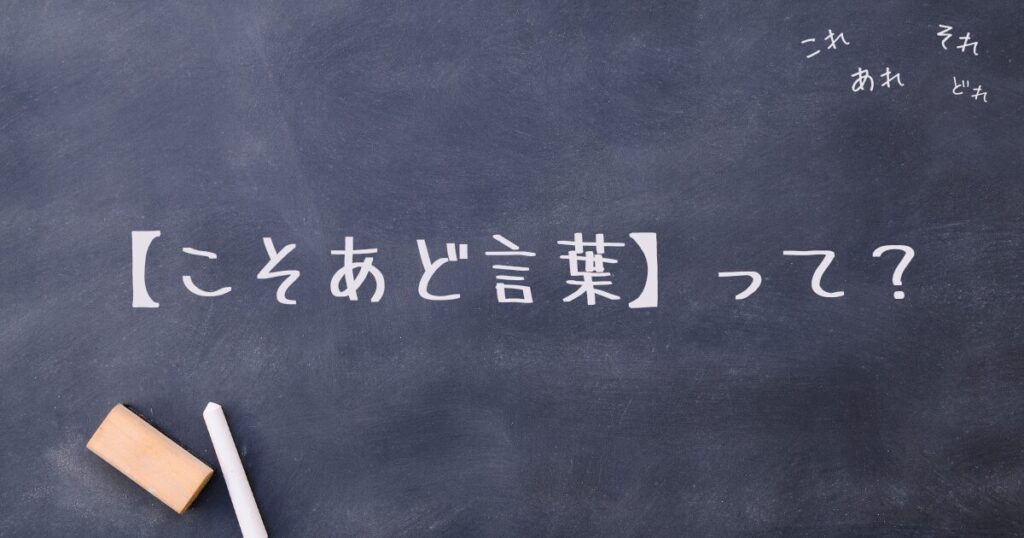
「こそあど言葉」とは、物や場所、人など「あらゆる物事を指し示す役割」を持つ言葉です。
誰もが日常的に使用している言葉ですが、ほとんどの人が「こそあど言葉」とは思わずに無意識に使用しているかもしれません。
多く使われる「こそあど言葉」の代表は「これ」「それ」「あれ」「どれ」です。
知りたいことや指示したい内容で「こそあど言葉」の使い方は以下のように変わります。
| 指示語 | 意味 |
|---|---|
| ここ、そこ、あそこ、どこ | 場所を指し示す |
| この、その、あの、どの | 直後の名詞を詳しく説明する |
| こう、そう、ああ、どう | 方法を示す |
| こっち、そっち、あっち、どっち | 方角を指し示す |
文章中に用いるときは、前述で書かれていることを繰り返さず「こそあど言葉」に置き換えることで、長い文章を短くまとめることができます。
【例①】
この前の日曜日、千葉県にある水族館に行きました。千葉県にある水族館で見たイルカのショーが本当に素晴らしく、良い思い出となっています。
【例②】
この前の日曜日、千葉県にある水族館に行きました。そこで見たイルカのショーが本当に素晴らしく、良い思い出となっています。
いかがでしょう?
【例①】より【例②】のほうが簡潔で読みやすくはないでしょうか?
また、会話中に用いるときには自分自身を起点とし「こそあど言葉」を使い相手に伝えることで、意図が明確に伝わりスムーズなコミュニケーションを築けるでしょう。
【例①】
「マヨネーズ取って」
【例②】
「そこのマヨネーズ取って」
どこにマヨネーズがあるかわかりにくい場合、指差しの動作と共に「そこの」と言葉を添えると相手にも明確に伝わりやすいです。
このように、「こそあど言葉」は円滑なコミュニケーションのための指示語として、日常的によく用いられていることがわかります。

【読解力UP】こそあど言葉の品詞ごとの使い方

「こそあど言葉」についてさらに詳しく見ていきましょう。
品詞ごとの使い方を理解することで「こそあど言葉」の適材適所がわかり、読者に伝わりやすい文章を作成できます。
指示語と品詞を組み合わせた一覧表が以下です。
| 品詞名 | こ(近称) | そ(中称) | あ(遠称) | ど(不特定称) |
|---|---|---|---|---|
| 指示副詞 | こう | そう | ああ | どう |
| 指示連体詞 | この | その | あの | どの |
| 指示代名詞 | これ | それ | あれ | どれ |
| 指示形容詞 | こんな | そんな | あんな | どんな |
このセクションではそれぞれの指示語と名詞の組み合わせについて解説します。
指示副詞

指示副詞は「こう、そう、ああ、どう」など、対象となる物事や人の状態・態度、動作を伝える時などに使用する品詞です。
話し手が自分の動作を交えて説明したり、近くにある対象のものを指しながら使用します。
「こうすれば上手に動かすことができますよ。」
「こうなったときは最初からやり直しですか?」
相手の動作や状態について指す場合や、既に出ている話題や動作、状態を指す場合に使用します。
「そうです。あなたの言うとおりです。」
「そう怒らないでください。」
自分や相手から離れた動作や状態、また以前の話題や行動などについて指す場合に使用します。
「ああ言ったのは、あなたのためだよ。」
「ああやってやるといいですよ。」
動作や状態が不明な時や、相手に方法を尋ねる場合に使用します。
「どうすればいいですか?」
「体調はどうですか?」
自分や相手の行動、状態を知りたいときや示したいとき、また方法などを相手に尋ねるときに指示副詞は有効です!

自分や相手の行動、状態を知りたいときや示したいとき、また方法などを相手に尋ねるときに指示副詞は有効です!
指示連体詞

指示連体詞は「この、その、あの、どの」の言葉を名詞の前につけることで、直後の名詞を修飾する働きを持つ品詞です。
話し手から近くにある対象の物事を指す場合に使用します。
「このダンボールを運んでください。」
「ファイルをこのバックに入れます。」
【その】
話し手と聞き手の中間、もしくは聞き手の近くの対象となる物事を指し示す場合。また、既に出た話題や動作などについて指す場合に使用します。
「その方法でやってみましょう。」
「その木を切ってくれませんか?」
【あの】
自分や相手から離れている対象の物事や人物を指し示す場合に使用します。
「あのお店でいいですか?」
「あの車を隣の駐車場へ動かしてください。」
【どの】
特定されていない物事や方法、動作などを相手に尋ねる場合に使用します。
「どの靴がいいですか?」
「どの方法が1番合っていますか?」
対象となる名詞の前に指示連体詞をつけることで、自分と相手の認識を合わせ明確に特定できるようになります。
特に相手に指示を仰ぐ場合は、誤解を防ぐためにも積極的に活用しましょう。
指示代名詞

指示代名詞は「これ、それ、あれ、どれ」など、対象となる物事や概念を指す場合に用いる品詞です。
【これ】
話し手の近くにある対象となる物事について指す場合に使用します。
「これが食べたいです。」
「着るならこれがいいです。」
【それ】
話し手と聞き手の中間、もしくは聞き手の近くにある対象の物事について指す場合に使用します。
「それ、いい靴ですね。」
「私もそれがいいと思います。」
【あれ】
自分と相手から離れている対象の物事や、以前出た話題や状態について指す場合に使用します。
「あれってどうなってますか?」
「あれを持ってきてくれませんか?」
【どれ】
特定されていない物事について相手に尋ねる場合に使用します。
「あなたの服はどれですか?」
「どれなら食べられますか?」
指示代名詞を使用すると、対象となる物事が簡潔に表現できスマートなコミュニケーションを図れます。
指示形容詞

指示形容詞は「こんな、そんな、あんな、どんな」を対象となる名詞の前につけ、物事の性質や状態を表す場合に用いる品詞です。
【こんな】
話し手から近くにある物事の状態や性質、また既に自分が経験した状態について相手に伝える際に使用します。
「こんな風にやってみると上手くできます。」
「こんなに食べられません。」
【そんな】
対象となる物事が聞き手の近くにある場合や、既に相手が経験した状態について知りたい場合に使用します。
「試験はそんなに難しいのですか?」
「そんなに多く持てません。」
【あんな】
自分も相手も経験していない物事や、以前話題に出たことを指す場合に使用します。
「あんなに高い山へ登ってみたいです。」
「なぜあんなことを言ったのですか?」
【どんな】
特定されていない物事や状況、形状などについて相手に尋ねる場合に使用します。
「どんな方法が最適ですか?」
「どんな大きさがいいでしょうか?」
自分の持っているイメージを相手に伝えたい場合は、指示形容詞を使うことで相手に明確に伝わりやすいでしょう。
AI文章作成ツールの使ううえでのポイント3つ
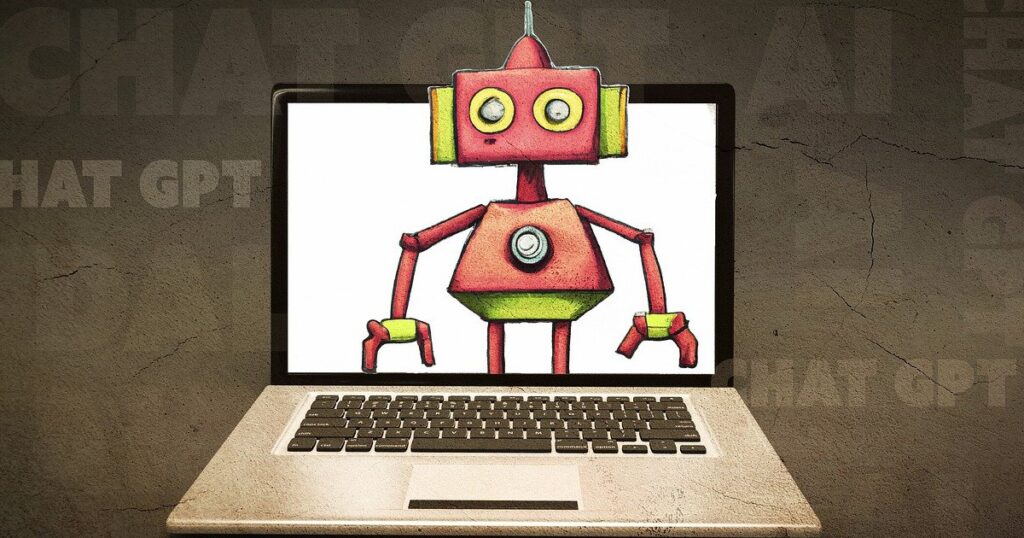
Webライターとして仕事を請け負う上で、AI文章作成ツールの使用経験の有無を事前に確認するクライアントも増えています。
AI文章作成ツールに欲しい文章を作成してもらうためには、指示する側の文章が的確かつ具体的でなければなりません。
特に普段から「こそあど言葉」を使用している人は、AIに指示する際にも使用してしまう可能性が高いです。
「こそあど言葉」は物事や形状、状態などを簡潔に表現できますが、「このぐらいの大きさ」など対面でこそ伝わりやすいが故に曖昧さも目立ちます。
つまり「こそあど言葉」を使った抽象的な指示では、AIが理解できずこちらの意図する文章を作成してくれません。
しかし上手に使いこなすことができれば、複雑な文章もスピーディに作成できるでしょう。
このセクションではAI文章作成ツールを使用する上でのポイントをお伝えしていきます。
【ポイント1】指示文は具体的かつ詳細に
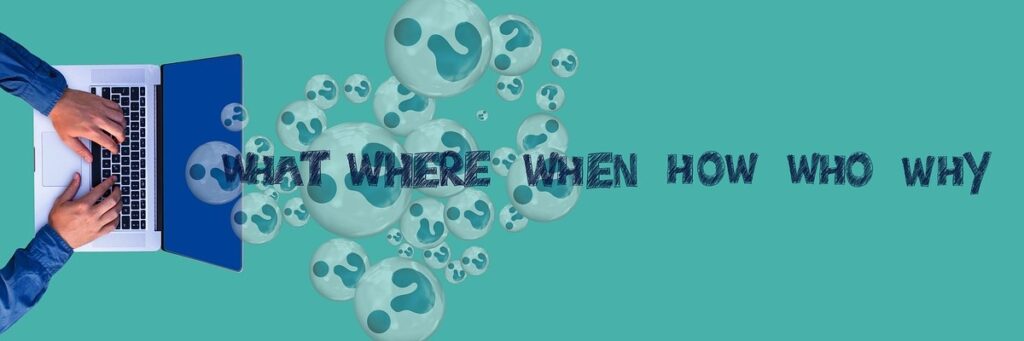
自分が求める回答を得るためには5W1Hや文章構成、文字数を指定するなど細かい指示が重要です。
特にあらゆるビジネスシーンにおいて基本とされている5W1Hを用いて指示することで、AI側も文章作成の目的を理解してくれます。
こちらの意図する文章に近い精度の高さで生成してくれるでしょう。
| When | Where | Who | What | Why | How |
| いつ | どこで | 誰が | なにを | なぜ | どのように |
また、「箇条書きにする」「文字数を指定する」など具体的な指示を伝えることで、大事な要点をまとめた形で生成してくれます。
【ポイント2】指示文は段階を踏む

指示文は段階を踏むことでAIの回答の精度が高まります。
最初はシンプルな指示文から始め、生成された文章で不足している情報があれば必要に応じて追加していくと良いでしょう。
この工程を繰り返すことで指示文の過不足が理解でき、的確な文章を生成してもらうためのプロンプトが出来上がります。
段階を踏むことの重要性が理解できていない場合、初めの2,3回でAIが意図する文章を作成してくれないだけでついつい離脱してしまいがちです。
精度の高い文章生成のためには、段階を踏むことが重要だと覚えておきましょう。
【ポイント3】ツールの特徴を理解し使い分ける

AI文章作成ツールにはさまざまな種類がありますが、効率良く作業を進めるためには用途別にツールを使い分けることが大切です。
以下はAI文章作成ツールを使用することで作業の効率化がはかれるものの例です。
✔ ブログやニュース記事の文章
✔ 議事録
✔ 小説
✔ 商品説明
✔ SNSに掲載する文章
✔ 広告文
✔ 論文
ツールによって特徴や得意分野が異なるため、生成したい文章と相性の良いツールを選ぶことを意識しましょう。
また、ツールにより無料/有料の選択が可能です。
アイデア出しや長い文章の要点をまとめる程度であれば、無料で使用できるツールでも十分活用できます。
より精度の高い文章の生成や校正などを目的とするなら、有料ツールを活用しましょう。

『要注意⚠』こそあど言葉の4つの落とし穴

「こそあど言葉」は文章や指示を明確にするために便利ですが、使い方を間違えたり多用しすぎることで読み手や相手にストレスを与える原因にもなります。
このセクションでは「こそあど言葉」の落とし穴4つについてご紹介していきますので、参考にしてみてください。
対象との距離感を間違える

「こそあど言葉」は指示の対象になるものに対する話し手と聞き手の距離に注意が必要です。
また、文章中に使用する場合は対象の言葉との文脈上の距離に気を付けなければなりません。

上記の画像の場合、「そこの」ではなく「あの/あそこの」と指示したほうがより明確に相手に伝わるでしょう。
「この」は近いもの、「その」は少し離れている距離、もしくはすでに指示した対象のものを指す場合に使用します。
「あの」は遠い距離にあるものを指すときに用いられることが多いです。
とは言え距離の測り方は人により異なるため、特に離れた対象を指し示したいときは対象物の名称を示してしまったほうが早い場合もあります。
乱用しすぎて伝わらない

「こそあど言葉」は乱用しすぎると何が何のことを示しているのかがわからなくなります。
【×】
「今日のランチはオムライスかカレーで迷っています。よく考えればそれはつい最近食べたので、今日はこっちを食べたい気分です。」
結局オムライスとカレーのどちらを食べたんですか?と聞きたくなる内容です。
【〇】
「今日のランチはオムライスかカレーで迷っています。よく考えればそれはつい最近食べたので、今日はカレーを食べたい気分です。」
文章として読者に伝わりやすいのは後者ですよね。
「こそあど言葉」の乱用は読者に誤解を与えやすいため、注意して使用しましょう。
最初の一文で使ってしまう

文章や会話の最初に「こそあど言葉」を使ってしまうと、何のことを示しているのかが相手に伝わりづらくなります。
【×】
「あの話どうなりました?」
上記の例だといつのどの話かがわからず、食い違いが生じる可能性があります。
【〇】
「先日お話したプロジェクトの件、どうなりました?」
少々長くても、お互いに認識の相違が起きないよう対象の物事についてきちんと明確に伝えましょう。
その上で「こそあど言葉」を使用すると、話の食い違いもなく円滑なコミュニケーションが図れます。
Web上の文章なのに多用する

Web上で「こそあど言葉」を多用することのデメリットとして、以下の点があげられます。
・ SEO対策の効果が弱まる
・ 記事の途中から目を通す人に指示語の示す内容が伝わらない
SEO対策として、対象のキーワードが文章中に盛り込まれているほど効果も大きくなります。
対象のキーワードについて「こそあど言葉」を用いて指し示してしまうと、検索エンジン側で対象のキーワードとして判断されなくなるのです。
そのためSEO記事の場合のWeb上の文章では、なるべく「こそあど言葉」の使用を控えるのが賢明でしょう。
またWeb上の記事は書籍などと違い、欲しい情報をかいつまんで読むユーザーが多いです。
記事の途中から読まれることを想定した場合、「こそあど言葉」を使用しすぎると何を示している内容なのかが読者に伝わりにくくなります。
多用を避け、適度に使用することでわかりやすくシンプルな文章が作成できます。
こそあど言葉を使いこなすトレーニング【3選】
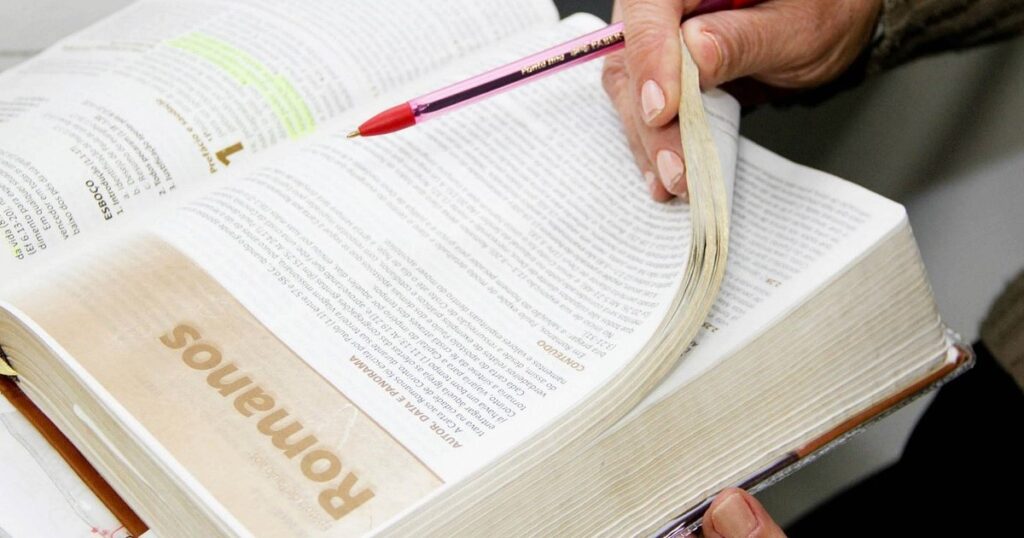
「こそあど言葉」を使いこなすことで、文章の作成が上手くなるだけでなく読解力も向上するでしょう。
このセクションでは「こそあど言葉」を使いこなすためのトレーニングを3つご紹介します。
どのトレーニングも今すぐに実践できるものなので、ぜひ参考にしてみてください。
何を指しているか置き換えながら文章を読む
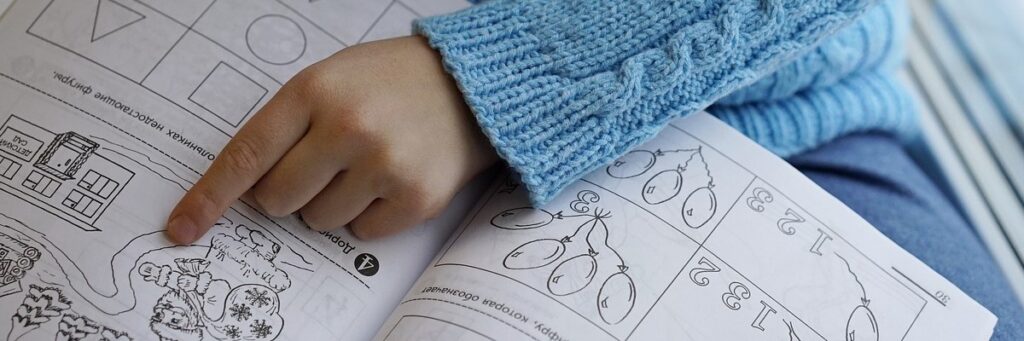
文章を読むときに表れる「こそあど言葉」は、何を指しているのかを常に考えながら読むクセをつけましょう。
慣れないうちは文章を読み返したり読み進めるのに時間がかかるかもしれません。
しかし、慣れてくると「こそあど言葉」と対象の内容が自動的に頭の中で置き換えられるようになります。
読むだけでなく自分で文章を作成するときも意識することで、適度な使い方が身に付くでしょう。
毎日、日記を書く

「こそあど言葉」のトレーニングとして、アウトプットが大切になります。
アウトプットの方法は文章を書くことが1番効果的ですが、「何を書けば良いのかわからない」という人もいるでしょう。
そんな人におすすめなのが、その日あった出来事や行動、思考などを日記として書き出すことです。
日記は文章力や語彙力が高まるだけでなく、ストレスの軽減やポジティブ思考になるなどの効果が期待できます。
自分だけが読むものなので短い文章でかまいません。
書く時の注意点として、文章中に「こそあど言葉」を使用することを意識しましょう。
毎日続けることで「こそあど言葉」を使いこなす力が自然と養えます。
会話の中で意識的に使う

今までは無意識に使っていることのほうが多かったかもしれませんが、反対に意識して使うようにしてみましょう。
意識しながら「こそあど言葉」を使うことで、相手に上手く伝わっているかもわかります。
また、自然と「こそあど言葉」を使う際の距離感が掴めたり、使いこなす感覚を養えます。
初めのうちはぎこちなく感じるかもしれませんが、慣れてくると会話も上達し相手に明確に伝えられる力が身に付くでしょう。
まとめ:こそあど言葉を使っても”わかりやすい文章”を書こう!
「こそあど言葉」は対象の物事や動作、状態などを相手へ伝える(尋ねる)際にとても便利な指示語です。
便利である一方、表現が曖昧になったり抽象的な印象となってしまう側面もあります。
対面している相手に「こそあど言葉」を使って何かを指示したいときは、対象の物事に対しての自分と相手の距離感を誤らないことが大切です。
また、文章に「こそあど言葉」を使用する際も、指し示したい対象の言葉との距離感や文脈、品詞に注意しましょう。
「こそあど言葉」を読んだ時に何について表しているのかがすぐに伝わらなければ、読み手にストレスを与えてしまいます。
誰が読んでも”わかりやすい文章”を書くために、「こそあど言葉」の使い方を理解し適度に使用することを心がけましょう。

「こそあど言葉」に関するよくある質問

このセクションでは「こそあど言葉」に関するよくある質問と回答についてまとめています。
よくある質問①
Q:子どもに「こそあど言葉」を教えるための良い学習方法はありますか?
A:一緒に本を読んでみると良いでしょう。
文中に「こそあど言葉」が出てきたら、「これはどの言葉を表しているのかな?」など、指差しをしながら子ども主体で考えるように読み進めてみてください。
繰り返していくうちに「こそあど言葉」について本人も感覚的に覚えられるようになります。
よくある質問➁
Q:「どうして?」はこそあど言葉になりますか?
A:「どうして」はタイミングや状況により、さまざまな意味合いで使われています。
[副]
1 方法についての疑問を表す。どのようにして。どうやって。「—時間をつぶそうか」2 原因・理由についての疑問を表す。なぜ。「—そんなにのろいのか」「—話を聞かないのだろう」
3 強い否定の気持ちを表す。決して…ない。…はずがない。「これが—黙っていられよう」
4 前の言葉を、予想外であるという意をこめて強く否定する気持ちを表す。それどころか。「見かけは子供っぽいが、—なかなかしっかりしている」
[感]
1 感動をこめて強調する気持ちを表す。なんともはや。いやはや。「—、大層な人出でした」2 強く否定する気持ちを表す。とんでもない。いやいや。「—、—、私などの及ぶところではない」
引用:goo辞書
「1」の方法についての疑問を表す場合に使用する「どうして」は、こそあど言葉の”指示副詞”に該当します。
文章中で判断が必要な場合は、前後の文章から見分けると良いでしょう。
よくある質問③
Q:ビジネスシーンでは、どの程度「こそあど言葉」を使用しても問題ないのでしょうか?
A:ビジネスシーンではわかりやすく、かつ簡潔な文章であることが求められますよね。
「こそあど言葉」は文章をすっきり見せられることに長けていますが、多用することで要件が伝わりにくくなります。
例えばビジネスシーンでのメール文章なら、文中に一つ(長さによっては多くて二つ)ほどの使用が望ましいです。
実際に書いてみて自信が持てなければ、相手方へ送信する前に先輩や上司に確認してもらうのも良いでしょう。