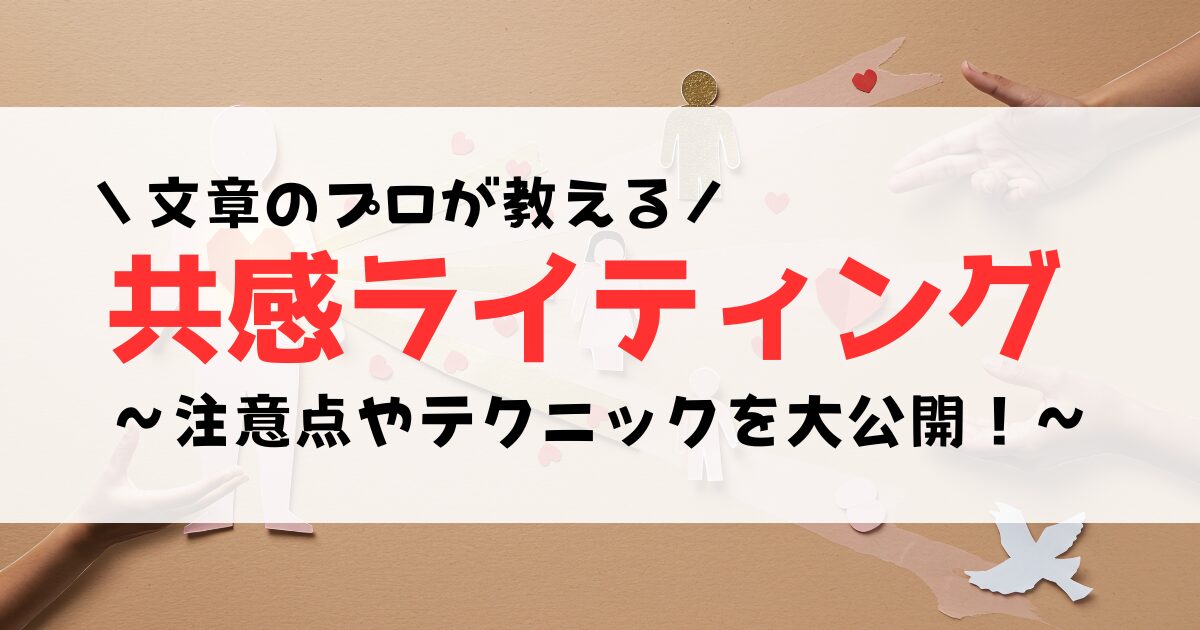読んでいて心が動く文章にあなたは出会ったことがありますか?
思わず「そうそう!」と頷いてしまったり…
「まさに私のこと!」と感じたりする文章です。
そんな文章の魔法、それが「共感ライティング」です。
今、この共感ライティングが一部のライター界隈で注目を集めています。
なぜなら、情報があふれる現代社会において、単なる事実や説明だけでは読者の心に届かなくなってきているからです。
読者の心に寄り添い、共感を呼ぶ文章こそが真の説得力を持つということ。
そこでこの記事では、共感ライティングについてその定義から具体的なテクニック、注意点まで詳しく解説していきます。
あなたのライティングスキルを一段階上のレベルへと引き上げる、そんなヒントが必ず見つかるでしょう。

トレンド到来!?共感ライティングとは?

共感ライティングとは具体的にはどのようなものなのでしょうか。
その定義や使い方、共感ライティングが求められる理由を一つずつみていきましょう。
共感ライティングとは?

共感ライティングとは、読者の感情や経験に寄り添いながら、心に響く文章を書く技術のことを指します。
つまり、単に情報を伝えるだけではなく、読者の立場にたって考え、共感を得られるような表現を用いることが特徴です。
この技術はマーケティング分野で特に重要視されており、身近な例だとSNSやブログなどで幅広く活用されています。
従来の情報提供型の文章との大きな違いは「書き手目線」から「読み手目線」へと視点を転換するという部分。
ある商品の紹介記事を書く場面をイメージした際に、その商品の機能を列挙するのではなく、その商品がどのように読者の生活を豊かにするかを描写する。
それが、共感ライティングということです。
例えば、商品やサービスの紹介記事において、ただ単に特徴や利点を羅列するのではなく、実際にその商品を使った人のストーリーや体験談を交えることで、読者がその文章に共感しやすくなります。
つまり、共感ライティングとは読者の不安やネガティブな感情を先回りして取り除き、共感を通じて良い結果を生むためのライティングスキルといえます。
人は自分のことを理解してくれる人の話に耳を傾けるため、この技術を使うことで相手の行動を促しやすくなるでしょう。
このように、共感ライティングは情報の伝達だけでなく、読者との絆を築くための強力なツールとなります。
共感を呼ぶライティングが求められる理由

共感ライティングがどういったものかイメージは掴めてきましたね。
では、どうして共感ライティングが必要なのでしょうか?
そこで、本セクションでは共感ライティングが求められる理由について説明します。
ライターとして読者の心を掴むためには文章を通じて、いかに相手に寄り添うかがポイント。
日々多くの情報がSNSやブログを通じて流れる中で、読者は自分自身と関連性を感じられるコンテンツを求めています。
つまり、単なる情報提供ではなく感情的な結びつきや信頼関係の構築が必要となってきているのです。
次のセクションからは、なぜ今、共感ライティングが求められているのか詳しくみていきましょう。
受け取る情報量が増えているから

インターネットの普及に伴い、私たちは日々膨大な量の情報に触れています。
そのような情報の洪水の中で読者の注意を引くことは非常に困難です。
読者が多くの選択肢を持つ状況下では、単なる情報提供では関心を引くことができません。
そこで重要になるのが、読者の感情に訴えかける共感ライティング。
感情に訴えることで、読者はその情報を自分事のように感じ取り、記憶に残りやすくなります。
また、共感を得ることで読者との信頼関係を築きやすくなり、結果としてメッセージの効果が向上します。
多くの記事の中から自分の文章を読んでもらい、さらに「また読みたい」と思ってもらうには、単なる情報提供ではなく感情に訴える“共感”が欠かせません。
共感によって読者に「この文章は自分のためにある」と感じてもらうことで、ライターとしての価値も高まるでしょう。
SNSが発達しているから

SNSの発展により情報の伝達速度と拡散力は飛躍的に向上しました。
インターネット上では多くの情報が瞬時に拡散され多くの人々に届けられています。
一方で、情報量が多いことにより読者の注意力が下がっているというのも事実。
このような環境下で読者の注意を引き、共有・拡散される文章を書くためには、感情に訴えかける共感ライティングが非常に有効です。
共感を呼ぶ文章は、読者に強い印象を与えエンゲージメント1を高めることにもつながるでしょう。
例えば、X(旧Twitter)やInstagramでの投稿において、共感を呼ぶストーリーやエピソードを盛り込むことで、読者がその投稿を共有したりコメントを残したりする確率が高まります。
その結果、投稿の拡散力が増し、より多くの人にメッセージが届けられるようになるでしょう。
さらにブランディングの観点からも高い効果を期待できます。
共感を得ることで読者とのコミュニケーションが活発化し、信頼関係を築くことができるためブランドの認知度や好感度も向上します。
1エンゲージメント(engagement)とは、「約束」「契約」「婚約」などを意味する言葉です。ビジネスでは主に従業員の企業に対する「愛着」や「思い入れ」などの意味で使用されます。従業員の企業に対する愛社精神や帰属意識につながる指標とされています。
また、エンゲージメントは企業と従業員の関係だけでなく、企業と顧客の関係を表すことがあります。
この場合は広告などのマーケティング手法による企業と顧客の結びつきの強さを指し、エンゲージメントの向上は売上や利益増加につながるといわれています。
共感ライティングの3つのメリット

次に共感ライティングを用いるメリットについて考えてみましょう。
主なメリットを3つあげます。
自分事として読んでくれる

共感ライティングを用いることで、読者は情報を単なる「他人事」ではなく、自分に直接関係のあることとして受け取るようになります。
例えば、日常の出来事や個人的な体験を交えて書くことで、読者はそれを自分の経験と照らし合わせて考えることができます。
具体的なエピソードや感情の描写を加えることで、読者は筆者の体験を自分のものとして感じ取ることができ、文章に引き込まれていくでしょう。
さらに、共感ライティングは読者の興味を引き続け、途切れさせない効果もあります。
読者は自分自身と関連性のある情報に対してより強い関心を持つため、共感を呼ぶ文章は最後まで読まれる確率が高まります。
このように、共感ライティングは読者の注意を引きつけ、文章の効果を最大化する手法といえるでしょう。
読者に自ら行動したいと思わせることができる

感情に訴えかける文章は、読者の行動を促す力を持っています。
共感ライティングを使うことで、読者は筆者のメッセージを自分事として受け取ります。
その結果として、実際に次の行動を起こす動機付けとなるのです。
感動的なストーリーや具体的な悩みを取り上げることで、読者はその問題に共感し、解決のために自ら行動しようとする意欲が湧いてくるでしょう。
また、共感ライティングは読者に対してポジティブな感情を喚起し、行動を起こすための具体的なステップを示すことが可能です。
例えば、ある商品を紹介する際にその商品を使用したことで、生活がどのように変わったかを具体的に描写します。
そして読者に対して同じような変化を実現するための方法を提案します。
これにより、読者は自ら行動しその商品を試してみようという気持ちになるでしょう。
そして商品購入やサービス申し込みなど、望ましい行動へと導くことができる可能性が高まります。
さらに、読者が「自分の気持ちをわかってくれている」と感じることで、読後の満足度が高まり、他の記事やサービスに興味を持ってもらうことにもつながります。
筆者のことを信頼してくれる

ライターにとって、読者との信頼関係を構築することはすごく難しいことだと考えていませんか?
実は共感ライティングを通せば、“読者に自分の状況や気持ちを理解してくれていると感じてもらう”ことができるのです。
これにより筆者への信頼感が高まります。
つまり共感ライティングは、文章だけでなく筆者自身への信頼も築くことができるということ。
信頼関係ができあがると、筆者の提案や意見がより説得力を持ち、読者が行動を起こす際の指針として受け入れられるようになります。
さらに、共感を得ることで読者は筆者の他の文章やコンテンツにも興味を持ち、長期的なファンとなってくれるかもしれません。
文章を通したコミュニケーションをすることで、筆者と読者との関係がより深まっていくことになるのです。
その結果、価値観が共有できている状態となり、継続的なエンゲージメントが期待できるでしょう。
読者が思わず共感してしまう具体的ライティングテクニック
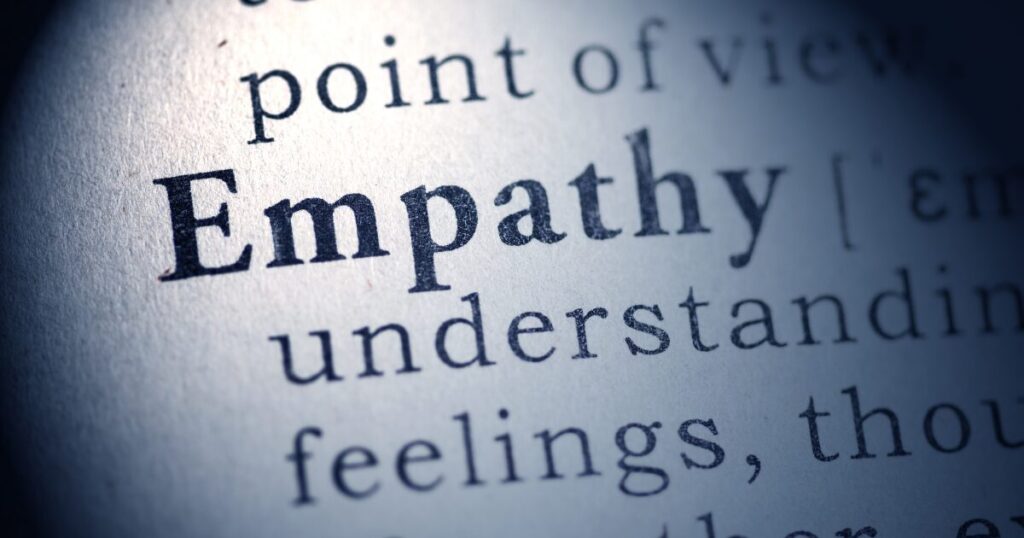
共感ライティングを駆使するためにはどのようなテクニックがあるのでしょうか。
このセクションでは読者が思わず共感してしまうような文章を書く技術をお伝えします。
①ストーリーを使う
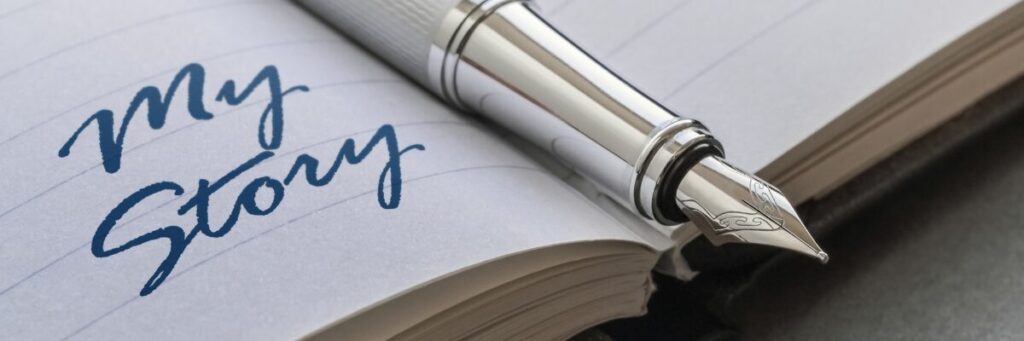
ストーリーを使って表現することは、読者の心に深く刺さる強力な手法です。
個人的な経験や感動的なエピソードを共有することで、読者は筆者の体験を自分のことのように感じ取ることができます。
仕事が忙しく毎日のように終電で帰宅する日々。そんな中、健康診断で高コレステロールと診断され、ショックを受けました。
「これじゃダメだ」と思い、生活習慣を見直すことを決意。
朝早く起きてジョギングを始め、食事もバランスよく摂るように心がけました。
初めは辛かったけど、3ヶ月後には体重も減りコレステロールも正常範囲に。
職場の同僚からも「最近元気そうだね」と言われ、自分自身も健康を実感できています。
人は物語に引き込まれやすい性質があります。
あなたの経験や他の人の体験談をストーリー形式で語ることで、読者の共感を得やすくなります。
起承転結を意識し、読者が自然に物語に入り込めるような展開を心がけましょう。
②具体的に描写する
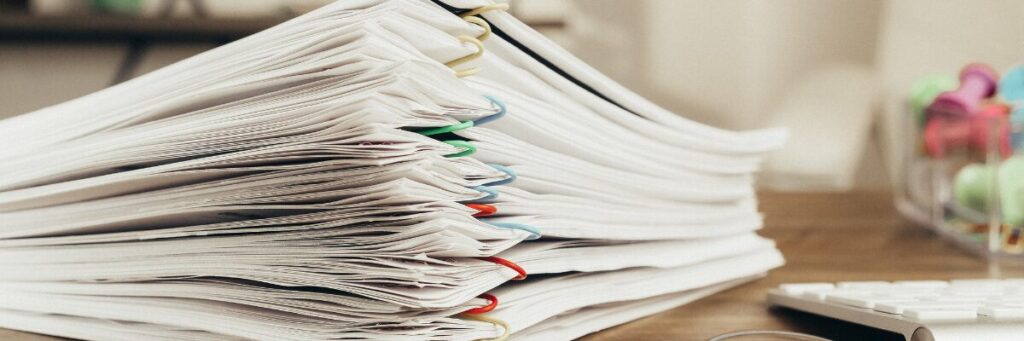
具体的な描写は読者にリアルなイメージを与え、感情移入を促します。
抽象的な表現よりも、具体的な状況や感情を詳細に描写することで、読者はそのシーンを自分のこととして捉えることができます。
長時間の会議でヘトヘトに疲れているのに、今日中に終わらせないといけないタスクがあって困っている。
デスクには未処理の書類が山積みで、全然片付いていないのに時計の針はどんどん進んでいく。
焦りと疲れで頭が重く、肩はパンパンに張っている。
そんな時、ふと窓の外を見て深呼吸をした。そうしたら、、
抽象的な説明よりも具体的な例やエピソードの方が読者の記憶に残りやすいもの。
具体例を使って読者の想像力を刺激し共感を呼び起こしましょう。
③読者の立場になって質問を投げかける
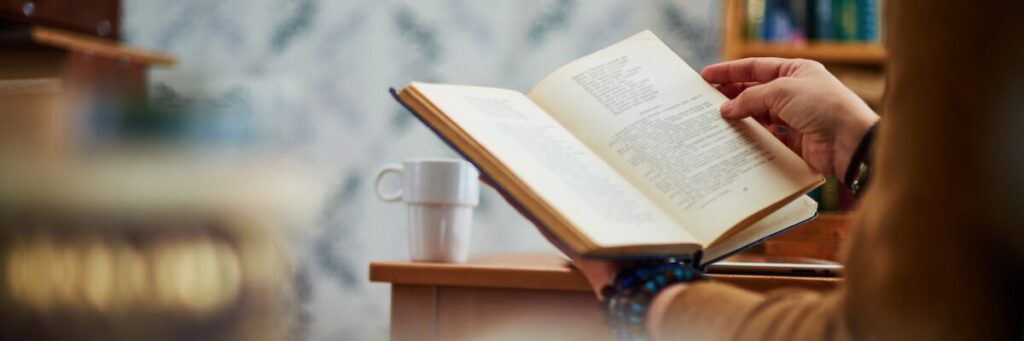
読者の疑問や不安を先回りして問いかけることで、共感を得ることができます。
「こんなことで悩んでいませんか?」といった質問は、読者に自分の問題を意識させ、共感を呼び起こします。
こんなことで悩んでいませんか?
毎日の業務に追われて自分の時間が全く取れない。
大事な家族との時間も減ってしまい、ストレスだけが溜まるばかり。
どうにか解決したいけど、何から手をつけていいのかわからない…。
読者が抱くネガティブな感情を理解し、不安や疑問を先に取り上げ、それに共感することで信頼を得ます。
読者の気持ちに寄り添い、「その気持ち、よくわかります」と伝えることで、自分の気持ちが理解されていると感じるようになります。
そして、投げかけた質問に対して解決策を提示することも大切。
例えば、読者の不安を解消する具体的な解決策や商品のメリットを提示することでより効果的に文章の内容を伝えることができるでしょう。
④五感を刺激するワードを使う

五感を刺激する言葉は、読者に感覚的な体験を提供し共感を深める効果があります。
視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚に訴える表現を使うことで、文章がよりリアルに感じられます。
コーヒーの香りが漂うカフェにはゆったりと静かな音楽が流れている。
心地よいソファに沈み込みながら、窓の外をしとしと降る雨音が聞こえてくる。
手に触れるカップの温もりが、疲れた心をほぐしてくれるようだ。
事実だけでなく感情を表現する言葉を意識的に使いましょう。
「嬉しい」「悲しい」「驚いた」といった気持ちを表す言葉や五感を刺激する表現を取り入れることで、読者の感情を揺さぶることができます。
五感に訴えかける表現をもっと学びたい方はこちらの記事がオススメです。

共感ライティングで陥りがちな落とし穴

共感ライティングを効果的に活用するためには注意すべきポイントもあります。
共感を得ることばかりにこだわり、落とし穴にハマらないように気をつけましょう。
感情の押しつけは逆効果

共感ライティングの目的は読者の感情に訴えかけることですが、過度に感情を押しつけると逆効果になることがあります。
読者は筆者の感情に共感できない場合、むしろ反発心を持ってしまうことがあるため、押しつけがましい表現は避けましょう。
感情を共有することは重要ですが、読者が自分の感情を持つ余地を残すことが大切です。
例えば、
「私はこの映画を見て涙が止まりませんでした!あなたも同じように感じるはずです。」
という表現では、読者が自分の感情を持つ余地を奪うため、共感を得にくくなります。
代わりに、
「この映画では誰もが経験したことのある家族との絆や成長の物語が描かれています。
自分の人生を振り返るきっかけになるかもしれません。」
といったように、読者に感情を押しつけずに自身で感じ取る余地を与える表現を心がけましょう。
自己開示ばかりしない

共感を呼ぶためには自己開示が有効ですが、自己開示が長すぎると読者の関心を失う可能性があります。
相手の話ばかりが続くと次第に興味を失ってくるようなことはありませんか?
読者も同じです。
興味を失うとその先の文章を読んでもらえなくなってしまうでしょう。
また、自己開示の長さだけではなくその内容にも注意が必要です。
例えば、
「私は子供の頃、両親の離婚で深く傷つきました。今でも人間関係に不安を感じ、毎晩眠れません。」
という深刻な自己開示は、読者にとって重すぎる場合があります。
代わりに、
「人間関係で悩んだ経験は誰にでもあるでしょう。私も以前は人付き合いに不安を感じることがありました。
しかし、少しずつ自分と向き合うことで、関係性を築く自信が持てるようになりました。」
といったように、読者が共感しやすい範囲に留めることが大切です。
自己開示をする際は、読者が自分の経験や感情とリンクさせやすい内容に絞り、長々と続けないように注意しましょう。
自己開示はバランスが重要!
読者が共感できる範囲で行うのがポイントです。
誇張しすぎない

共感を得るためには、正直で誠実な表現が重要です。
誇大表現は読者に不信感を与えることがあるため、過度な誇張は禁物。
共感ライティングではリアリティを重視して、読者が現実的に受け入れられる表現を使いましょう。
例えば、
「このダイエット法を使えば、たった1週間で10kg痩せることができます。
しかも、リバウンドの心配は一切ありません!」
という過度な誇張表現ではなく、
代わりに、
「このダイエット法を継続的に実践することで、健康的に体重を減らすことができます。
個人差はありますが、多くの方が1ヶ月で3~5kgの減量に成功しています。」
といったように現実的な表現を使うことで、読者の信頼を得ることができます。
嘘のない正直で誠実な表現を心がけ、読者に対して誇張せずに真実を伝えることが重要です。
これにより読者との信頼関係ができあがり、長期的なエンゲージメントを生むことができるでしょう。
読者が思わず共感してしまう具体的ライティングテクニック
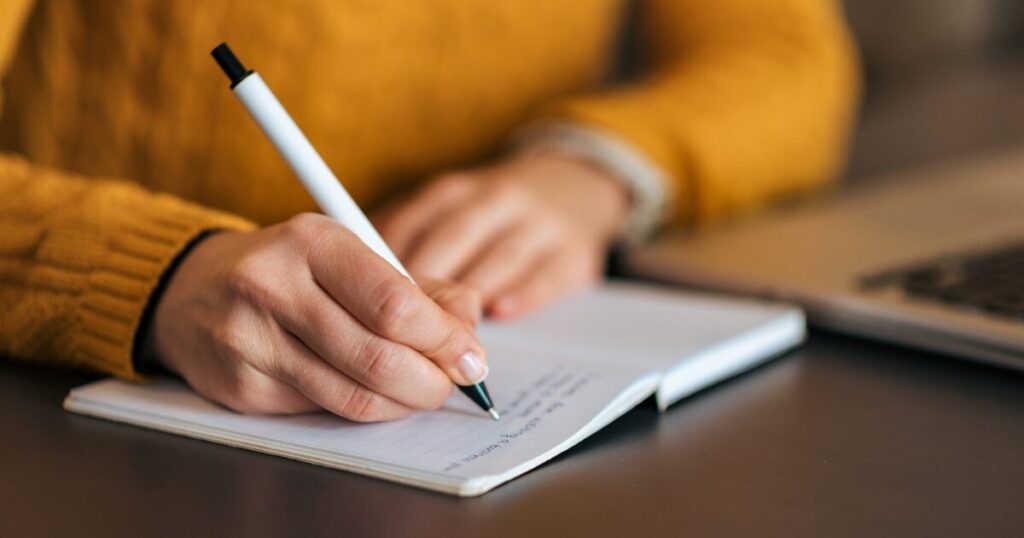
実際に筆者は共感ライティングを知ってすぐに取り入れました。
しかし、はじめのうちは「共感してもらおう」と意識しすぎて、不自然な文章になってしまうこともありました。
読者の注意を引きつけることはできても、その先の行動を促すことができていなかったのです。
そこで次の工夫を取り入れるようにしました。
- 行動心理学 の考え方を学ぶ
- マーケティング要素 を組み合わせる
- データやエビデンス を活用して信頼性を高める
心理学を学んだことで、共感ライティングの本質が理解できるようになり、お客様や読者の悩みや不安に寄り添う文章が書けるようになりました。
また、具体的なエビデンスやデータを示すことで、文章全体の説得力も向上。
結果として、読者の行動を促す力が格段にアップしました。
そんなスキルを体系的に学べるのが、コピーライター養成オンラインスクール【Online ApC Academy】の無料トライアルです。
このスクールでは、行動心理学を駆使したライティング技術を学ぶことができ、さらにマーケティングの要素もあわせて習得できます。
つまり、コピーライティングのスキルを磨きながら、読者の行動を促すテクニックを身につけることができるのです。
私自身、ApCで学んだことで文章力が格段に向上しました。
セミナーやプロの講師による具体的な指導と実践的な課題に取り組むことで、ビジネスの成果も上がっています。
今では、自信を持って共感ライティングを実践できるようになり、読者の心を掴む文章を書くことができるようになったと自負しています。
あなたも、この機会に【Online ApC Academy】の無料トライアルを試してみませんか?
共感ライティングのスキルを高め、読者の心を動かす文章を書けるようになれるはずです。
行動心理学とマーケティングの融合によるライティング技術を学び、あなたの文章力を次のレベルに引き上げましょう。

まとめ:共感ライティングを活用して読者にさらなる価値を提供しよう!

ここまでみてきたように共感ライティングは、単なる文章技術を超えて、読者の心に響く強力なツールになります。
この記事を通じて、共感ライティングの基本から具体的なテクニック、注意点についてご理解いただけたでしょう。
共感ライティングを身につけることは、単なるスキルの向上だけではありません。
より深く自分の内面に向き合い、読者とのつながりを感じながら書く力を育むことができます。
その結果、書き手と読み手双方にとって豊かな体験となるはずです。
ライターが共感を引き出すスキルを身につけて高品質な記事を書くことで、読者にとっても価値のある体験を提供できるようになります。
ライターの成長は、そのまま読者に伝わる内容の質にも反映され、最終的には全ての読者がその恩恵を受けるという、素晴らしい循環が生まれるでしょう。
読者は共感できる文章を読むことで、自身の問題を解決したり、新しい視点を持ったりすることにつながります。
結果として読者は満足感や感動を得て、彼らの人生がより豊かになっていくということになるのです。
共感ライティングを上手に活用して読者へさらなる価値を提供していきましょう!
よくある質問
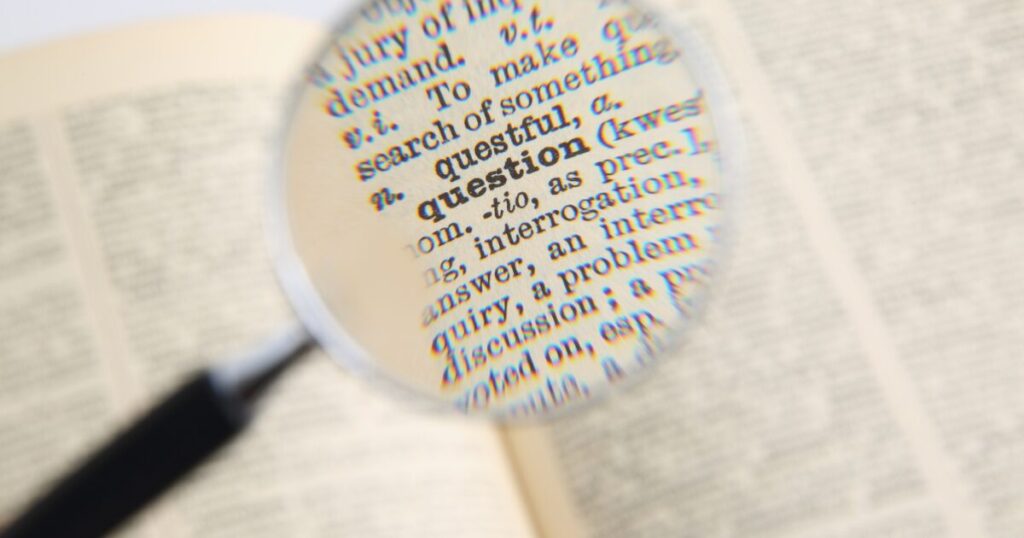
最後に、共感ライティングについてよくある質問をまとめました。
ぜひ参考にしてみてください。
よくある質問①共感の強い文章を書くにはどうしたらいいですか?
共感の強い文章を書くためには、まず読者の立場にたって考え彼らの悩みや不安に寄り添うことが重要です。
具体的なストーリーやエピソードを交え、五感に訴える表現を使うことで、読者にリアルな体験を感じさせることができます。
例えば、自分が実際に経験した困難や成功体験を詳細に描写することで、読者はその体験を自分のことのように感じ取ることができます。
また、誠実で正直な表現を心がけ、過度な誇張や自己開示を避けることも大切です。
これにより読者との信頼関係を築き、深い共感を得ることができます。
よくある質問②なぜ共感ライティングが重要なのですか?
情報が溢れる現代において、読者の注意を引くためには感情に訴えかけることが重要です。
共感ライティングを使うことで、読者の関心を引きつけ信頼を築くことができます。
例えば、単なる事実やデータだけでなく、読者の心に響くストーリーや感情的なエピソードを盛り込むことで、情報がより記憶に残りやすくなります。
さらに、共感ライティングは読者との長期的な関係を築くための強力なツールであり、読者が再び訪れたくなるような価値のあるコンテンツを提供することが可能です。
よくある質問③共感ライティングの具体的なテクニックを教えてください。
共感ライティングにはいくつかの具体的なテクニックがあります。
代表的なものを4つ紹介します。
- ストーリーで伝える
物語の形で書くことで、読者が感情移入しやすくなる - 具体的に描写する
状況や感情をリアルに描くことで、読者にリアルなイメージを与えられる - 読者の立場で問いかける
読者の不安や疑問を先回りして質問を投げかけると、共感が生まれやすくなる - 五感に訴える表現を使う
五感を刺激する言葉を使うことで、読者の感覚を通じて深い共感を呼び起こすことができる
よくある質問④共感ライティングで注意すべきことは何ですか?
共感ライティングで注意すべきこととして、感情の押しつけ・過度な自己開示・誇張しすぎる表現の3つがあります。
- 感情の押しつけ…感情を押しつけると読者が反発することがあるため、読者自身の感情を持つ余地を残すことが重要。
- 過度な自己開示…自己開示はバランスが重要で、過度になると読者の関心を失うことがある
- 誇張しすぎる表現…誇張しすぎる表現は信頼を損なう原因となるため、正直で誠実な表現を心がける
よくある質問⑤共感ライティングのスキルを磨くためにはどうすればいいですか?
共感ライティングのスキルを磨くためには実践的なライティングを継続し、フィードバックを受けることが重要です。
また専門的な講座やトレーニングを受けることで、スキルを体系的に学ぶことができます。
例えば、コピーライター養成オンラインスクール【Online ApC Academy】の無料トライアルでは、行動心理学とマーケティングを駆使したライティング技術を学ぶことができ、読者の行動を促す具体的なテクニックを身につけることができます。
プロの講師による指導や実践的な課題を通じて、自身のライティングスキルを向上させることができるのです。
さらに、他のライターや講師からのフィードバックを受けることで、自分の文章の改善点を見つけ効果的なライティングを実践することができます。