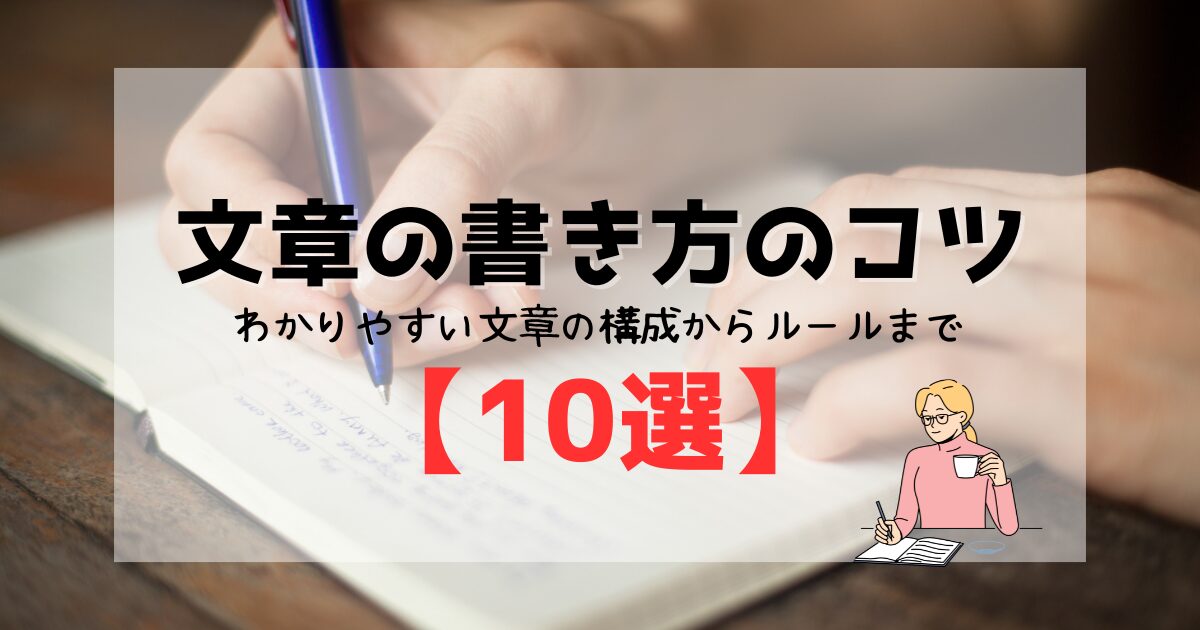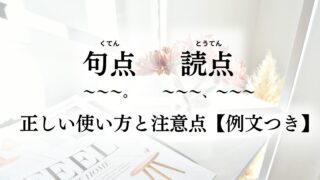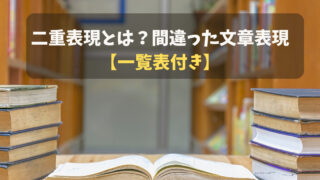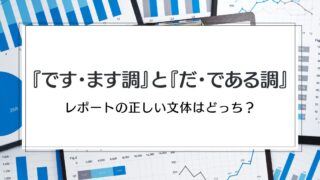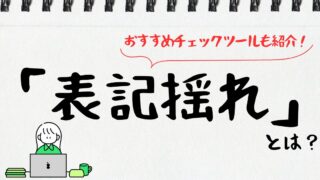あなたは「読まれる文章を書きたいけど、どうしたらいいのかわからない」と悩んでいませんか?
ブログや日記とは違い、SEO記事は自分の好きなように書くだけでは読者の心に響きません。
今回の記事ではわかりやすい文章や読まれるためのコツを10個の例を挙げながら解説しています。
人を惹きつけるためのテクニックや、文章が劇的に変わるためのポイントを解説しました。
ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

わかりやすい文章の書き方【10選】例文つき
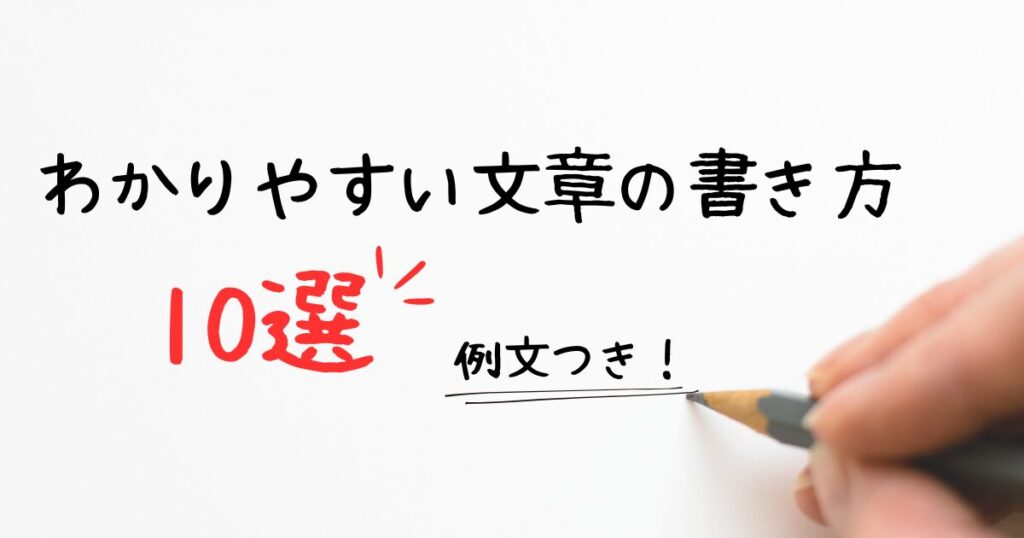
多くの人に読んでもらう文章を書くには、ただ情報を並べるだけでは不十分です。
読者の興味を引きつけ、最後まで読ませるための工夫が必要。
では、どんなポイントに注意すべきでしょうか?
1つずつ見ていきましょう。
①一文は短く書く意識を持つ
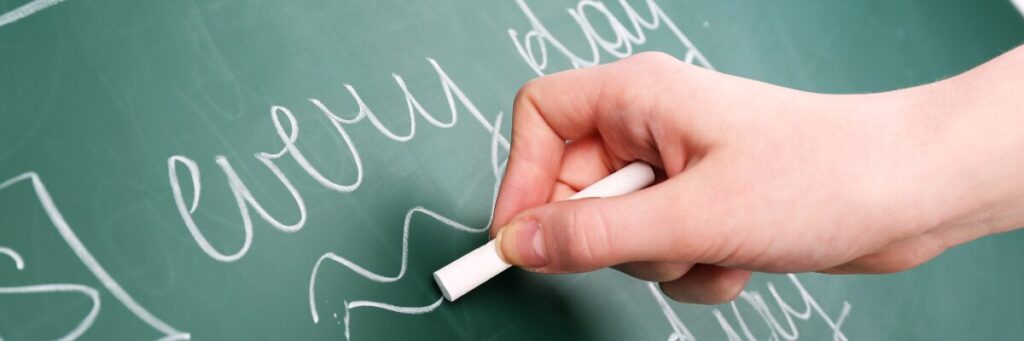
相手に言葉を伝えるときは一文を短くし、端的に伝えましょう。
一文が長くなると、主語と述語の関係が曖昧になり、情報量が増えて読み手を混乱させます。
短い文章で書くことで、読み手は正確な情報を手に入れられます。
先日、当社の最新製品の発表会が開催され、多くのメディア関係者や業界の専門家が参加し、その場で製品の革新的な機能や将来性が詳細に紹介されただけでなく、参加者からの活発な質疑応答も行われ、成功裏に終了しました。
先日、当社の最新製品の発表会が開催されました。多くのメディア関係者や業界専門家にご参加いただき、製品の革新的な機能や将来性をご紹介いたしました。活発な質疑応答も行われ、発表会は成功裏に終了しました。
このように、良い例の文章は一文がすっきりとしており、主語述語が明確です。
一方悪い例は文の区切りが一切なく、何を伝えたいのかが不明瞭です。
その結果、読み手は文章の意図を理解できず、離脱につながりやすくなります。
②結論ファーストで書く

結論ファーストは、読み手が内容をいち早く理解するために非常に効果的な文章術です。
最初に伝えたいことを書くことで、読み手は要点を瞬時に把握できます。
逆に、要点が見えないまま文章が続くとどうなるでしょうか。
「結局、何が言いたいの?」と疑問やストレスがたまり、読者は途中で読むのをやめてしまいます。
一度離脱されてしまうと、せっかく一生懸命書いた記事も読まれません。
つまり、伝えたいことが届かないまま終わってしまうのです。
最後まで離脱されないためにも、結論を明確化した文章を書くよう心掛けましょう。
③曖昧な表現をなくす

曖昧な表現を避けることは、読み手の誤解や混乱を防ぎ、信頼性の高い文章を作成するために非常に重要です。
曖昧な表現としてよく使われるものには、以下のような言葉があります。
- 〜かもしれません
- 〜と思います
- かなり〜
一見やわらかい表現にも見えますが、このような曖昧な表現は読み手に不安を与えます。
「え? かもしれないってどういうこと?」
「かなりってどのくらい?」
このように、正確さや具体性が欠けていると読者は疑問を感じるため、他の記事を探したり、辞書で調べたりと余計な行動を取らざるを得ません。
その結果、せっかく一生懸命書いた記事も最後まで読まれず、離脱につながってしまうのです。
では、どうすれば読者に安心して読み進めてもらえるのでしょうか。
曖昧な表現をなくすために大切なのは、言い切ることです。
例えば、
「〜かもしれない」→「〜と判断されます」
「かなり増えました」→「前年比50パーセントです」
このように断定や具体的な数字を示すことで、読者は安心して情報を受け取れます。
曖昧表現をなくすことこそが、読まれる文章への第一歩です。
④語尾を連続させない

文章を書くときは、語尾が同じ形(です・ます・である など)で3回以上続かないように気をつけましょう。
同じ語尾が続くと、文章全体が単調に感じられてしまいます。
昨日は友達と、ランチを食べに行きました。今回はいつも行くお店ではなく、新しくできたイタリアンのお店に行きました。私はパスタを食べて、友達はピザを食べました。食べながら、いろんな話をしました。とても美味しく食べました。帰り際に、また行こうと約束しました。
いかがでしょうか?
同じ語尾が連続しているため、間延びした印象を与えます。強弱や抑揚もないため、読み手が退屈に感じてしまう恐れがあります。
では、語尾を変化させながら、もう一度見ていきましょう。
昨日は友達と、ランチを食べに行きました。今回はいつも行くお店ではなく、新しくできたイタリアンのお店に行くことに。メニューはどれも美味しそうでとても悩みましたが、私はパスタ、友達はピザを食べました。パスタの麺がモチモチで、とても美味しかったです。帰り際「また行こうね」と約束しました。
修正前と修正後の文章を比べてみてください。
語尾を変えるだけで文章の印象がグッと変わったのがわかります。
同じ語尾が連続しないコツは、文章を書き終えたら声に出して読んでみることです。
声に出して読むことで、目で読むだけでは気づきにくい単調さや違和感に気づけるようになります。
⑤接続詞を適切に使う

接続詞を適切に使うと、文章の流れがスムーズになります。
接続詞は情報の流れを明確化するうえで、必要不可欠です。
上手に使うことで、読者も自然とストレスなく最後まで読めるでしょう。
接続詞の種類を例文と一緒に見ていきましょう。
例:しかし・ところが・それなのに
使用例:朝は雲一つない青空が広がっていた。しかし、昼から急に雨が降り出した。
例:そのため・したがって・よって
使用例:私は数学が苦手です。そのため、毎日30分勉強を続けました。
例:一方・あるいは・これに対して
使用例:A町のスーパーは白菜が150円です。一方、B町のスーパーは100円で買えます。
例:さらに・加えて・しかも・また
使用例:テレビが定価より20パーセント引きになっています。さらに、今ならおまけで箱ティッシュがついてきます。
文章を自然につなげる大切な役割を持つ接続詞ですが、使い過ぎには注意しましょう。
多用することによって、文章がかえって読みづらくなることも。
適切に使い分けながら、読みやすい文章を心がけてください。
⑥句読点を適切に使う
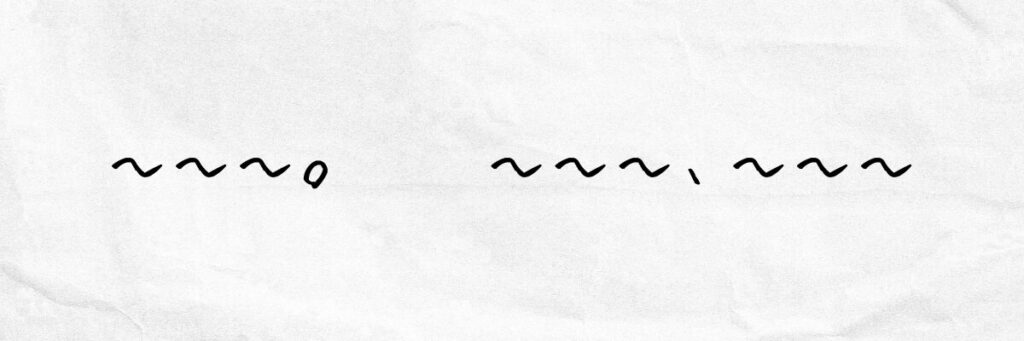
句読点は、文章のリズムを作るうえでとても重要です。
主な役割は、息継ぎと区切り。歌でいうと、ブレスです。
読者に「読みやすい」と感じてもらう文章にするためには、句読点の使い方が重要です。
ここでは、例文を用いてその効果を見ていきましょう。
【例文】
昨日私は買い物に行き洋服と靴と化粧品と鞄を購入しました欲しいものが手に入りとても嬉しかったです買い物から帰る途中で偶然友達と会ったのでカフェでお茶をしました
読み手からすると「なんのこっちゃ…」となるでしょう。買い物に行ったことはわかるものの、情報が大渋滞しており全く頭に入ってこない残念な文章です。
では、改善した文章はどうでしょうか?
【例文(改善版)】
昨日私は買い物に行き、洋服・靴・化粧品・鞄を購入しました。欲しいものが手に入り、とても嬉しかったです。買い物から帰る途中で、偶然友達と会ったのでカフェでお茶をしました。
「買い物に行った」「洋服・靴・化粧品・鞄を購入した」「帰りは友人とカフェに行った」という事実が漏れることなく伝わってきます。
ただし、むやみやたらに句読点を打たないようにすることが大切です。
読みやすさを意識して、句読点を適切に打ちましょう。
もっと詳しいコツが知りたい方はこちらの記事もチェックしてみてください。
⑦二重表現をなくす

二重表現とは、同じ意味の言葉が連続で続くことを指します。
これにより文章が冗長になり、読み手に読みにくさを感じさせます。
二重表現について、例文を挙げて解説します。
この件は、彼女にすべて一任します。→ この件は、彼女に一任します。
「一任」という言葉には「物ごとを全て任される」という意味があります。
そのため「すべて」という言葉をつけることで重複した表現になってしまいます。
一番最初に到着したのは私です。→ 最初に到着したのは私です。
「最初」という言葉は「一番」という意味です。すなわち「一番最初」と書くと、二重表現に該当します。
このように、不要な重複表現を取ることで簡潔に状況を伝えられる文章となります。
二重表現はスラスラと読みたい読み手の妨げとなるため、特に注意しましょう。
「でもどうすれば二重表現に気づけるの?」
答えはシンプル。自らの語彙力を鍛えることが一番の対策です。
言葉の引き出しを増やすことで、二重表現に気づきやすくなります。
こちらの記事ではよくある二重表現を紹介しています。
言葉の引き出しを増やす第一歩としてチェックしてみるのがオススメです。
⑧漢字・ひらがな・カタカナのバランスを調整する
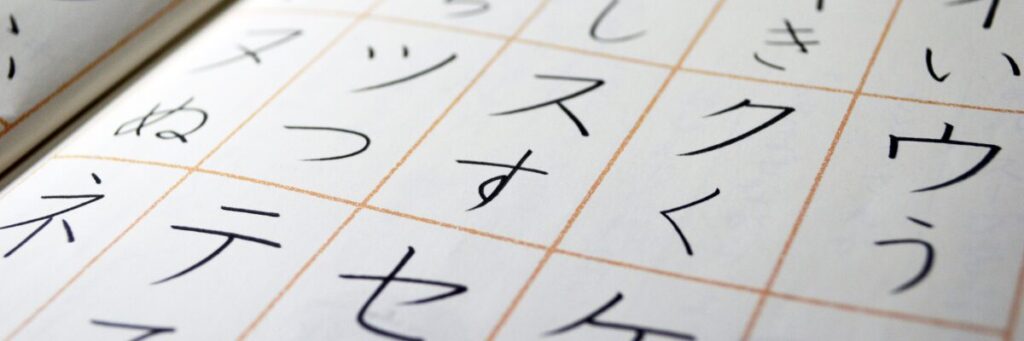
漢字・ひらがな・カタカナを適切に使い分けると、バランスの良い文章になります。
どれかに偏ったバランスの悪い文章は読みにくく、ストレスを感じる原因になるでしょう。
具体的な例文で確認してみましょう。
温暖化問題解決に貢献し、持続可能な社会実現に繋がる重要行動です。
市民一人ひとりの意識向上、日常的実践が不可欠であり、今後益々その重要性は増大するでしょう。
全体的に堅苦しい印象を与えるうえに「日常的実践」という言葉は普段なかなか使いませんよね。
この文章では読む気をなくしてしまいます。
では、カタカナに偏った文章だとどうでしょう。
温暖化のソリューションに貢献し、サステナブルな社会実現へとつながる大切なポイントです。
市民一人ひとりのマインドアップとデイリーアクションがマストであり、これから先ますますその重要性はアップしていくでしょう。
横文字に慣れてない読み手にとっては「え?ソリューション?マインドアップとデイリーアクション?どういう意味だろう」と疑問の連続になりかねません。
ひらがなに偏った文章も見ていきます。
おんだんかもんだいかいけつにこうけんし、持続可能なしゃかい実現につながるたいせつなぽいんとです。市民ひとりひとりの意識こうじょう、にちじょうてき実践が不可欠であり、こんごますますその重要性はあっぷしていくでしょう。
いかがでしょうか?
文章に違和感こそないものの、ひらがなが多すぎて読みたいとは思いませんよね。
漢字・ひらがな・カタカナのバランスは「2:7:1」がベストと言われています。
では、先程の例文をバランス良く整えてみましょう。
温暖化の問題を解決し、サステナブルな社会の実現につながる大切なポイントです。
市民一人ひとりが意識を高め、日常のアクションを積み重ねることが不可欠であり、これから先ますますその重要性は大きくなるでしょう。
バランスが良く、スムーズに読める文章に変わりました。
専門的なカタカナ用語や難しい言葉を多用するのではなく、誰もがすんなり理解できる言葉を選ぶことが大切です。
⑨冗長的な表現を削る

冗長的な表現は、文章をスムーズに読みたいときの妨げになります。
文章の中に無駄な表現が多いと、要点がわかりにくくなるからです。
また文章に対してプロフェッショナルな印象が薄れるのも冗長表現のデメリットの一つ。
以下の例文を見ていきましょう。
例文:本日は、休講という形になります。
修正後:本日は休講です。
例文:このファイルをを使えば、すべて管理することができます。
修正後:このファイルを使えば、すべて管理できます。
冗長表現を削ることで、文章は簡潔になり、書き手の意図も明確に伝わります。
執筆時は冗長な言い回しが紛れ込んでいないかを見直し、少しでも違和感を覚えた表現は他の語に置き換えましょう。
⑩読み手の気持ちを考える
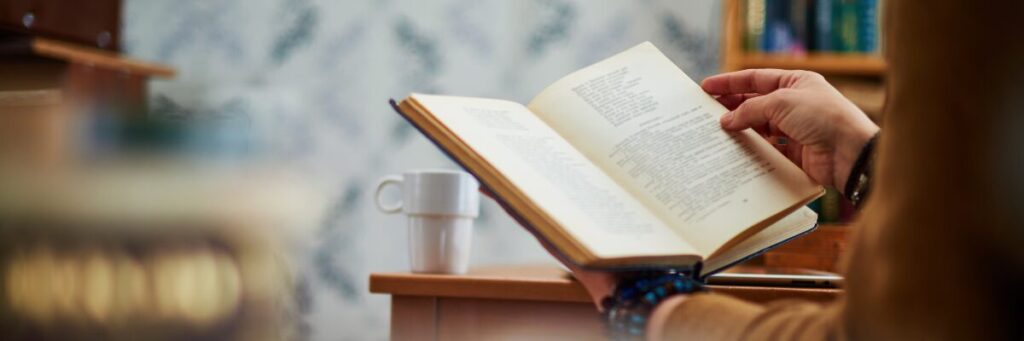
不特定多数の人が読む記事は、読み手が何を知りたくてこの記事に辿りついたかを考える必要があります。
個人的なブログや日記であれば、自分の好きなように書いても問題ありません。
しかし、SEO記事など多くの人の目に入る記事の場合は、執筆するときの矢印を自分ではなく、相手に向けましょう。
検索上位の記事を熟読し、検索意図(なぜこのキーワードで検索したか)を理解することが大切です。
特定のキーワードで検索する人は、必ず検索目的を持っています。
例えば、検索キーワードを「夏 旅行」と設定したケースで考えてみましょう。
このキーワードに関連して「夏 旅行 カップル」「夏 旅行 おすすめ 涼しい」「夏休み 旅行 子連れ おすすめ」といった関連キーワードが出てきます。
これらの関連キーワードは、読み手の検索意図を反映しています。
つまり、多くの人が「カップルで行ける旅行先」や「家族・子ども連れで楽しめるスポット」「涼しい場所での旅行情報」を求めているということです。
記事を作成するときは自分の書きたい言葉や入れたいワードを、闇雲に使うだけでは読んでもらえません。
読者がどんな情報を探しているのかを理解し、そのニーズに応えることがもっとも重要です。
わかりやすい文章を書くうえでの注意点

せっかく書いた文章も、読み手に「意図がわからない文章だなあ…」と思われては意味がないですよね。
では、なぜ読む気をなくしてしまうのでしょうか?
ここではやってしまいがちな例と、わかりやすい文章を書くうえでの注意点や改善点をお伝えします。
「ですます調」と「だである調」を混合させない

文章の中に「ですます調」と「である調」を混合させないように気をつけましょう。
語尾が統一されていない文章は読みにくく、かつ違和感として読み手に伝わります。
以下の例文を見てください。
今日は前から楽しみにしていた、旅行の日です。高校の友人5人で行く旅行だ。このメンバーでの旅行は初めてなので、とても楽しみだ。きっと楽しい思い出になるでしょう。
語尾が統一されていないだけで、ターゲット層がわからない記事になりました。
基本的にWebコンテンツは「ですます調」で書かれていることが多いです。
一方「である調」は少々堅苦しい印象を与えます。
論文や研究発表、新聞記事などで使われることが多いでしょう。
混合させないためには、まず「誰に向けた記事なのか」をはっきり決めましょう。
不特定多数の読者に向ける場合は「ですます調」、社内での報告書など形式的な文章では「である調 」を使うなど、場面に応じて使い分けることが大切です。
専門用語を使う際は読み手を置いてけぼりにしない

特定の分野の知識がない人にとって、専門用語だらけの文章は理解できません。
Webライターが使う専門用語を例に解説します。
このようなWebライターでなければ、なじみのない言葉が多いと読者は読むのをやめてしまいます。
もし文章の中で専門用語を使うときは、注釈を入れて誰が読んでも意味がわかるようにしてください。
記事を書くときは知見がある人、初めてその言葉に触れた人、いろんな状況の人が読むことを頭にいれておきましょう。
表記揺れを起こさない

表記揺れとは、同じ意味を持つ単語が文章の中で表記が変わることです。
表記がばらつくと、主語や対象が誰なのか分かりにくくなり、文脈の理解を妨げる原因になります。
ここで表記揺れの例を、1つ挙げてみます。
当社は、AIを活用した新しいアプリを開発中です。特に、人工知能による画像認識技術が重要な役割を果たします。
いかがでしょうか?
「え?AIと人工知能って同じ意味だよね?それとも違うのかな…よくわからないからもういいや。」
このように、表記揺れにより混乱を招いてしまうとそのままページを閉じられる可能性もあります。
表記は文章の中で統一させ、読み手を混乱させないよう注意してください。
表記揺れに関してもっと知りたい方は、下記の記事がオススメです。
伝わる文章を書くための実践的なコツ

読み手に伝わる文章を書くのは、読み手に行動を促すための重要なスキルです。
このセクションでは、わかりやすい文章を書くためのコツをご紹介します。
しっかりとポイントを抑えて、満足度の高い記事を書けるようになりましょう。
書き始める前に構成を練る
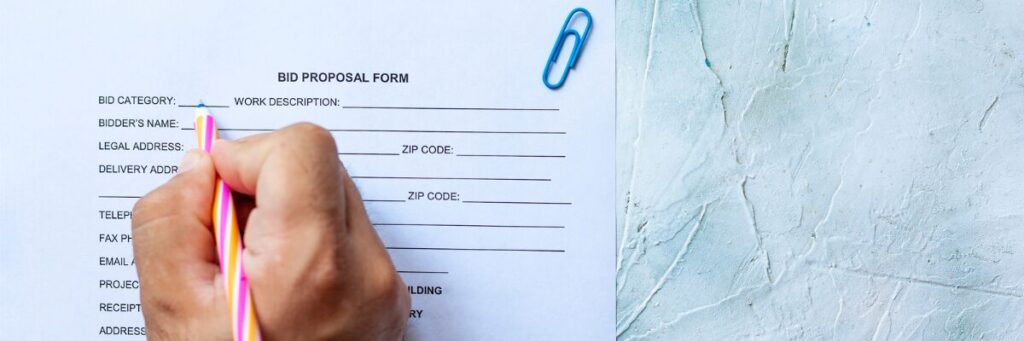
文章を書くうえで、構成は重要な役割を持っています。
構成の出来次第で、“文章が読まれるか読まれないかが決まる”と言っても過言ではありません。
離脱率を下げる構成の作り方を見ていきましょう。
PREP法
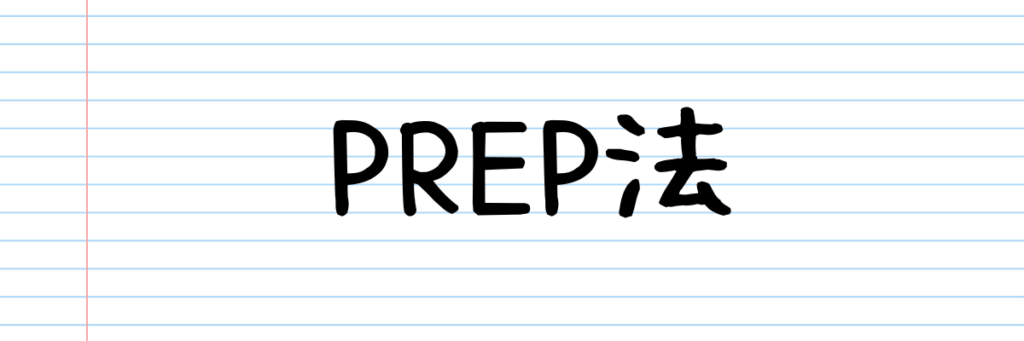
PREP法は、結論を最初に提示し、説得力のある文章を構築するための文章構成法です。
Point(結論):結論先だしで、最も伝えたいことを書く
Reason(理由):その結論になる理由を示す
Example(具体例):理由の裏付けになる具体例やエピソードを提示
Point(結論):最後にもう一度結論を語り、読み手を納得させる
プロ野球選手を例にPREP法で文章を作ります。
Point(結論):A選手は今年、チームの中心選手になると予想します。
Reason(理由):なぜなら彼は、バッティングが良くホームランを量産していてチャンスに強いからです。
Example(具体例):先日の試合でも8回の緊迫した場面で逆転満塁ホームランを打ち、チームを勝利に導きました。
Point(結論):打撃でチームを救い続けるA選手こそ、チームの中心選手だと考えます。
結論を一番に書き、なぜそう思うのか、どんな根拠があるのかを示しました。
内容が伝わりやすく、読み手の関心を集められるのがメリットです。
SDS法
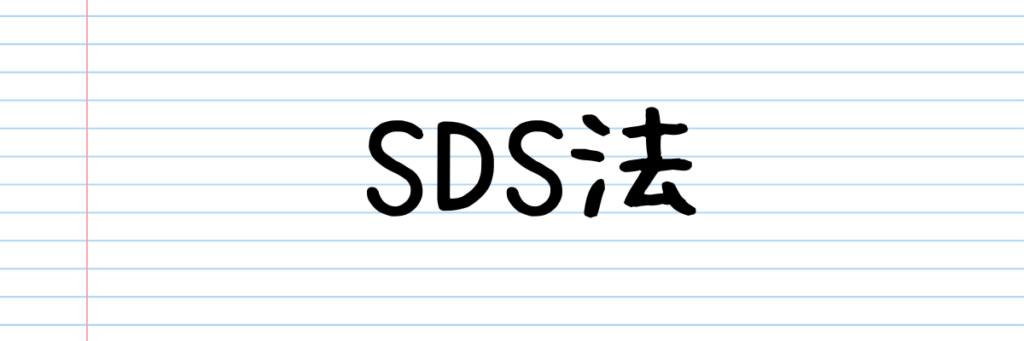
SDS法は、
Summary(要点):最初に結論や伝えたいポイントを示す
Details(詳細):続けて、その根拠や具体例を説明する
Summary(要点):最後にもう一度結論をまとめ、強調する
の略であり、文章の冒頭で要点を伝え読み手の理解を深める手法です。
商品紹介やサービス紹介、ニュースの報道で頻繁に使われます。
例文を見てみましょう。
Summary(要点):口にいれた瞬間、ふわっと溶けていくような食感。
Details(詳細):厳選された北海道の生クリームを使った数量限定のケーキです。
Summary(要点):一度食べたらやみつきになる、イチゴショートケーキ。ぜひ一度お試しください。
このようにSDS法を使うことで、印象的に商品紹介ができます。
起承転結
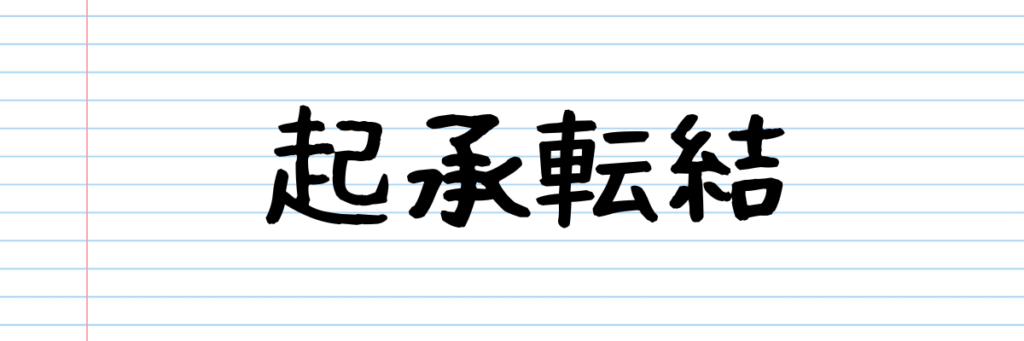
起承転結とは、読み手にスムーズに内容を伝えるための手法です。
起:導入部分
承:起の部分の内容を膨らませ、展開していく
転:文章の中で一番肝となる部分。意外性の提示や、驚きを与える
結:全体をまとめ、納得感を出す
例を挙げます。
起:ある街に、一匹の犬が住んでいました。犬はいつも、アパートの窓から外を眺めています。ある日一人でアパートの外に出てみました。
承:初めて見る外の世界に心躍らせていましたが、見慣れない光景に不安になってきました。
転:そんなとき意地悪な人間に追いかけられ、路地裏に逃げ込みます。あたりも暗くなってきて「もう帰れないかもしれない」と絶望する犬。そこへ偶然、犬の飼い主が通りかかります。
結:飼い主はずっと犬を探していました。無事アパートに帰れた犬は、やっぱり家だ一番だと思いながら眠りにつきました。
起承転結は読み手の納得させ、ストーリーに引き込みたいときに有効です。
AIで出力した文章をそのまま使わない

現在AIは目覚しい進化を遂げ、私たちの生活にも溶け込んでいます。WebライターもAIを使って執筆する人が増えてきました。
しかし、AIで出力した文章をそのままコピーして使わないようにしましょう。
その理由は以下の通りです。
情報の正確性に不安がある
AIは膨大なデータをもとに文章を作りますが、誤情報や古い内容を出す可能性があります。
結果として読者に誤解を与え、記事や書き手の信頼を損なうリスクがあります。
オリジナリティの欠如
AIの文章は既存データをもとにしているため「どこかで見たような表現」になりがちです。独自性のない記事は読者の心に残らず、検索エンジンからの評価も下がってしまいます。
AIは、アイディアに行き詰まったときや情報が見つからないときなど、あくまでアシスタントとして活用する程度にとどめましょう。
伝えたい情報の整理を正しく行う
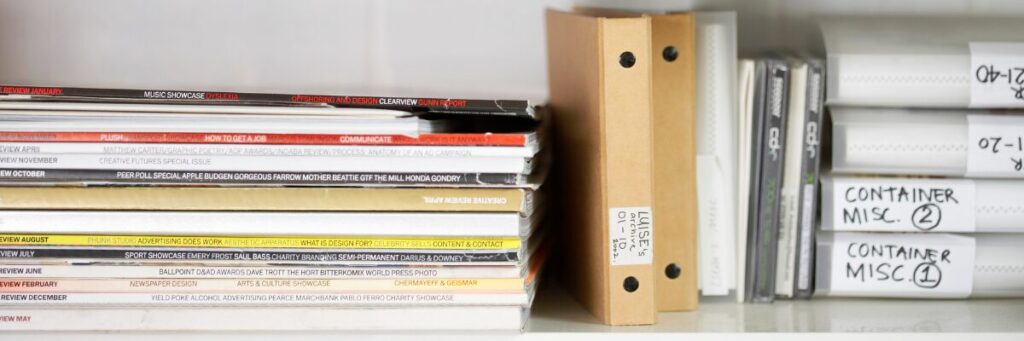
伝えたいことを一カ所に詰め込むと、読み手は混乱します。
まずは、伝えたいことをメモに書き出して整理しましょう。
情報を整理することで、記事を書く目的や読者に理解してほしいこと、促したい行動がはっきりします。
伝えたいことが決まったら、次に構成を考えましょう。順序立てて整理された文章は、読み手の共感や関心を得やすくなります。
情報整理と構成は、読者に「分かりやすい」「役に立つ」と感じてもらうために欠かせない文章作成の基本プロセスです。
筆者が文章を書く際に気をつけていること
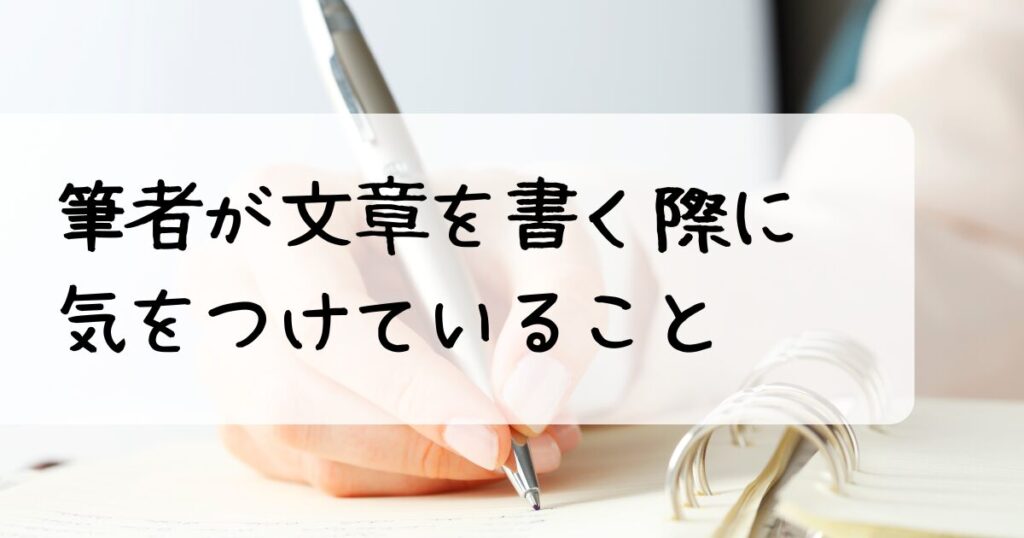
では、実際に文章を書くときに筆者はどんなことを意識しているのか、ポイントをお伝えします。
ターゲット選定は念入りに

文章を書くときにターゲット選定がずれると、本当に伝えたい人に届きません。
せっかく一生懸命書いても、伝えたい人に届かなければ意味がありませんよね。
ターゲットを明確にするには、まず同じキーワードで検索上位(1〜10位)の記事を読み込みましょう。検索結果の上位にある記事は、Googleが「読者の求める情報を十分に満たしている」と判断している証拠です。
上位記事を分析することで検索意図を深く理解でき、そのうえで具体的なターゲット像を描くことができます。
例えば、ターゲット像を「多くの人」ではなく「30代女性・共働きで時間がないが健康的に痩せたい人」と設定すれば、記事の内容や表現がぐっと具体的になり、特定の読者に強く響く文章になります。
上位記事のコピーにはならない

上位記事は、文章作成において重要な参考資料です。
しかし、その内容をそのまま踏襲しても読者を惹きつけることはできません。内容が重複している記事は「前に読んだものと同じ」と感じさせ、既視感から最後まで読まれない恐れがあります。
読者に飽きられず価値を提供するには、上位記事で検索ニーズを把握したうえで、自分なりのオリジナリティを加えることが欠かせません。
具体的には、上位記事から「読者が何を求めているのか」を理解し、そのニーズを満たしながら独自の視点や情報を盛り込むことです。
検索ニーズを意識しつつ独自性を打ち出すことで、他の記事にはない魅力を提供でき、読者の関心をより強く引きつけられる記事になります。

まとめ:基本に忠実に文章を書こう
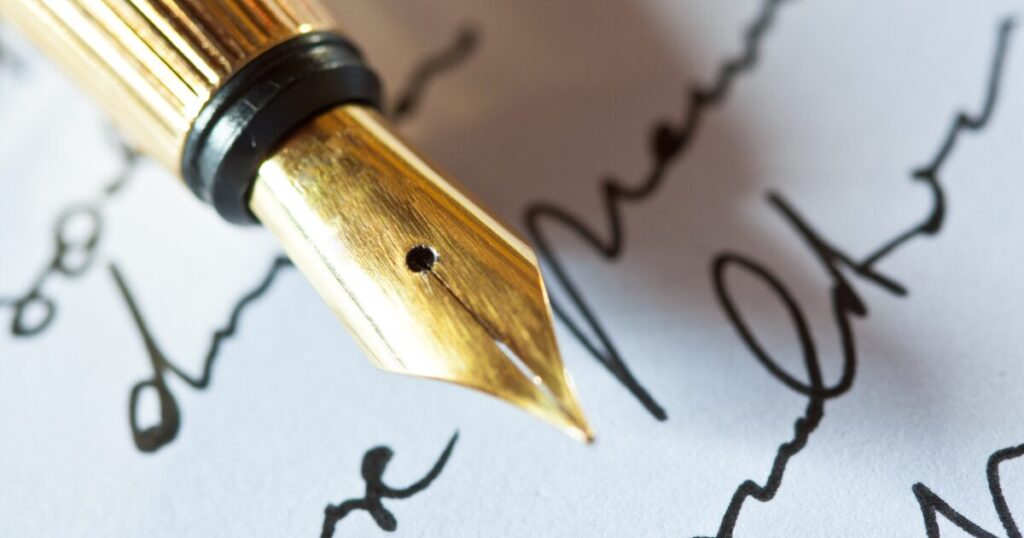
文章は、何でも好きなように書いていいわけではありません。
読み手の関心を引くには、基本を押さえて執筆することが大切です。
「なぜこの文章を書くのか」「誰に届けたいのか」を明確にし、ターゲットを決めましょう。
読んでほしい人の像が固まったら、わかりやすい言葉と構成で文章を組み立てます。
基本を意識して、読まれる記事を書く力を身につけていきましょう。
「文章の書き方」を調べている方からよくある質問
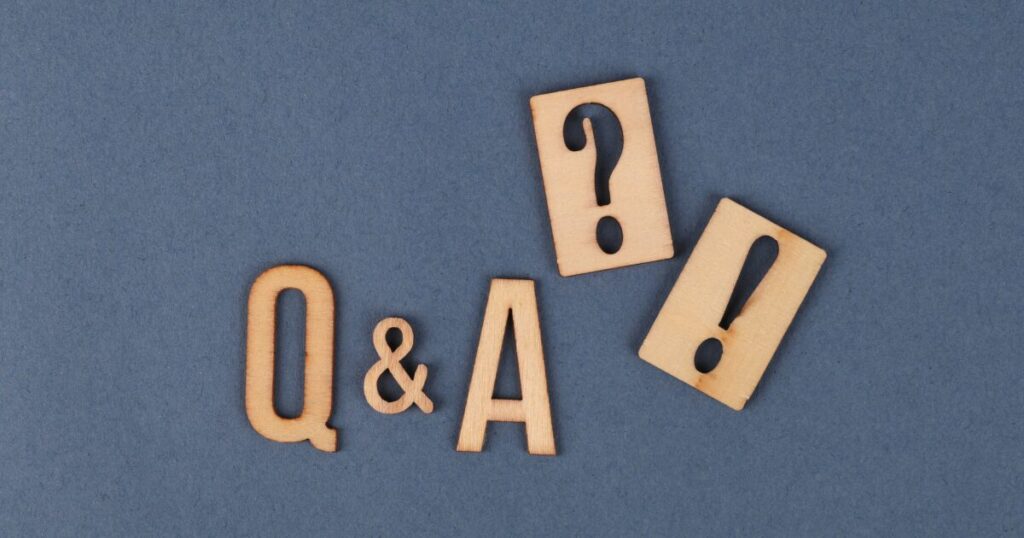
ライター歴7年の筆者が、これまでいただいたご質問に回答します。
よくある質問①未経験でもWebライターになれますか?
はい、なれます。記事を書いたことがない人でも、基本を押さえた文章が書ければ問題ありません。
大切なのは読み手のニーズを理解し、求められる内容を書くことです。
よくある質問②未経験だと文字単価はどれくらいですか?
受注する案件によって異なりますが、最初は文字単価0.5円〜1.0円程度が多いです。経験やスキルをつけることにより、文字単価2.0円〜3.0円の案件も獲得しやすくなります。
よくある質問③仕事はどうやって見つけますか?
クラウドワークス・ランサーズは、常に多くのクライアントが募集を出しているため、案件を見つけやすく初心者でも取り組みやすい環境が整っています。
また、これらのクラウドソーシング以外にも、X(旧Twitter)やInstagramなどのSNS上で案件募集が行われることもあります。
特にSNSではクライアントと直接つながれるため、単発ではなく継続案件に発展するチャンスも広がります。