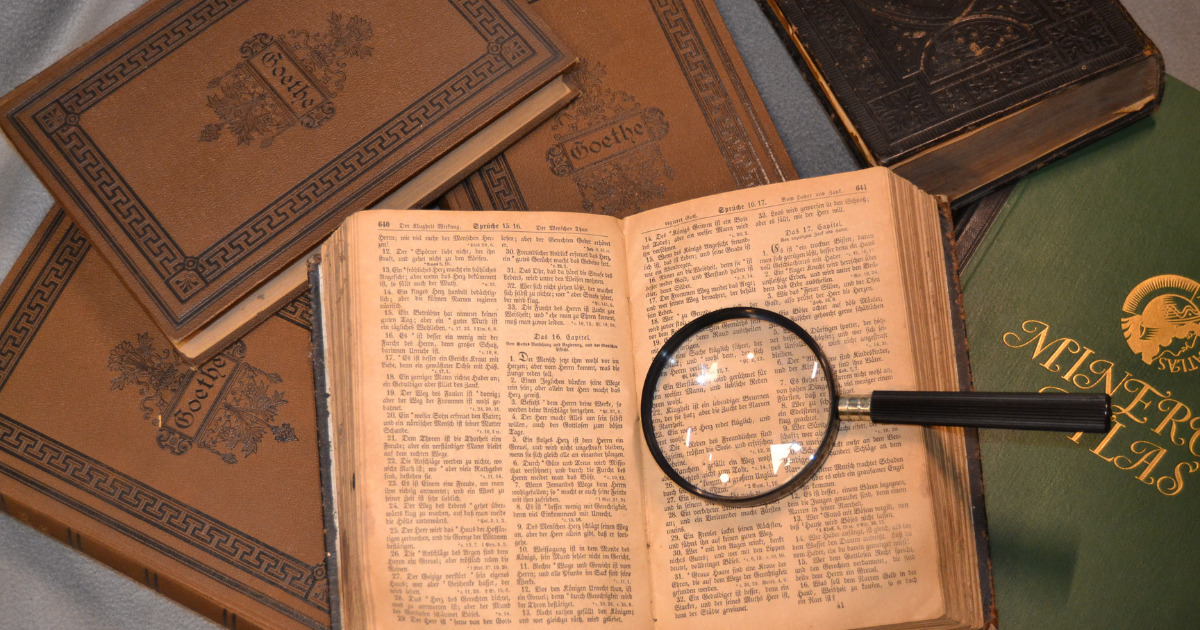われわれ人類が試行錯誤しながら歩んできた道、そこに『歴史』が刻まれます。
現代ではコピーライターという職業の名称は広く知られておりますが、あなたはコピーライターの歴史というものをご存知でしょうか?
これはあまり知られていないのですが、実はコピーライターとは、ずいぶん昔から存在する職業なのです。
そこで本記事では、日本と海外に分けて、コピーライターの始まりから現在にいたるまでの歴史上の主なことがらをご紹介します。
また、現代のコピーライター市場について、過去の様子と比較してお示ししましょう。
そして最後に、コピーライターに関する最新トレンドをお伝えします。
あなたが本記事をお読みになることでコピーライターに関する周辺知識を得られ、これまでよりもコピーライターについて魅力を感じていただけますと幸いです。

コピーライターの歴史(海外版)

われわれは相手と直接会って話をしなくても、あるいは電話で話をしなくても、文字を介して意思の疎通ができます。
文字を駆使して商品やサービスを売り込むことの意義や可能性を見いだし、それを実践し、効率を高める努力を始めた人々がコピーライターと呼ばれるようになりました。
そんなコピーライター発祥の地はアメリカ…ということで、
まずは海外のコピーライターの歴史から紐解いていきましょう!
コピーライターの誕生(1880年ごろ〜)
世界で最初の専業のコピーライターは、アメリカの『ジョン・E・パワーズ』であると言われています。
1880年代後半、他社で働いていた『パワーズ氏』は大手デパートに引き抜かれてコピーを書くことになったのですが、なんと従来の売り上げの2倍もの数値を叩き出す偉業を成し遂げました。
このパワーズ氏の成功をきっかけにコピーライティングの重要性に周囲が気づき、
広告代理店を起業する人が増えたのです。
コピーライティングの定義が定まる(1904年ごろ〜)
コピーライティングの定義・基礎を作ったのは、アメリカの『ジョン・E・ケネディ』であると言われています。
ケネディ氏は1904年にシカゴの広告代理店「ロード&トーマス社」を訪れ、経営者であるアルバート・ラスカーと「広告とは何か」議論を交わしました。
そのとき、ケネディ氏は「私は3語で表現できる」と主張し、
『Salesmanship in print(印刷された営業マンだ)』と示した定義が世に広まったのです。
後に彼らはビジネスパートナーとなり、コピーライティングの技術を確立していくこととなります。
ピアノコピー(1925年ごろ〜)

この時代になるとコピーライティングの技術はますます磨かれ、より良い広告を作成するための技術向上はもちろん、広告作成に活かすための『できる限り数値化した効果確認』が行われるようになりました。
本セクションでは、そんな時代に約49年間も現役で活躍した伝説的なコピーライター『ジョン・ケープルズ』を紹介しましょう。
ケープルズ氏は25歳であった1925年に、ある音楽学校の通信講座のコピーを発表しました。
They Laughed When I Sat Down At the Piano But When I Started to Play !~
(私がピアノの前に座るとみんなが笑いました。でも弾き始めると !)
引用:DIAMOND online(伝説のコピーライター、ジョン・ケープルズが25歳のときに発表した「ピアノコピー」全訳大公開!)
上記の一文は見出しとなっているのですが、これは現代でいうキャッチコピーにあたります。
筆者は初めてこの広告の日本語訳を見たとき、途中で読むのをやめることなど到底できませんでした!
というのも、見出しには「未完了のものや、情報の一部が隠されているものに注意が向かってしまう」という行動心理学「ザイガニック効果」が使われています。
このテクニックは現代のコピーライティングでも活用されているため、そんな手法が100年近く前にも使用されていたというのは感慨深いですよね…。
さらにケーブルズ氏は、自らが世に放ったコピーの「効果」を数値化し、具体的に確かめ改善することに努めるなど、広告・コピーライター市場の地盤を作った彼の功績は計り知れません。
世界のセールスコピーライターの頂点(現在)
現在、世界のセールスコピーライターの頂点と評されるのが、アメリカの『ジョン・カールトン』です。
カールトン氏のコピーは”世界で最も真似されている”とまで言われており、ライティング技術の1つであるフックの第一人者でもあります。
フックとは『顧客の心を引きつけ、その先の文章を読んでもらうために興味を惹きつけるための仕掛け』を指すのですが、昨今のライティングには欠かせない要素です。
そして優れたフックとは、”見込み客が抱えるぼんやりとしたニーズ”と”商品をつなぐポイント”であり、簡単には見つけられないとカールトン氏は語ります。
こういった技術の反映と名だたるコピーを手掛けた彼は現代におけるセールスコピーライターの頂点と言われるのも納得ですよね…。
以上の内容が海外版のコピーライターの歴史です。
また、意図的に選んだわけではないのですが、今回ご紹介した4人のコピーライターのファーストネームがすべて同じ『ジョン』であることに、筆者は驚きを隠せません…笑

コピーライターの歴史(日本版)

日本では、明治時代も半ばをすぎた1900年頃に広告代理店が出現し、コピーライターという職業が認知されるようになりはじめました。
しかし歴史を紐解くと、それよりももっと昔の江戸時代に
「今になって考えてみれば、コピーライターの”はしり”だったのだなあ」
と思われる人物がいたのをご存知でしょうか?
本セクションではそんな日本のコピーライターの歴史を紐解いていきます!
『コピーライター』ではないけれど…日本初?(江戸時代 1770年ごろ〜)
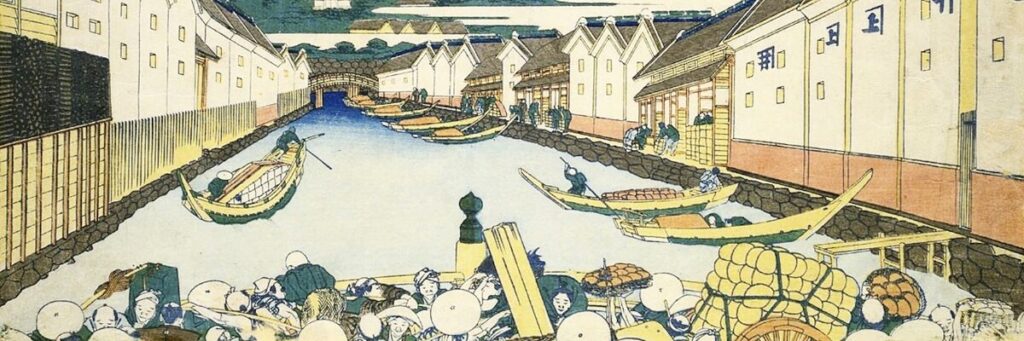
江戸時代にエレキテルの復元を行なったことで有名な発明家『平賀源内』。
彼が行なった仕事の一部は、今考えるとコピーライティングではないかと思われるような内容のものでした。
有名なのは、夏場に売り上げが落ちて困っているといって彼に相談を持ちかけてきた鰻屋に
「本日、土用の丑の日」と書いて店先に貼ることを勧めたという言い伝えです。
もともと鰻と土用の丑の日に関連はありませんが、名前のあたまに「う」がつくものを丑の日に食べると夏負けしないという風習が当時あり、源内がそこに目をつけたと考えられています。
しかし、鰻の広告を源内が発案したという明確な根拠は、残念ながら不明です。
そして、源内が行なったコピーライティングのような仕事として秀逸だと言われているのが、
1769年に江戸時代のチラシ「引札」に書いた『歯磨き粉「漱石膏(そうせきこう)」の広告文』です。
歯磨き粉をおすすめする言葉から始まるものの、
「元手のいらない商売」「砂に匂いを入れただけの価値のない品」などと内幕をバラしはじめます。
さらには「効能があるかどうかは分からないけれど害にはならない」「こちらは金欲しさに売り出したのだから、あなたがもし気に入らず捨ててしまっても大した損にはならず、当方は得をする」とまくしたてるのです!
「これはひどい!」と思われそうな話の展開ですが…
全体が『芝居の口上仕立て』で書かれているために、読み手が客の立場となり、売る側を『少しずるいが憎めない商人』役として登場させたお芝居になっているのです。
内情や本音をあっけらかんとさらけ出しているにも関わらず、お芝居という『フィクション』であるからこそ、読み手も苦笑いしながらも受け入れてしまう、そんな構造になっています。
この広告がもつ雰囲気は当時の江戸っ子におおいに受け入れられ、何度も読んで楽しむ者も多かったようです。
ジョン・E・パワーズが活躍した1880年代よりももっと古い時代に日本にこのような人が存在していたというのは、驚くべきことですね。
広告代理店の出現(明治時代 1900年ごろ〜)
1895年に「博報堂」が創業し、1901年には「電通」の前身である「日本広告」が創業しました。
そして現在もなお、博報堂と電通が、国内の広告代理店の2大巨頭と呼ばれています。
そうして移りゆく世間のなか、新聞広告やバス、電車などの乗り物内の広告を専門に手がけるコピーライターが職業として認知されるようになってきたのがこの頃。
当時はコピーライターではなく「文案家(ぶんあんか)」と呼ばれるのが一般的でした。
現代でも文章を構想することを「文案」と言うことがありますが、あまり馴染みのない言葉ですね…。
新聞広告:グリコ豆文広告シリーズ(昭和時代 1930年ごろ〜)
現代も大阪に訪れる観光客の多くが写真を撮って親しまれている、道頓堀川沿いの巨大ネオンサインでおなじみの『グリコ』。
昭和初期には名コピーライターである『岸本水府』が新聞広告で、この『グリコ』のキャッチコピーを発表しました。
この頃の新聞各紙にはグリコのキャッチコピーがほぼ毎日掲載され、好評を博していたそうです。
まだ幼い子供が毎朝新聞受けに走り、朝食のしたくをしている母親にこの広告を見せて喜んでいる、そんな様子が目に浮かびます…。
引用:アドミュージアム東京
株式会社宣伝会議(昭和時代 1954年ごろ〜)
1954年には「久保田宣伝研究所(現、株式会社宣伝会議)」が、日本で初めてのコピーライター養成講座を始めました。
また、1962年に公募形式の広告賞である「宣伝会議賞」が創設。
宣伝会議賞の受賞者の中には、もののけ姫のキャッチコピー『生きろ。』で有名な糸井重里氏。
エッセイ集『ルンルンを買っておうちに帰ろう』で有名な林真理子氏も名を連ねており、国内のコピーライターの輩出、コピーライティングという仕事の普及に大きな貢献をしています。
現代のコピーライター市場とは?

ここまで、国内外のコピーライターの歴史を振り返ってきました。
その頃のコピーライターは、実際にペンや筆を持ち、紙に書いて仕事をしていましたが、インターネットが普及した現代では、コピーライターを取り巻く環境も大きく様変わりしています。
それでは現代のコピーライター市場は、どうなっているのでしょうか?
本セクションでは過去〜現在の変化から現代のコピーライター市場を見てみましょう!
コピーライターの存在の変化
かつてのコピーライターは広告代理店や一般の企業に所属して、広告文の作成を主とした文章を作る仕事を担当する職業でした。
また、コピーライターとは「キャッチコピーを作る職業」と世間に認識されていることが多く『語数が少なくてセンスのよいフレーズ(言葉)』を考え出す人たちという捉え方をされることも少なくありません。
しかし現代では、キャッチフレーズを作るばかりがコピーライターの仕事ではありませんし、企業へ所属せずに活動する、いわゆるフリーランスという業務形態があったりとその存在のカタチは変化を遂げています。
コピーライターの仕事の受け方の変化
広告メディアの発展により、コピーライターの仕事は大きな変化を遂げました。
というのも、広告の配信先が昔から主流だったテレビや雑誌、新聞といったマスメディアから、
Web(インターネット)メディアに大きくシフトしてきているからです。
Webを使って、商品の売買を自宅にいながらできてしまう…。
そんな環境が整ったからこそ、コピーライターの仕事の受け方が変化したというのも自然な流れでしょう。
昨今では『クラウドソーシングサイト』という”仕事を委託したい企業”と仕事を請けたいワーカーを繋げる仕組みが一般化されており、企業に直接雇われないと仕事を請けられなかった時代からは変化しています。
Webが発展していなかった頃は、仕事募集の情報を見つけることも、自己発信することも容易ではなかったため、狭き門というイメージを持っている方も多くいたようですが、ハードルも下がり時代は変わりましたね…。
コピーライターが手がける仕事内容の変化
記事の冒頭でご紹介したとおり、歴史をひもとくと、もともとコピーライターの仕事は「広告の文章を作ること」でした。
しかし現代のコピーライターは広告に限らず、さまざまな文章を作る職業になってきているのです。
本記事ではコピーライターと一言でお伝えしていますが、一般的には大きく分けて3種あります。
・コピーライター:キャッチコピーなどの広告作成
・セールスライター:商品・サービスを売る目的の文章作成
・Webライター:ブログ、SNSなどのWebメディアに載る文章作成
これらライターの種類をより細分化すると以下のようになります!(一例にすぎませんが…)
・専門ライター:ある分野に特化した記事を書く
・取材ライター:現場取材をして記事を書く
・ルポライター:社会問題や事件を記事にまとめる
・シナリオライター:いわゆる脚本家
・ゴーストライター:代筆をする
・コンテンツライター:商品等の魅力を伝える記事を書く
つまり、選択の幅が広がり、自身が取り組みやすい分野のコピーライターを目指すことが可能になったといえるでしょう。
こういった背景のもと、現代においてのコピーライターという職業は”まったくの未経験の人でも明日から始められる身近なもの”になっています。
コピーライターの最新トレンド【3選】

本セクションでは、コピーライターに関する最新のトレンドを3つご紹介します。
筆者はコピーライターのため、最新のトレンドを押さえておくのは当然ですが…。
本記事を読んでくださっているあなたも、コピーライターに少しでも興味をもっているのであれば本セクションの内容は”知っておいて損はない”ので…ぜひ読み進めていただけますと幸いです!
①文章作成AIの出現

昨今では、ChatGPTやBing、notionAIといった文章作成AIが台頭しはじめました。
文章生成AIとは、大規模言語モデル(Large Language Model)に基づいて文章を生成するプログラムのことです。
大規模言語モデルは深層学習によって大量の自然言語テキストを手本として学習し、ある一連の言葉が入力された後に、続く可能性の高い言葉を予測して出力する仕組みになっています。
このAIの出現により、コピーライターの仕事がAIに取って代わられてしまうと心配する声があります。
しかし、コピーライターの仕事の本質は、文章で「読み手の感情を揺さぶり、行動を促す」こと。
無機質な事実だけを提示する文章に、そのようなチカラはありません。
そのため、コピーライターの仕事がAIに取って代わられることはないと筆者はもとより、ライター業に携わる方々の多くが唱えています。
むしろ、AIを活用することでコピーライター市場はより発展できるのではないか…?とすら言われているのですが…。このコピーライターとAIの関係について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください!
アメリカのニューヨーク・タイムズ(以下NYT)が、2023年8月3日に利用規約を変更し、記事や写真などを無断でAIの学習に活用することを禁止したとのことです。
NYTは「利用規約に従わない場合、民事や刑事での罰金や罰則が科せられる可能性がある」と警告しました。
NYTとOpenAIは、NYTの記事をAIの学習に使用するにあたってライセンス料を支払う契約について交渉を続けてきていますが、協議が紛糾したためNYTは法的措置を検討していると報じられています。
一方、2023年7月13日にはAP通信が、OpenAIとニュース記事の使用についてライセンス契約を締結したと発表しました。
OpenAIが開発したChatGPT、その学習に使用されるデータに関する今後の動向が気になるところです。
②動画コンテンツが主流に?

これからは、動画コンテンツに関わるライティングが重要になってくると言われています。
アメリカは人口が多く、国土も広く、通信販売が重要な販路になっている国であるため、セールスライターを主として、コピーライターの数が非常に多いです。
そして過去の傾向から、アメリカのコピーライター市場の動きは、少し遅れて日本でも起こることが予測できると言われています。
そのアメリカで最近は、記事となる文章作成に代わって動画コンテンツに関わる文章を作る仕事がメインになってきているとの情報があるのです。
例えば、動画のシナリオ、あるいは動画の内容の構成企画を書く仕事で、商品紹介動画、商品紹介アニメのような、短時間の動画の制作に関する業務が増えてきているとのこと。
先のことを考えて、動画に関わるライティングスキルの習得を目指すのもよいかもしれません。
③広告から狭告へ

突然ですが、あなたは『狭告(きょうこく)』という言葉をご存知でしょうか?
これは「狭い」と「広告」を合わせた言葉で「対象をしぼってコンセプトを明確にした広告活動」のことです。
先の章で触れましたが、広告を発信するにあたり、マスメディア利用からWebメディア利用にシフトしてきています。
そのため、これまでのように不特定多数に対して広告するのではなく、対象を絞り込み、訴求内容も特定の個人に訴えかけるような対応が主流になってきているのです。
身近な例としては、インスタグラムで見つけた「商品の広告」に表示されたリンク先に飛ぶと、次の日にはまた同じ商品の広告が表示される…というケース。あなたは経験ないですか?
筆者は、結構身に覚えがあります。
(今日も「売れるセールスライティング資料」という趣旨の広告を目にしました…笑)
しかし、もしその商品が高額で購入する決断がなかなかつきづらいものであったならどうでしょう。
売り手としては日々内容を変えつつ、読み手の心を動かして購買意欲を高める広告を打つに違いありません。
このとき、この広告はたったひとりの読み手に対して発せられる「狭告」となり、その文面を考えるのはライターの腕の見せ所となることでしょう。

まとめ:歴史を調べてわかること
本記事ではコピーライターの歴史、現代の市場の様子、そして最新トレンドとご紹介しましたが、いかがでしたか…?
実は筆者自身、正直に申しますとコピーライターに関する歴史や昔のことをそこまで詳しくは知らなかったため、改めて調査を進めると楽しみながらも発見ができました。
また、コピーライターの存在意義・原点はもともと「商品やサービスを売るための広告を作成すること」であったと認識することができたのです。
そして、いつの時代も「広告とは何か?」「どういう広告が効果的であるのか?」という普遍的な問いと向き合いながら、コピーライターは仕事をしてきたのだなと感じます。
その上で「どうしたら、目に留めてもらえるか?」「どうしたら、さらに読み進んでもらえるか?」と、読み手を想像しながら、その気持ちをどう動かすかについて考えることが大切であると再認識しました。
読んでくださったあなたにもコピーライターについて少しでも知ってもらえて、その業務に興味を持っていただけたなら、こんなに嬉しいことはありません。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。