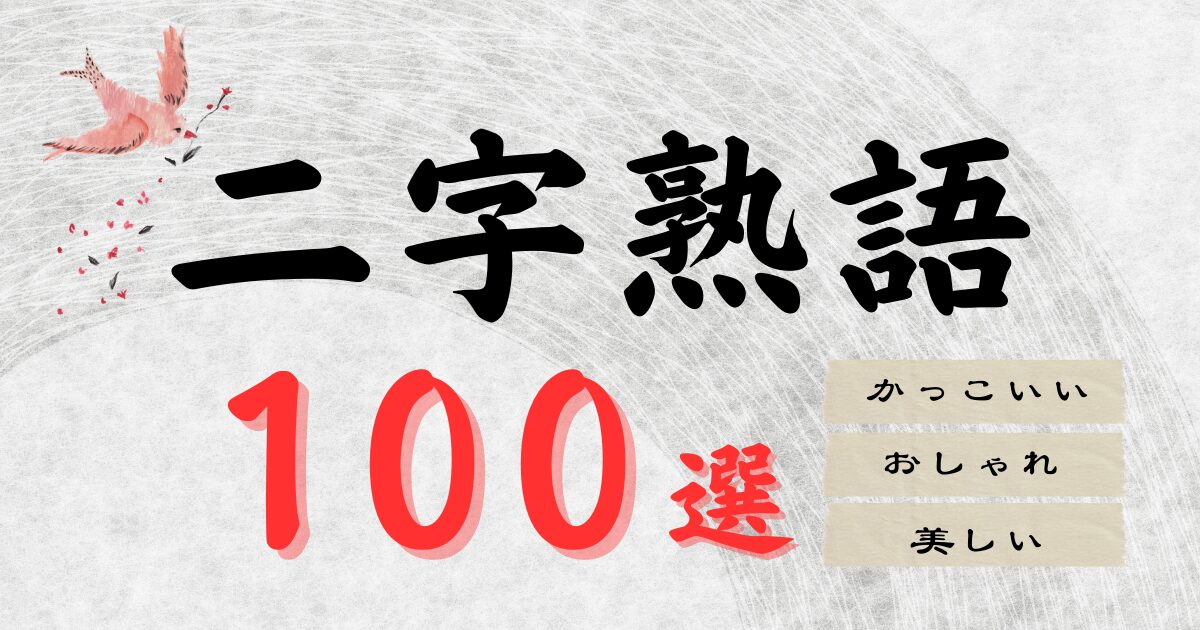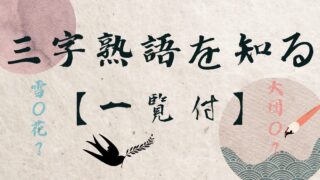スローガンや目標などに使える素敵な二字熟語を探していませんか?
見た目や響きが良い二字熟語を見ると、気分が上がりますよね。
また、チーム共通の二字熟語を使えば、団結力が高まるかもしれません。
この記事では、さまざまな二字熟語について解説します。
かっこいい二字熟語を知りたい方や、語彙力を高めたい方、雑学が好きな方、座右の銘を見つけたい方にもおすすめです。
あなたにとってお気に入りの素敵な二字熟語がみつかるかもしれません。
ぜひ最後までご覧ください。
- 二字熟語とは
- 二字熟語の構成一覧
- キャッチコピー、目標、スローガン、スポーツ、季節、天気に関連する二字熟語
- 二字熟語クイズ

二字熟語とは?
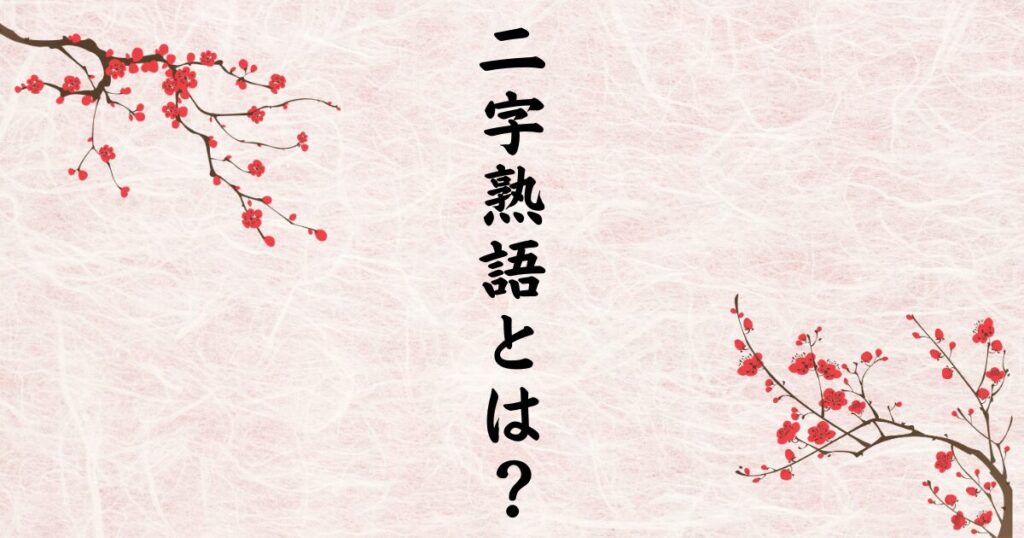
二字熟語は2つの漢字を組み合わせた言葉です。
それぞれの漢字の意味を合わせて意味を強調したり、変化させたりします。
日本で二字熟語がいつできたかは不明です。
しかし「新聞」「社会」「資本」などは、明治時代以降に欧米から入った英語を翻訳し、二字熟語にしたと言われています。
「新聞」「社会」「資本」などは、元は日本にない言葉でした。
二字熟語の特徴は以下の5つです。それぞれについて解説します。
- 簡潔に伝わる
- 覚えやすさ
- 豊富な組み合わせ
- 意味の変化や拡張
- 音読みと訓読みの組み合わせ
二字熟語は2つの漢字で多くの意味を持ち、文章を簡潔に表します。
そのため、直感的に理解しやすいと言えるでしょう。
ロゴやポスターなどのデザインにも取り入れやすい言葉です。
また、時間をかけずに一目で伝える広告やキャッチコピーにもおすすめです。
二字熟語は漢字2文字のため、見た目が良く記憶に残りやすいメリットがあります。
ビジネスシーンから日常生活まで、幅広いシーンで使われます。
1文字でそれぞれ意味を持つ漢字。
2つの漢字を組み合わせると、類語や反対の意味など、多くの意味を持つ二字熟語が作成できます。
1つで意味を持つ漢字を2つ組み合わせると、意味が変化したり広がったりします。
二字熟語の大きな特徴と言えるでしょう。
二字熟語は「音読み2文字」または「訓読み2文字」を組み合わせた二字熟語が一般的です。
しかし、例外として「音読み+訓読み」または「訓読み+音読み」の二字熟語もあります。
音読み+訓読みを「重箱(じゅうばこ)読み」、訓読み+音読みを「湯桶(ゆとう)読み」と言います。
二字熟語の構成「5種類」
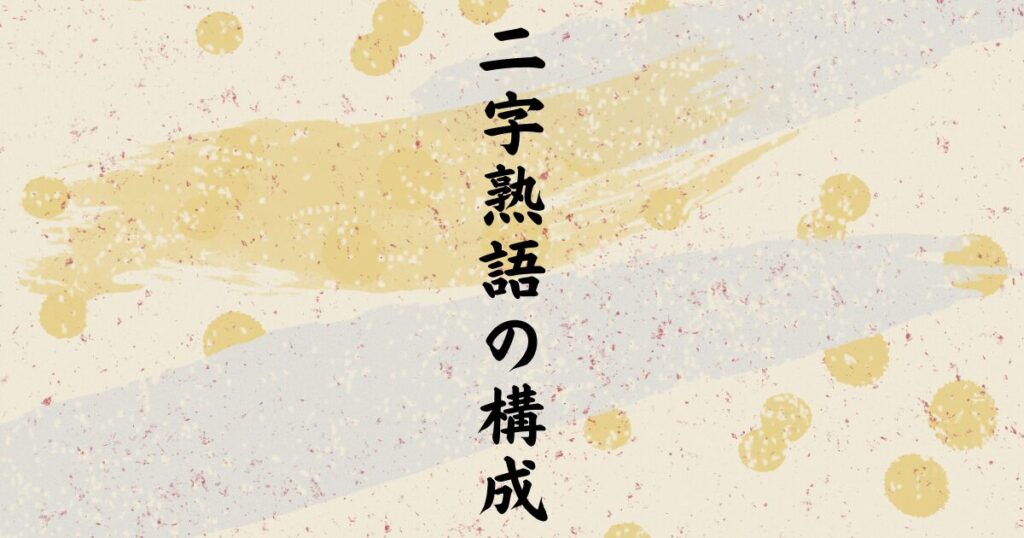
二字熟語には構成が5種類あります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
主語・述語関係にある漢字(日没・国立)

それぞれの漢字が主語と述語の関係にある二字熟語です。
直感的に理解しやすく、意味が推測しやすい言葉だと言えるでしょう。
例:日没(日が沈む)/国立(国家が設立される)
似た意味の漢字(温暖・離散)

似た言葉を組み合わせてできた二字熟語です。
類語を組み合わせると、意味を強調する効果があります。
例:温暖(温める+暖かい)/離散(離れる+散る)
反対の意味の漢字(上下・増減)
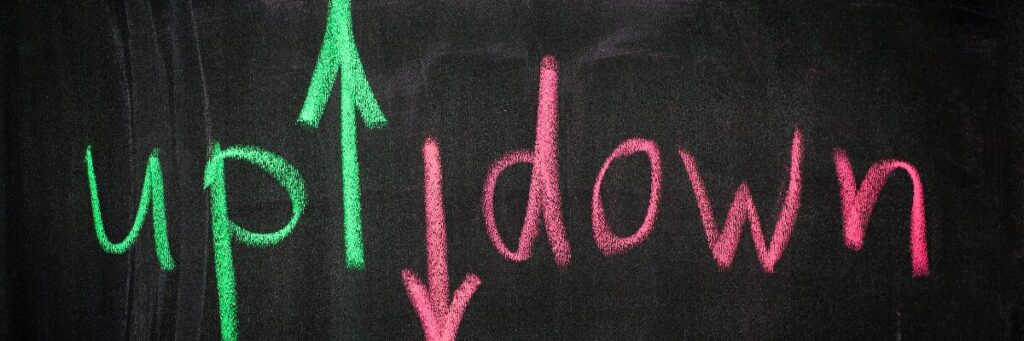
反対の意味を持つ漢字を組み合わせてできた二字熟語です。
組み合わせると、対照的な意味を強調します。
例:上下(上・下)/増減(増える・減る)
上下が修飾関係にある漢字(高所・美人)

上の漢字が下の漢字を修飾する二字熟語です。
二字熟語全体の意味が明確になります。
例:高所(高い所)/美人(美しい人)
下の字が上の字の目的になる漢字(登山・読書)

下の漢字が上の漢字の目的になる二字熟語です。
行動を明確に表す効果があります。
例:登山(山に登る)/読書(書物を読む)
キャッチコピーでよく使われる二字熟語【五十音順】
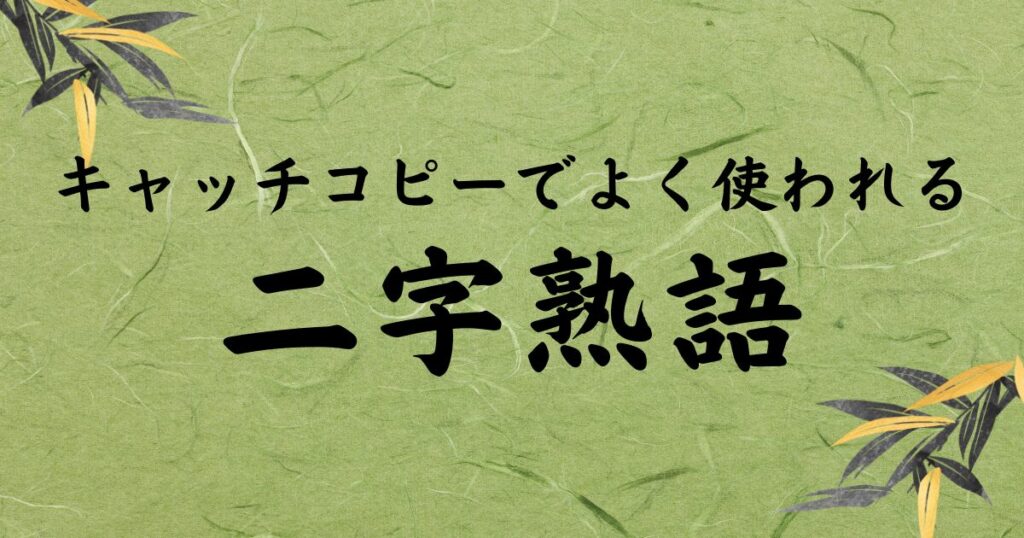
キャッチコピーでよく使われる二字熟語20選を解説します。
短い言葉でもインパクトがあり、心に響く訴求力の高い言葉です。
キャッチコピーを作成する際は、ぜひ参考にしてください。
圧巻(あっかん)
他と比較して特に優れている様子を表しています。
視覚的、感覚的に強い印象を与える場面で使われる言葉です。
古代中国では答案用紙を「巻」と表しており、最も良い答案を一番上に置く習慣がありました。
この習慣により、他の答案用紙を上から押さえつける=圧巻になったと言われています。
現在は「複数ある中で最も優れていること」の意味で使われています。
一流(いちりゅう)
ある分野において、最もすぐれたレベルを表しています。
何かを高く評価する場合に用いられる言葉です。
江戸時代は、1本の木から作られる最上級の材料を「一流木」と呼んでいました。
転じて、優れた品質や能力を意味するようになりました。
快感(かいかん)
心地良い気持ちや感覚を表しています。
身体的だけではなく、精神的な場面でも用いられる言葉です。
革新(かくしん)
古いものを改めて、新しいものに変える場合に用いられます。
大きな変化や発展、進歩を表す言葉です。
「革」には「あらためる」という意味があるため「新」と合わせて意味を強めています。
華麗(かれい)
外見や姿、動作が美しく華やかな様子を表しています。
高級感や優雅さを強調する場面で使われる言葉です。
鮮やかな「華」と、上品さを意味する「麗」を組み合わせて、美しさを強調しています。
奇跡(きせき)
普通では起こりえない出来事を指しています。
滅多にない素晴らしい出来事が起きたときに用いられる言葉です。
究極(きゅうきょく)
非常に高いレベルや限界を示しています。
「究」と「極」はいずれもこれ以上のものがない状態を表しているため、意味を強調しています。
剛毅(ごうき)
心や意志が固い場面で使われます。
困難に直面しても、自分の信念を貫き通す姿勢を表現した言葉です。
「剛」と「毅」にはいずれも強いという意味があるため、2語をつなげて意味を強調しています。
高揚(こうよう)
気分や感情が高まる場面で用いられます。
喜びや誇りなど、ポジティブな感情を表す言葉です。
「高」と「揚」にはいずれも上がる意味があるため、つなげて意味を強めています。
極上(ごくじょう)
品質や状態が最も良く、他よりも格段に上質なものを表す言葉です。
「極」には「これ以上ないこと」「最果て」の意味があるため、これ以上先のない上=最も良い状態を指しています。
最高(さいこう)
物事が最上位にある場面で用いられる言葉です。
満足度が最も高い場合に多く使われます。
至上(しじょう)
物事が頂点にある状態を表しています。
他に比較するものがないほど優れているシーンで用いられる言葉です。
「至」には「終着点」の意味があるため、一番上の終着点=頂点を示しています。
進化(しんか)
物事が時とともに変化し、改善される過程を示しています。
「進」は「すすむ」「化」は「別のものになる」という意味があるため、
良い方向に発展する意味を持つ言葉です。
絶品(ぜっぴん)
比較できるものがないほどすぐれた品物を指す言葉です。
おいしい料理や食品に対して多く使われます。
超絶(ちょうぜつ)
程度が他と比べてはるかに優れている場面で用いられます。
きわめて高い評価や称賛される場合に使われる言葉です。
電撃(でんげき)
体に電流が通ったような、強い衝撃を受けた場面を指しています。
世の中が驚くようなニュースや発表の際にも用いられる言葉です。
美景(びけい)
心が和むような美しい景色に対して使われる言葉です。
自然の風景や建物、街並みの他に、美術や写真などにも多く使用されます。
冒険(ぼうけん)
未知の世界を求めて、新しい事柄に挑戦するシーンで用いられます。
「冒」には「むやみに突き進む」「険」には「けわしい」という意味があります。
危険な状態を承知の上で、あえて行う場合に使われる言葉です。
魅力(みりょく)
他者を引きつける力を表現しています。
魅了される、好感を持たれる要素がある場合に使われる言葉です。
「魅」は古代中国の神話に登場する妖精を表しています。
妖精には人々を引きつける力があると言われており、転じて、人々を引きつける力=魅力になりました。
無敵(むてき)
どんな相手にも打ち勝つという意味があります。
絶対的に有利な状態を示す言葉で、敵がいない=ずば抜けて強い実力者に対して使われる言葉です。
目標・スローガンに使える二字熟語【五十音順】
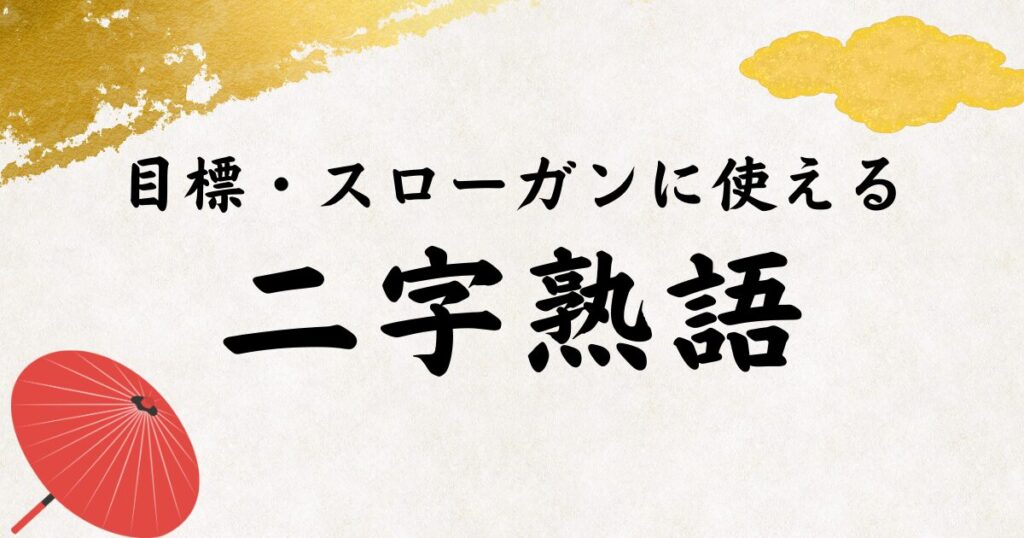
目標やスローガンでよく使われる二字熟語20選を解説します。
力強く前向きな印象があり、やる気や団結力を高める言葉です。
チームで使えば、士気が上がるでしょう。
目標やスローガンを作成する際は、ぜひ参考にしてください。
栄光(えいこう)
名誉や成功を示す場合に用いられます。
努力の結果、勝利や偉業の達成につながる場面で使われる言葉です。
「栄」には「さかえる、活気がある」という意味があります。「光」を組み合わせて、輝かしい名誉を表しています。
開拓(かいたく)
未知の分野に進出し、開発する場面を表しています。
土地だけでなく、技術開発などにも使われる言葉です。
元は「荒野を田畑へ変える」という意味がありました。
苦労しながら、全く異なるものへ発展させる際に用いられます。
革命(かくめい)
大きな変化や進歩を表現しています。
「天命が改まる」という意味があり、従来の慣習を大きく変えるシーンで用いられる言葉です。
希望(きぼう)
将来に対して前向きな期待や願望を持つ場合に用いられます。
勇気や力を与える言葉です。
「希」と「望」にはいずれも「のぞむ」という意味があります。2つの漢字を重ねて、意味を強調しています。
向上(こうじょう)
上に向く意味があるため、物事がより良い状態に進化するシーンを表しています。
能力や技術などによく使われる言葉です。
情熱(じょうねつ)
非常に強い熱意を表現しています。
燃えるような力強さを持ちながら、目標に向かって全力で取り組む場面で用いられる言葉です。
信念(しんねん)
何かを信じて疑わない気持ちを表しています。
強い覚悟が感じられる言葉です。
「念」には「心に思いを寄せる」という意味があり、信じる心を持ち続ける行動を示しています。
誠実(せいじつ)
自分自身や他者に対して偽りのない態度を示しています。
「誠」には「真実」、「実」には「本当の」という意味があり、同じ意味の漢字を合わせて意味を強調しています。
信頼関係を築くためにも大切な言葉です。
成長(せいちょう)
進化する状態を表しています。
個人の能力や社会の発展について使われる言葉です。
責任(せきにん)
任されたことを最後までやり遂げる場面で使われます。
信頼や高評価が期待できる言葉です。
前進(ぜんしん)
目的や目標に向かって進歩、成長する意味で用いられます。
前向きな印象を持つ言葉です。
全力(ぜんりょく)
自分が出せる最大限の力を使う場面で使われます。
熱意を持って取り組む姿勢が感じられる言葉です。
超越(ちょうえつ)
非凡な能力や存在感を持ちながら、限界を超えるシーンを表現しています。
「超」には「かけ離れている」「抜きん出ている」という意味があり、普通の程度をはるかに超える場合に使われる言葉です。
挑戦(ちょうせん)
困難に立ち向かい、乗り越えようと健闘する場面で使われます。
果敢に取り組むシーンを表現する言葉です。
努力(どりょく)
目的を達成するために、精一杯取り組むシーンを表しています。
願望を叶えるために、諦めずにこつこつと励み続ける印象のある言葉です。
突破(とっぱ)
努力により困難を乗り越える場面を表現しています。
積極的な意欲が感じられる言葉です。
発展(はってん)
状況が進み、より良い状態に変わる場面を指しています。
持続的な進展が期待される言葉です。
「発」は物事が進む、「展」は広がるという意味です。
2つを合わせて物事が伸びて盛んになる、潜在的な可能性が実現する意味になります。
飛躍(ひやく)
大きな進歩や発展を表し、目標達成に向かって進む場面で使われる言葉です。
「飛」と「躍」にはいずれも「飛ぶ」「高く跳ね上がる」の意味があり、大きく発展するイメージがある言葉です。
未来(みらい)
現在や過去と対比してこれから起こる実現する時間や出来事を指します。
特定の人や出来事は対象にならず、大きな範囲で用いられる言葉です。
理念(りねん)
個人や団体、組織が持つ方針や目標を表すものです。
企業理念など、事業や計画に対する根本的な考え方を示しており、物事を判断するときの指針として使われます。
スポーツで使える二字熟語【五十音順】
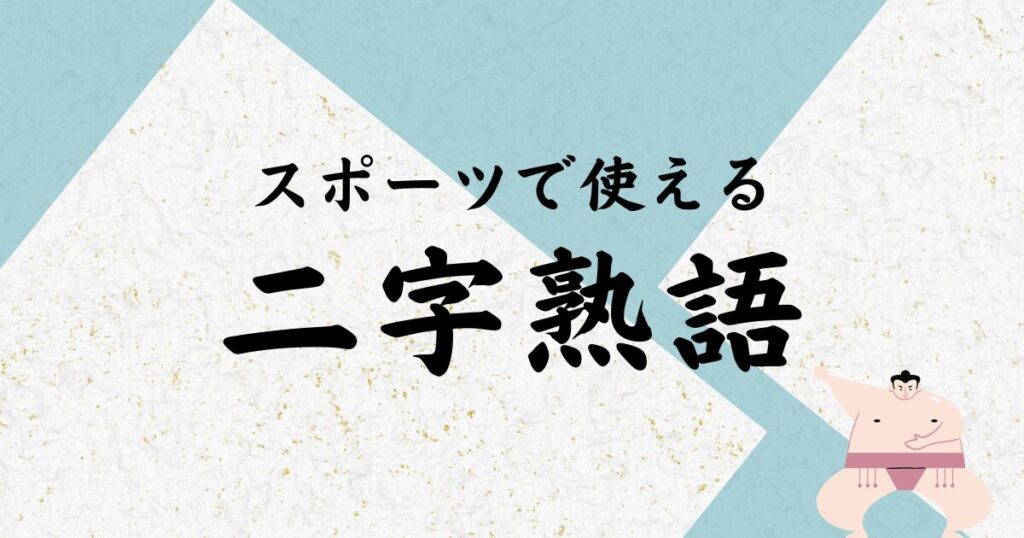
スポーツでよく使われる二字熟語20選を解説します。
レベルの高さや力強さを感じさせる言葉です。
スポーツで使える二字熟語を使用する際は、ぜひ参考にしてください。
部活などのチームTシャツに使うのもおすすめです。
圧倒(あっとう)
非常に強い力やレベルで相手に打ち勝つ場面を表しています。
相手との間に大きな差があり、強く押さえつけて相手を屈服させる意味が込められている言葉です。
一撃(いちげき)
相手に打撃や攻撃を加える場合に用いられます。
一度の攻撃で相手に強くダメージを与える言葉です。
極限(きょくげん)
物事の限界ギリギリの位置を表しています。
これ以上先に進めない場合に用いられる言葉です。
「極」は最高点「限」は制限の意味があり、限度ギリギリの切迫した状況を示しています。
結束(けっそく)
共通の目標に向かって、人々が団結する場面を示しています。
連帯感が高まる言葉です。
「結」と「束」には、いずれもまとまる意味があり、バラバラだったものが1つになる意味を強調しています。
最強(さいきょう)
最も強いことを表しています。
絶対的な強さを指す場合に用いられる言葉です。
成就(じょうじゅ)
願いが叶うシーンで用いられます。
長い間の努力が実を結ぶ場合によく使われる言葉です。
勝利(しょうり)
試合などで相手に打ち勝つ場合に用いられます。
目標の実現や喜び、ポジティブで強い印象を持つ言葉です。
団結(だんけつ)
多くの人が同じ目的のために心を合わせるシーンで使われます。
「団」と「結」にはどちらもまとまる意味があるため、一体感を強調する言葉です。
闘志(とうし)
戦いに対する強い意欲や情熱を表しています。
困難な状況に立ち向かう強い気持ちを表現する言葉です。
熱血(ねっけつ)
燃えるような情熱を表しています。
血が沸き立つような、熱い意気込みが感じられる言葉です。
覇者(はしゃ)
「覇」は武力で天下を取るという意味があります。
転じて、試合で優勝し、頂点に立った人を指します。圧倒的な力を感じる場面で使われる言葉です。
飛翔(ひしょう)
目標に向かって大きく飛躍する場合に用いられます。
新しい挑戦に立ち向かうイメージのある言葉です。
いずれの漢字にも「飛ぶ」「羽ばたく」という意味があるため、上を目指す印象を強調しています。
必勝(ひっしょう)
勝ちを狙っている場合や、確実に勝利する場面で使われます。
努力の積み重ねにより、絶対に勝つという信念を感じさせる言葉です。
妙技(みょうぎ)
技術が非常に優れている場面を示しています。
芸術やスポーツの分野で主に使われる言葉です。
無双(むそう)
並ぶものがないほど優れている状態を表しています。
「無」は「ない」「双」は「2つ、並ぶ」の意味があり、成績や人気、能力が圧倒的に高い場合に使われる言葉です。
猛攻(もうこう)
非常に激しい攻撃を意味しています。
「猛」には「荒々しい」という意味があるため、相手を激しく攻め立て、圧倒する様子を示す言葉です。
躍進(やくしん)
飛躍的に進展する場面を指しています。
「躍」には高く飛ぶという意味があります。
高く飛びながら進むため、前向きで目覚ましい成長が感じられる言葉です。
勇気(ゆうき)
恐れず困難に立ち向かうシーンを表しています。
心の強さや精神力を示す言葉です。
雄飛(ゆうひ)
才能を発揮して、大きな成果を挙げる状況を示しています。
雄鳥が力強く飛ぶイメージを表した言葉です。
連覇(れんぱ)
複数回連続して優勝する場面を指しています。
安定した実力や、継続的な努力が感じられる言葉です。
「覇」には「天下を取る者」の意味があるため、続けて天下を取る意味があります。
季節に関する二字熟語【五十音順】
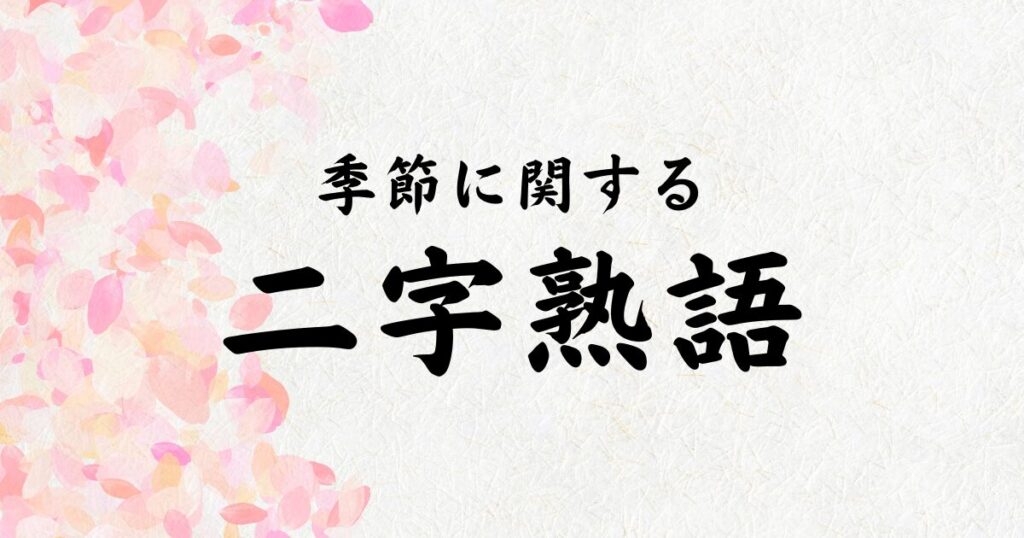
季節に関する二字熟語20選を解説します。
日本の四季を感じる風景や気候、自然の美しさが楽しめる言葉です。
挨拶や手紙、ビジネスメールなどにも使えます。
春

春に関する二字熟語は、物事の始まりや生命の力強さを感じます。
明るくポジティブな印象を持つ言葉です。
開花(かいか)
花の美しさや、自然の生命力を表しています。
新たな希望を予感させる言葉です。
春光(しゅんこう)
春の柔らかい日差しを表しています。
美しい景色を鮮やかに描写するイメージの言葉です。
新緑(しんりょく)
鮮やかな若葉が茂る様子を示しています。
明るく爽やかな気分になる言葉です。
春風(しゅんぷう)
春に吹く爽やかな風を表現しています。
新たな始まりを象徴する言葉です。
花見(はなみ)
桜の花の美しさを堪能する場面を表しています。
日本ならではの風景を感じさせる言葉です。
夏

夏に関する二字熟語は、暑さや夏ならではの風物を表現しています。
活気に満ちた印象の言葉です。
盛夏(せいか)
最も夏らしい、夏の真っ盛りを示しています。
強い日差しのパワーを感じる言葉です。
夏祭(なつまつり)
夏に行われるお祭りを表しています。
地域独特の文化が楽しめる機会を表す言葉です。
納涼(のうりょう)
涼を求めるために避暑地へ行ったり、イベントに参加したりする様子を指しています。
暑い夏を快適に過ごしながら楽しむ印象のある言葉です。
避暑(ひしょ)
暑い夏を避けて、涼しい場所に訪れる場面を指しています。
穏やかな時間が期待できる言葉です。
涼風(りょうふう)
暑い季節に吹く心地よい風を表しています。
穏やかな安らぎを感じる言葉です。
秋

夏が終わり心地よい気候を感じるとともに、冬に向かう間の少し寂しいイメージを表現しています。
農作物の収穫など、豊かな実りを感じる季節です。
紅葉(こうよう)
樹木の葉が赤や黄色に色づく自然現象です。
秋ならではの美しさを感じられます。
月見(つきみ)
中秋の名月やそれに近い時期の満月を鑑賞しながら、月の美しさを楽しむ行事を表しています。
中秋の名月の日は月の満ち欠けで毎年異なり、9月から10月頃に該当する日です。
晩秋(ばんしゅう)
秋の終わり頃を表す言葉です。
日本では10月下旬から12月上旬ごろを指すのが一般的と言われています。
豊穣(ほうじょう)
穀物が豊かに実る様子を表しています。
自然の恵みを感じ、収穫の喜びを分かち合う印象の言葉です。
夜長(よなが)
静かで長い夜を穏やかに楽しむシーンで使われます。
ゆったりとした時間が流れる印象の言葉です。
冬

寒さにより、凛とした冷たい空気を感じる様子を表現しています。
雪景色の美しさも楽しめる季節です。
寒波(かんぱ)
寒気が入り、気温が急激に下がる現象を表しています。
冬の到来を実感する言葉です。
霜月(しもつき)
霜月は11月のことです。
だんだん寒くなり、霜が降りる時期を表しています。
冬の訪れを感じる言葉です。
冬至(とうじ)
1年のうちで昼の時間がもっとも短い日です。
冬至の日は毎年変動しますが、12月20日前後にあたります。
また、無病息災のためにゆず湯に入る習慣があります。
白銀(はくぎん)
一般的には貴金属の銀を指しますが、季節の場合は降り積もった雪を表現しています。
雪の清らかさが感じられる言葉です。
冬空(ふゆぞら)
冷たい空気の中で、凛とした雰囲気を感じます。
冬の光景が一段と美しく見える様子を表す言葉です。
天気に関する二字熟語【五十音順】
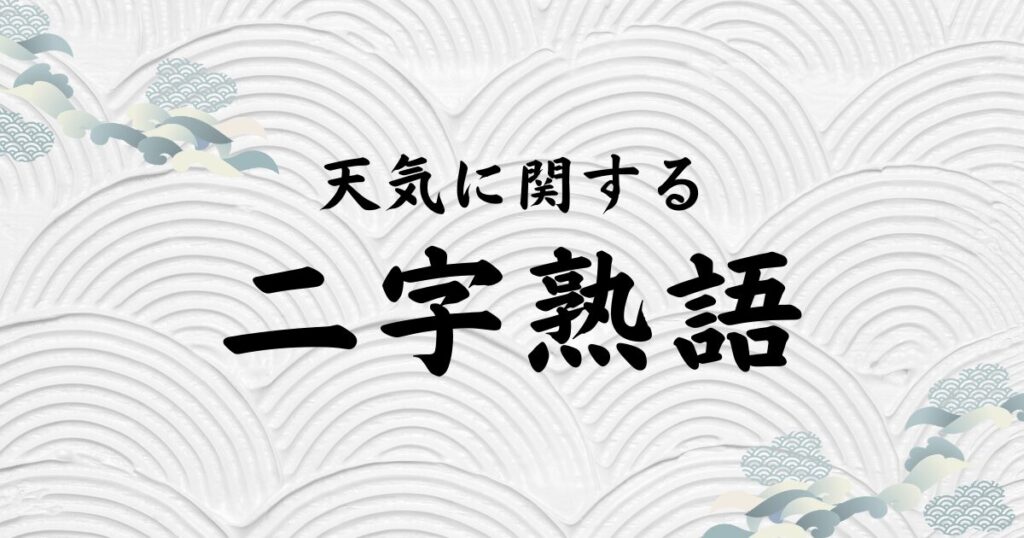
天気に関する二字熟語20選を解説します。
四季によって異なる日本の天候を表す言葉です。
青空(あおぞら)
よく晴れ渡った、青い空を表しています。
鮮やかで澄み切った青を感じられる言葉です。
朝霧(あさぎり)
早朝に霧が立ち込めている状態を指しています。
幻想的な風景が見え、神秘的なイメージを持つ言葉です。
雨露(あめつゆ、うろ)
雨と露により、繊細な美しさを感じられます。
「うろ」と読む場合「大きな恩恵」の意味もあります。
薄日(うすび)
薄雲を通した、かすかな日の光を示しています。
光と影のコントラストが穏やかなイメージの言葉です。
雲海(うんかい)
山や飛行機など、高いところから見下ろした際に見える雲を表しています。
雲が一面に広がり、海のように見える様子です。
快晴(かいせい)
雲1つないほど気持ち良く晴れている状況を指しています。
心身ともにリフレッシュできるような印象の言葉です。
霧雨(きりさめ)
霧のような細かい雨を指しています。
秋の季語としても使える言葉です。
雲間(くもま)
雲の切れ間から青空が見える状態を示しています。
幻想的な印象のある言葉です。
晴朗(せいろう)
晴れやかで明るい様子や、心地よい空気感を表しています。
「朗」には「ほがらか」や「明るい」という意味があります。
曇りなく澄んだ、気持ちの良い気候を感じる言葉です。
晴天(せいてん)
空がすっきり晴れ渡っている様子を示しています。
気分が晴れやかになる言葉です。
層雲(そううん)
層状または霧状の雲を表現しています。
静けさと穏やかさを感じる雰囲気の言葉です。
台風(たいふう)
台風は熱帯の海上でできた低気圧が発達したものと言われています。
自然の猛威が感じられる言葉です。
曇天(どんてん)
どんよりと曇った天候を表しています。
空が雲で覆われ、薄暗い印象を持つ言葉です。
濃霧(のうむ)
深い霧を表しています。
ぼんやりとしつつ、神秘的な印象がある言葉です。
霧中(むちゅう)
霧が立ち込め、周りの景色がわからないほどの場面で用いられます。
転じて、見通しがつかない状態も示す言葉です。
暴風(ぼうふう)
非常に強く激しい風が吹き荒れている様子を表しています。
自然の恐ろしさを感じる言葉です。
雷雨(らいう)
雷を伴った激しい雨を表しています。
自然の強い力を感じさせる言葉です。
雷光(らいこう)
雷の光を表しています。
暗闇を一瞬で切り裂くような印象の言葉です。
雷鳴(らいめい)
雷が鳴り響き、光も発生している様子を表しています。
自然の圧倒的なエネルギーを感じさせる言葉です。
陽光(ようこう)
空から降り注ぐ太陽の光を表しています。
明るい未来や希望が想像できる言葉です。
□に入る共通の漢字は?二字熟語クイズ
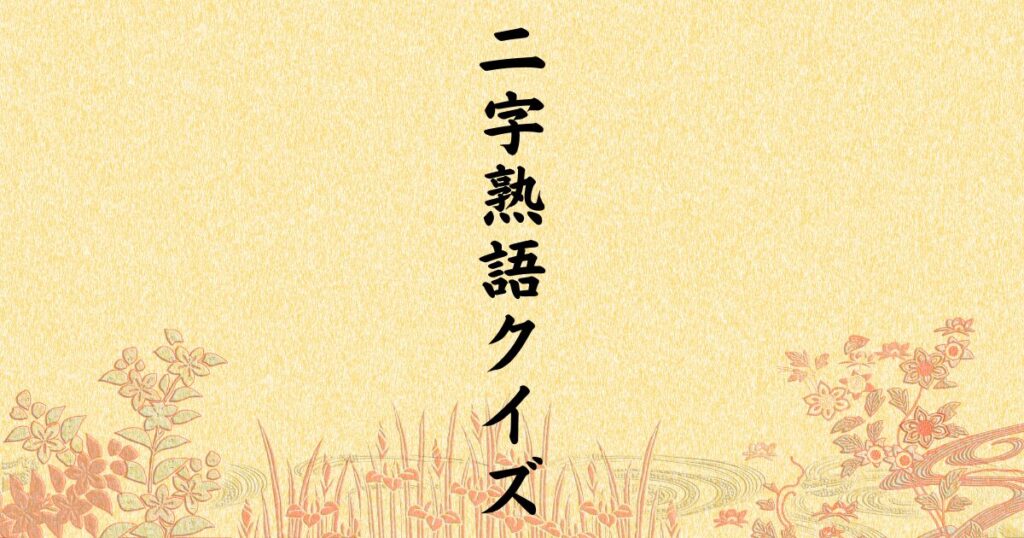
難易度低、中、高の二字熟語クイズです。
ゲーム感覚で楽しく学べます。
新しい表現を知る機会になるかもしれません。
ぜひお試しください。
難易度:低
| 毎 | ||
| 曜 | ? | 刊 |
| 常 |
こちらは比較的、難易度が低めです。
□の?に入る漢字、わかりましたか?
正解は…「日」
毎日/曜日/日常/日刊
という4つの二字熟語になります。
難易度:中
| 今 | ||
| 深 | ? | 間 |
| 行 |
少しレベルを上げてみました。
□の?に入る漢字はなんでしょうか。
正解は…「夜」
今夜/深夜/夜行/夜間
という4つの二字熟語になります。
難易度:高
| 濃 | ||
| 朝 | ? | 散 |
| 笛 |
最後の問題はかなり難易度が高いです。
□の?に入る漢字を当ててみてください。
正解は…「霧」
濃霧/朝霧/霧笛/霧散
という4つの二字熟語になります。
いかがでしょうか?
楽しみながら二字熟語を知ることができたかと思います。
自分でクイズを作ってみるのもオススメですのでぜひ試してみてください!
まとめ:二字熟語をマスターして使いこなそう!
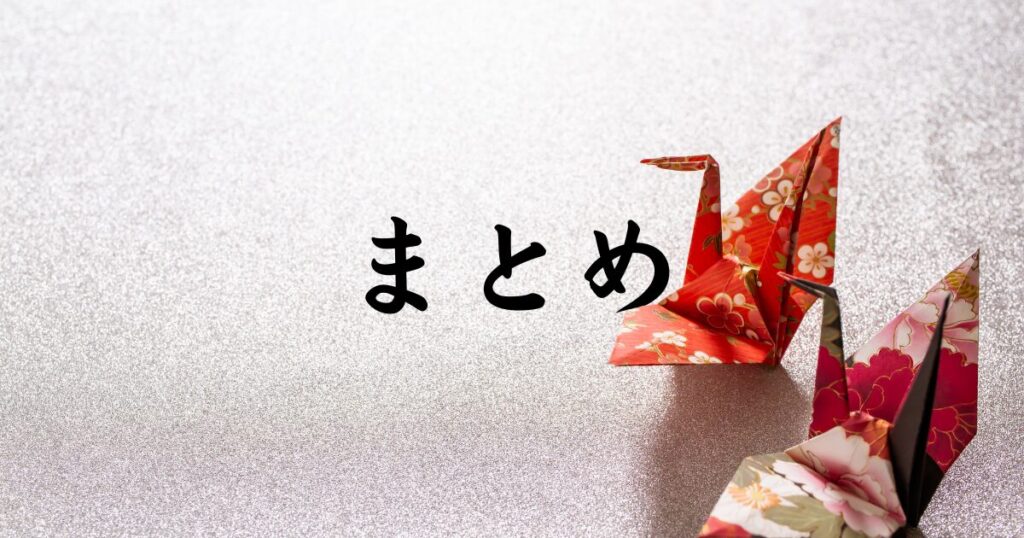
かっこいい、おしゃれ、美しい印象のある二字熟語100選をご紹介しました。
初めて見た二字熟語だと思われたものもあったかもしれません。
さまざまな表現を知り、日常生活で使ってみてください。
あなたの文章力がより高くなるでしょう。
また、キャッチコピーや目標、スローガンで使えば訴求力が高くなります。
人の心をグッと引きつける素敵な二字熟語をぜひ見つけてください。
二字熟語の面白さを知り、興味を持った方には、三字熟語についてまとめた記事もオススメです!
よろしければご覧ください。

「二字熟語」に関するよくある質問
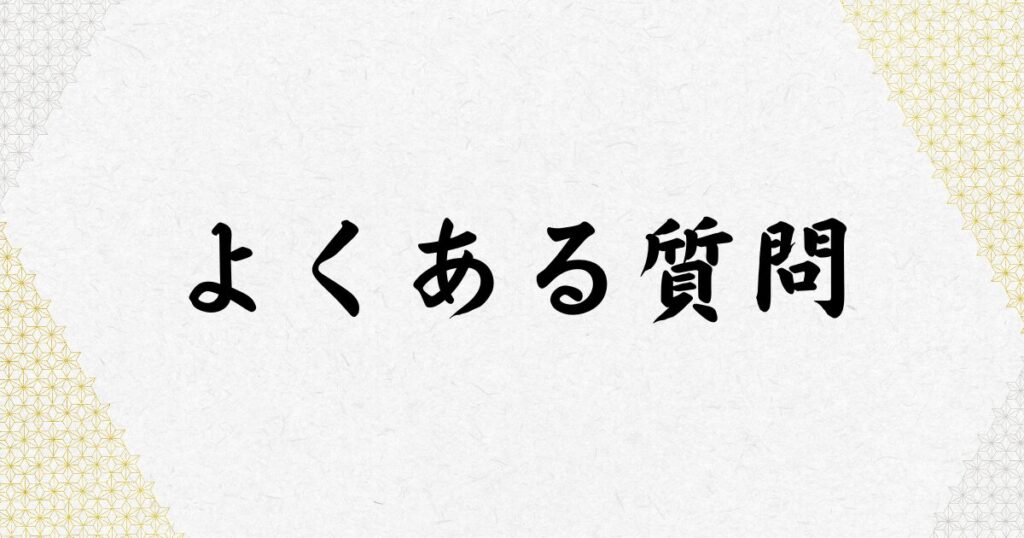
ここでは、二字熟語についてよくある質問をまとめました。ぜひご覧ください。
よくある質問①二字熟語と四字熟語の違いは何ですか?
二字熟語は短くて覚えやすく、伝えたい内容を簡単に表現できます。
四字熟語はその長さから、全体の響きやリズムが重視されることがあり、文学的な魅力を持っています。
よくある質問②重箱読みと湯桶(ゆとう)読みの違いは何ですか?
「重箱読み」は前が音読み、後ろが訓読みの二字熟語です。
例)重箱(ジュウばこ)、本屋(ホンや)、残高(ザンだか)
「湯桶読み」は前が訓読み、後ろが音読みの二字熟語です。
例)湯桶(ゆトウ)、長年(ながネン)、夕飯(ゆうハン)
重箱読みと湯桶読みは、いずれも二字熟語の変則的な読み方です。
読み方を耳で聞いたときに、分かりやすくするために作られたと言われています。